第1日目その2 2001年1月1日(月) 晴れ 日本橋−品川−川崎−神奈川−保土ヶ谷−戸塚
川崎宿
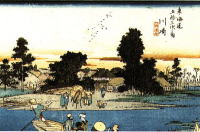 川崎宿が正規の宿になったのは元和9年(1623年)で、東海道では最も遅い。多摩川は古くは六郷川と呼ばれ、六郷大橋は慶長5年(1600年)に架橋された。元禄元年(1688年)の大洪水で流失してからは、船渡しとなった。
川崎宿が正規の宿になったのは元和9年(1623年)で、東海道では最も遅い。多摩川は古くは六郷川と呼ばれ、六郷大橋は慶長5年(1600年)に架橋された。元禄元年(1688年)の大洪水で流失してからは、船渡しとなった。

新六郷橋を渡り終えると、左へ行けば大師道、右が旧道(写真右)。東海道の分岐点にあった道標は、現在、川崎大師境内にある(実際の東海道の分岐点に2001年に新たな道標が設けられた)。 右折するとかつて奈良茶飯が有名で本陣より賑わったという万年屋を紹介する歴史案内板がある。旧東海道沿いではないが、川崎グランドホテル(川崎区宮本町6−2)ではランチタイムに奈良茶飯膳というメニューがある。万年屋の辺りから近道でこのグランドホテルに向かうと、現代の吉原と言える堀之内で飯盛女のごとく客引きに会いますのでお気をつけて。

旧東海道沿いの田中本陣裏手には、お閻魔様で知られる一行寺や、飯盛女の供養塔がある宗三寺がある。街道を進み、賑わいがなくなってきた辺り右手の馬島病院の脇に見附跡。
京浜急行の八丁畷駅手前には芭蕉句碑(写真左)「麦の穂をたよりにつかむ別れかな」。芭蕉はここで弟子たちと別れたそうであるが、この句碑の対面に一見大木戸のようなものがある。かつて貨物線が通っていたときの名残りであるようだ。踏切を渡って道の左側すぐのところにこの付近から出土した江戸時代の人骨の慰霊碑がある。駅名にある畷とはあぜ道のことで、八丁(約870メートル)続いていたようだ(実際の距離でなく、かなり長い距離を形容して用いられたとも)。駅の名前になっているが、現在そのような地名はない。
鶴見〜生麦

 八丁畷から最初の信号を超えると横浜市。鶴見市場には日本橋から5番目の一里塚跡(写真左)。左側だけ残っているのは、こちらにはお稲荷様が奉られていたから壊せなかったようだ。鶴見川橋手前右側にはちょっとした案内板が。鶴見川橋を渡ると右手に鶴見橋関門旧跡。自宅前の鶴見図書館では東海道や旅行ガイドブックなどの本をよく借りている。4月には公園前のサクラが咲き誇る(写真左:写真の右手は寺尾稲荷道道標)。 9時2分、自宅に到着。
八丁畷から最初の信号を超えると横浜市。鶴見市場には日本橋から5番目の一里塚跡(写真左)。左側だけ残っているのは、こちらにはお稲荷様が奉られていたから壊せなかったようだ。鶴見川橋手前右側にはちょっとした案内板が。鶴見川橋を渡ると右手に鶴見橋関門旧跡。自宅前の鶴見図書館では東海道や旅行ガイドブックなどの本をよく借りている。4月には公園前のサクラが咲き誇る(写真左:写真の右手は寺尾稲荷道道標)。 9時2分、自宅に到着。
鶴見の自宅でお雑煮とおせちを食べ、しばし休憩。11時10分から再び歩き始める。自宅から京急鶴見駅までは、1万回以上歩いている旧東海道。現在はマンションが立ち並ぶが、今思うと20年前は街道らしい道だったんだと回想してしまう。ラーメン屋の信楽茶屋は、この店名になったのは数年前。道なりに進み、信号のある小さな交差点手前右側に鶴見村の名主であった佐久間家の古い屋敷がある(2001年8月に解体されました)が、旧東海道を意識して歩いている人か何十年も前から住んでいる人でなければ、ただの古い家である。このような建物は他の地区にもたくさんあると思いますが、一般の人にもはっきり判るような案内板がない限り、民家の写真とか撮ってると不信に見られるだろうと思ってしまった。

京急鶴見駅のところの信号を渡ったら左手の駅へ向かうほうの道へ進み、ベルロード(旧鶴見銀座)という商店街に入る。右手のパン屋の脇にサボテン茶屋跡の石碑。しばらく進み左手には米(よね)饅頭を売る清月がある(ここは仮店舗で今は元の駅前の大通り沿いに移転、移転後の清月)。国道15号に突き当たったら、信号を渡り、道なりに斜めに入る道が旧道。レトロなJR鶴見線の国道駅を過ぎると生麦の魚河岸通り。少し大きな交差点は横断し直進し、道幅の狭い道を行く。左手にはキリンビアビレッジの工場が続き、駐車場の出入口付近に生麦事件碑があり、国道15号に合流。神奈川宿まで国道を進む。
神奈川宿
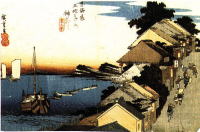 神奈川宿は、東海道有数の景勝地である「袖ヶ浦」を臨み、行楽地としても栄え、安政5年(1858年)の日米修好通商条約締結後は、開港場としても賑わった。
神奈川宿は、東海道有数の景勝地である「袖ヶ浦」を臨み、行楽地としても栄え、安政5年(1858年)の日米修好通商条約締結後は、開港場としても賑わった。
 生まれてからずっと神奈川県民であるが、神奈川は県の名前なのに、鉄道の駅としては京浜急行の普通列車しか停車しない小さな駅で、隣は横浜駅であるが、神奈川宿周辺が中心ではなく不思議に思っていた。東海道について調べているうちに色々判る事もあるもので、答えは幕末の政策によるものであった。 幕府が和親条約や通商条約を結んだ国々に対し、神奈川を外国人の居留地としたが、幕府が和洋混ざり合う生活を好まなかったので、当時は寒村だった横浜村に隔離する計画を立てた。条約には開港場は神奈川と明記されていたので、外交団は反論したが、幕府
生まれてからずっと神奈川県民であるが、神奈川は県の名前なのに、鉄道の駅としては京浜急行の普通列車しか停車しない小さな駅で、隣は横浜駅であるが、神奈川宿周辺が中心ではなく不思議に思っていた。東海道について調べているうちに色々判る事もあるもので、答えは幕末の政策によるものであった。 幕府が和親条約や通商条約を結んだ国々に対し、神奈川を外国人の居留地としたが、幕府が和洋混ざり合う生活を好まなかったので、当時は寒村だった横浜村に隔離する計画を立てた。条約には開港場は神奈川と明記されていたので、外交団は反論したが、幕府 は横浜も神奈川の中の小地名であるとこじつけ納得させたそうで、これから神奈川が広まったとのことである。
は横浜も神奈川の中の小地名であるとこじつけ納得させたそうで、これから神奈川が広まったとのことである。
話しを戻そう。神奈川宿本陣のあった位置からすると国道15号を直進するわけだが、京浜急行の神奈川新町駅付近からは右に1本入った道がお勧め。ただし、仲木戸・東神奈川駅近くの道の横断には気をつけましょう。お寺が立ち並び、高札場(復元:写真左)もあり、歴史案内板も数多く、町が力を入れている様子がわかる。
京浜急行線とJRの間に位置する慶運寺(写真右)はうらしま寺とも呼ばれている。滝の川を渡り、国道の方に歩くと途中に「滝の橋と本陣跡」の説明板がある。旧道は商店街を通って青木橋に出るようだ。
台町〜天王町
 青木橋で鉄道を超えるが、本来はまっすぐ台町に続いていた道なので、交差点を横断し、すぐに東急東横線のガードをくぐる道を行く。ガードをくぐってすぐ右手に大綱金比羅神社があるが、この辺りに神奈川宿の一里塚があったようである。
青木橋で鉄道を超えるが、本来はまっすぐ台町に続いていた道なので、交差点を横断し、すぐに東急東横線のガードをくぐる道を行く。ガードをくぐってすぐ右手に大綱金比羅神社があるが、この辺りに神奈川宿の一里塚があったようである。
この道が旧東海道ということは横浜市民でもほとんど知らないと思う。横浜駅から歩いて10分以内のところとは思えない落ち着いた街並み(写真左)であるが、広重画(神奈川-台の景)に見るような左手に海は見える気配すらない。
 首都高をくぐる手前から住所は南軽井沢。私は道なりに進んだが、東海道ルネッサンスのマップには、ここから浅間下の交差点まで環状1号が東海道となっている。道なりに進んだ場合、突き当たったところで、少し左に行き、大きな道路(新横浜通り)を横断し、左折し歩道橋手前の道を入る。ここは旧東海道を歩いている人にとってわかりにくいと言われている。富士山に続くと言われる穴がある浅間神社でお参り。東海道は神社前の道を進み、途中ちょっとみすぼらしい追分道標(写真右)。右折すると八王子往還らしい。東海道は直進し、いつも賑わっている松原商店街を通るが、元旦なのでひっそりしていた。ある本には「横浜のアメ横」と紹介されていた。
首都高をくぐる手前から住所は南軽井沢。私は道なりに進んだが、東海道ルネッサンスのマップには、ここから浅間下の交差点まで環状1号が東海道となっている。道なりに進んだ場合、突き当たったところで、少し左に行き、大きな道路(新横浜通り)を横断し、左折し歩道橋手前の道を入る。ここは旧東海道を歩いている人にとってわかりにくいと言われている。富士山に続くと言われる穴がある浅間神社でお参り。東海道は神社前の道を進み、途中ちょっとみすぼらしい追分道標(写真右)。右折すると八王子往還らしい。東海道は直進し、いつも賑わっている松原商店街を通るが、元旦なのでひっそりしていた。ある本には「横浜のアメ横」と紹介されていた。
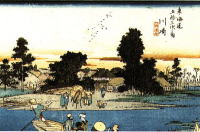 川崎宿が正規の宿になったのは元和9年(1623年)で、東海道では最も遅い。多摩川は古くは六郷川と呼ばれ、六郷大橋は慶長5年(1600年)に架橋された。元禄元年(1688年)の大洪水で流失してからは、船渡しとなった。
川崎宿が正規の宿になったのは元和9年(1623年)で、東海道では最も遅い。多摩川は古くは六郷川と呼ばれ、六郷大橋は慶長5年(1600年)に架橋された。元禄元年(1688年)の大洪水で流失してからは、船渡しとなった。


 八丁畷から最初の信号を超えると横浜市。鶴見市場には日本橋から5番目の一里塚跡(写真左)。左側だけ残っているのは、こちらにはお稲荷様が奉られていたから壊せなかったようだ。鶴見川橋手前右側にはちょっとした案内板が。鶴見川橋を渡ると右手に
八丁畷から最初の信号を超えると横浜市。鶴見市場には日本橋から5番目の一里塚跡(写真左)。左側だけ残っているのは、こちらにはお稲荷様が奉られていたから壊せなかったようだ。鶴見川橋手前右側にはちょっとした案内板が。鶴見川橋を渡ると右手に
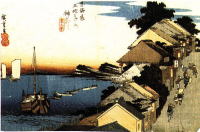 神奈川宿は、東海道有数の景勝地である「袖ヶ浦」を臨み、行楽地としても栄え、安政5年(1858年)の日米修好通商条約締結後は、開港場としても賑わった。
神奈川宿は、東海道有数の景勝地である「袖ヶ浦」を臨み、行楽地としても栄え、安政5年(1858年)の日米修好通商条約締結後は、開港場としても賑わった。 生まれてからずっと神奈川県民であるが、神奈川は県の名前なのに、鉄道の駅としては京浜急行の普通列車しか停車しない小さな駅で、隣は横浜駅であるが、神奈川宿周辺が中心ではなく不思議に思っていた。東海道について調べているうちに色々判る事もあるもので、答えは幕末の政策によるものであった。 幕府が和親条約や通商条約を結んだ国々に対し、神奈川を外国人の居留地としたが、幕府が和洋混ざり合う生活を好まなかったので、当時は寒村だった横浜村に隔離する計画を立てた。条約には開港場は神奈川と明記されていたので、外交団は反論したが、幕府
生まれてからずっと神奈川県民であるが、神奈川は県の名前なのに、鉄道の駅としては京浜急行の普通列車しか停車しない小さな駅で、隣は横浜駅であるが、神奈川宿周辺が中心ではなく不思議に思っていた。東海道について調べているうちに色々判る事もあるもので、答えは幕末の政策によるものであった。 幕府が和親条約や通商条約を結んだ国々に対し、神奈川を外国人の居留地としたが、幕府が和洋混ざり合う生活を好まなかったので、当時は寒村だった横浜村に隔離する計画を立てた。条約には開港場は神奈川と明記されていたので、外交団は反論したが、幕府 は横浜も神奈川の中の小地名であるとこじつけ納得させたそうで、これから神奈川が広まったとのことである。
は横浜も神奈川の中の小地名であるとこじつけ納得させたそうで、これから神奈川が広まったとのことである。 青木橋で鉄道を超えるが、本来はまっすぐ台町に続いていた道なので、交差点を横断し、すぐに東急東横線のガードをくぐる道を行く。ガードをくぐってすぐ右手に大綱金比羅神社があるが、この辺りに
青木橋で鉄道を超えるが、本来はまっすぐ台町に続いていた道なので、交差点を横断し、すぐに東急東横線のガードをくぐる道を行く。ガードをくぐってすぐ右手に大綱金比羅神社があるが、この辺りに 首都高をくぐる手前から住所は南軽井沢。私は道なりに進んだが、東海道ルネッサンスのマップには、ここから浅間下の交差点まで環状1号が東海道となっている。道なりに進んだ場合、突き当たったところで、少し左に行き、大きな道路(新横浜通り)を横断し、左折し歩道橋手前の道を入る。ここは旧東海道を歩いている人にとってわかりにくいと言われている。富士山に続くと言われる穴がある浅間神社でお参り。東海道は神社前の道を進み、途中ちょっとみすぼらしい追分道標(写真右)。右折すると八王子往還らしい。東海道は直進し、いつも賑わっている松原商店街を通るが、元旦なのでひっそりしていた。ある本には「横浜のアメ横」と紹介されていた。
首都高をくぐる手前から住所は南軽井沢。私は道なりに進んだが、東海道ルネッサンスのマップには、ここから浅間下の交差点まで環状1号が東海道となっている。道なりに進んだ場合、突き当たったところで、少し左に行き、大きな道路(新横浜通り)を横断し、左折し歩道橋手前の道を入る。ここは旧東海道を歩いている人にとってわかりにくいと言われている。富士山に続くと言われる穴がある浅間神社でお参り。東海道は神社前の道を進み、途中ちょっとみすぼらしい追分道標(写真右)。右折すると八王子往還らしい。東海道は直進し、いつも賑わっている松原商店街を通るが、元旦なのでひっそりしていた。ある本には「横浜のアメ横」と紹介されていた。