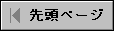カンボジアから伝来したのでこ
の名がある。古くから栽培され、
江戸時代にはトウナスと呼ばれ
た。夏に黄色い花を咲かせる。
夏の味覚の代表で、熱帯アフリ
カ原産。中央アジアを経て中国
から入ったので西瓜と書く。6月
から黄色い小花を咲かせる。
その生育環境とも相まって、いか
にも清々しい十字の白い花。文
政年間に江戸でワサビをはさん
だ握り寿司が考案された。
果実は猛毒で、「悪しき実」が名
の由来という。全体に香気があ
り、枝を仏事に用い、葉から抹香
をつくる。花は淡黄白色。




昔、中国の貴人が車の前の草
の名を従者に尋ねた。その名を
知らぬ従者が「車の前の草は車
前草」と頓知で答えたのが漢名
の由来という。白小花を穂状に。
名は犬ころ草の意味。穂の柔ら
かい毛が子犬の尾を思わせる。
穂に猫がじゃれつくので、「ネコ
ジャラシ」とも。身近で楽しい命
名である。
晩夏に地下に生ずる巻貝に似た
塊茎は食用で、赤く染めておせ
ち料理に用いる。「草石蚕」は塊
茎が蚕に似ていることに由来と
も。秋に紅紫色の小花を開く。
花嚢の内面に無数の花をつける
が、外からは見えないことから名
づけられた。世界的に最も古い
果樹。紀元前8世紀にはギリシ
ャで栽培されていたとの記録も。


稲や小麦とともに世界三大穀物
のひとつ。新大陸で古代から栽
培され、コロンブスによって旧大
陸にもたらされた。雄花穂は茎
頂に、雌花は茎の中程につく。
名の由来は、平安時代飢饉に備
え救荒食として植樹、葉の採取
貯蔵を命ずる法令が出たことか
ら。樹皮はなめらかで茶褐色。
材は床柱、良質の木炭となる。