第1日目その1 2000年7月9日(日) 晴れ 日本橋−内藤新宿−高井戸−国領
今日、街道歩きを始める記念すべき第一歩を踏み出す。夏場は歩くのはきついので、もう少し早い次期に歩き始めたかったが、土曜日は野球の試合や練習があったり、または雨降りという日が続いたので、今日になってしまった。
江戸を基点とする五街道(東海道・中山道・甲州街道・日光街道・奥州街道)のスタートは日本橋、と言うことで、まずは京浜東北線に乗り、東京駅に。駅から日本橋までは1キロほどである。
日本橋
現代は高速道路が頭上を走る日本橋では、これまではあまり気にも留めていなかった道路原標のレプリカや都市までの距離が書かれたものを写真に収め、午前10時5分に出発。気温はすでに30度ありそうである。
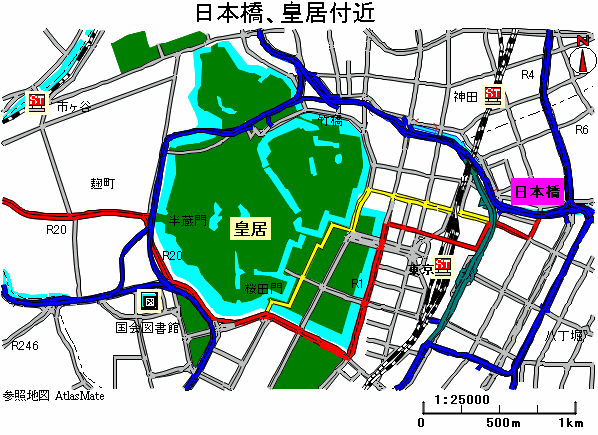



甲州街道は、東海道(中央通り)を150mほど南に進み、東急百貨店があった「日本橋」の交差点を右折、永代通りを進む。その後、私はJRのガードをくぐり、突き当たりの内堀通り大手門の交差点で左折、左手に東京駅が見えるところから皇居外苑内を歩いた。実際の甲州街道は、永代通りが外堀通りと交差する呉服橋の交差点を過ぎてから左折し、国際観光会館の裏から和田倉門に出て、現在の国道(日比谷通り)に沿って進んだようである。昔は、皇居外苑内などは歩けなかったのだろう。皇居外苑内は東京のど真ん中とは思えないほど広々としたところである(写真上中)。二重橋前(写真上右)を通り、桜田門をくぐり国道に出た。この道はこれから歩く甲州街道の現代の道である国道20号である。気温が高いので、三宅坂を登るだけで汗が噴き出す。半蔵門の交差点で左折し、新宿通り(国道20号)を進む。
内藤新宿
内藤新宿が宿場になったのは元禄11年(1698年)である。内藤とは、この周辺(四谷、代々木、千駄ヶ谷、大久保)が内藤氏の土地であったことによる。
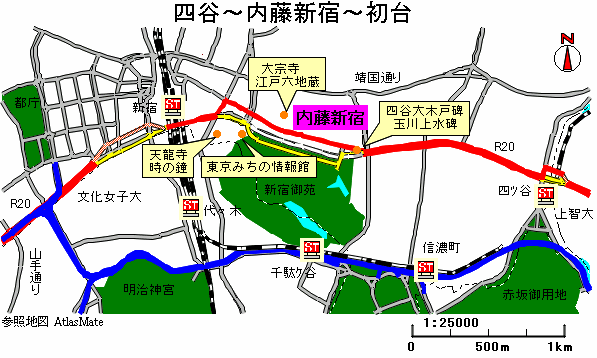
 |
| 晩秋の新宿御苑散策路 |
四谷駅のところは北側の外堀の内側に四谷見附門があったようで、新四谷見附橋を渡ってから新宿通りに戻る。 芸能プロダクション「サンミュージック」がある四谷四丁目の交差点から先、国道は地下に入る。甲州街道は、その右側の道を進む。国道の左側から一般の人は新宿御苑に入ることはできないようだ。交差点を渡ったところに、四谷大木戸跡碑と水道碑がある。そこのビル(四谷区民センター)の左側(裏)に回ると玉川上水記念碑がある。そこを出たところに内藤新宿開設三百年記念碑がある。そこから数十メートルのところに新宿御苑の大木戸門の入口がある。園内は有料であるが、甲州街道に沿った散策路は無料であり、歩くのに良い道である。
 実際に甲州街道ウォークとして歩いたとき、この界隈での寄り道は新宿駅周辺でパソコンの価格調査を少し行っただけであったが、他に立ち寄る価値のあるものがいくつかある。新宿御苑を出てすぐのところに「みちの情報館」(写真左)という建物があり、非常に惹かれる名称であったが、開館は平日のみで、土日・祝日は休館だったのでこの日は寄れなかった。国土交通省が運営していて、入場無料。平日に休みが取れたときに行ってみると、道路元標のレプリカなど日本橋に関するものや五街道に関するもの、また新宿の基盤整備事業に関するものなどが展示されていた。規模はそれほど大きくないが、日本橋についてのパンフや都内の「東海道さんさくマップ」などを貰ってきた。(2001年2月からは23区内の五街道のウォーキングマップが貰える)
実際に甲州街道ウォークとして歩いたとき、この界隈での寄り道は新宿駅周辺でパソコンの価格調査を少し行っただけであったが、他に立ち寄る価値のあるものがいくつかある。新宿御苑を出てすぐのところに「みちの情報館」(写真左)という建物があり、非常に惹かれる名称であったが、開館は平日のみで、土日・祝日は休館だったのでこの日は寄れなかった。国土交通省が運営していて、入場無料。平日に休みが取れたときに行ってみると、道路元標のレプリカなど日本橋に関するものや五街道に関するもの、また新宿の基盤整備事業に関するものなどが展示されていた。規模はそれほど大きくないが、日本橋についてのパンフや都内の「東海道さんさくマップ」などを貰ってきた。(2001年2月からは23区内の五街道のウォーキングマップが貰える)

 新宿御苑駅近くの大宗寺には江戸六地蔵のひとつである銅造地蔵菩薩坐像(写真左)があり、甲州街道を旅する人が旅の安全を祈願したそうである。新宿四丁目の明治通り沿いの天竜寺には「時の鐘」(別名:追い出しの鐘、写真右)がある。
新宿御苑駅近くの大宗寺には江戸六地蔵のひとつである銅造地蔵菩薩坐像(写真左)があり、甲州街道を旅する人が旅の安全を祈願したそうである。新宿四丁目の明治通り沿いの天竜寺には「時の鐘」(別名:追い出しの鐘、写真右)がある。
この「時の鐘」の近くに日本橋から2番目の一里塚があったそうである。
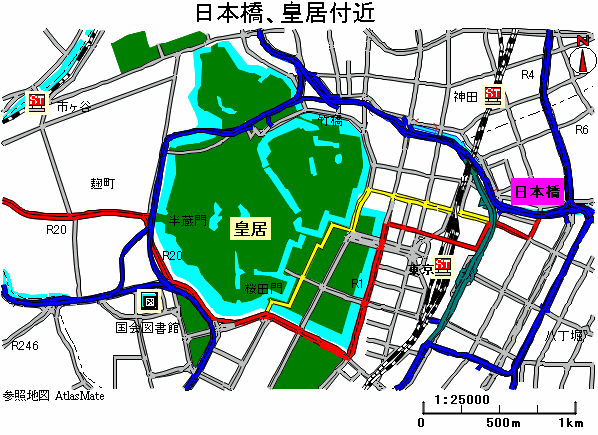



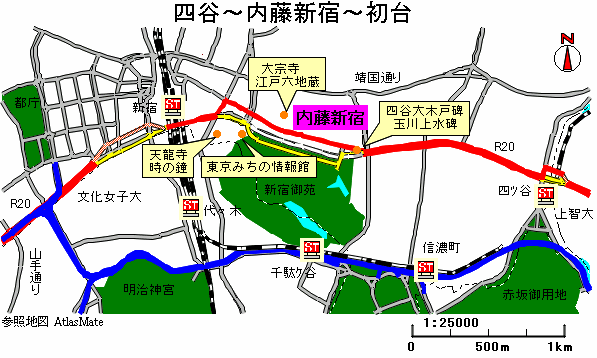

 実際に甲州街道ウォークとして歩いたとき、この界隈での寄り道は新宿駅周辺でパソコンの価格調査を少し行っただけであったが、他に立ち寄る価値のあるものがいくつかある。新宿御苑を出てすぐのところに「みちの情報館」(写真左)という建物があり、非常に惹かれる名称であったが、開館は平日のみで、土日・祝日は休館だったのでこの日は寄れなかった。国土交通省が運営していて、入場無料。平日に休みが取れたときに行ってみると、道路元標のレプリカなど日本橋に関するものや五街道に関するもの、また新宿の基盤整備事業に関するものなどが展示されていた。規模はそれほど大きくないが、日本橋についてのパンフや都内の「東海道さんさくマップ」などを貰ってきた。(2001年2月からは23区内の五街道のウォーキングマップが貰える)
実際に甲州街道ウォークとして歩いたとき、この界隈での寄り道は新宿駅周辺でパソコンの価格調査を少し行っただけであったが、他に立ち寄る価値のあるものがいくつかある。新宿御苑を出てすぐのところに「みちの情報館」(写真左)という建物があり、非常に惹かれる名称であったが、開館は平日のみで、土日・祝日は休館だったのでこの日は寄れなかった。国土交通省が運営していて、入場無料。平日に休みが取れたときに行ってみると、道路元標のレプリカなど日本橋に関するものや五街道に関するもの、また新宿の基盤整備事業に関するものなどが展示されていた。規模はそれほど大きくないが、日本橋についてのパンフや都内の「東海道さんさくマップ」などを貰ってきた。(2001年2月からは23区内の五街道のウォーキングマップが貰える)
 新宿御苑駅近くの大宗寺には江戸六地蔵のひとつである銅造地蔵菩薩坐像(写真左)があり、甲州街道を旅する人が旅の安全を祈願したそうである。新宿四丁目の明治通り沿いの天竜寺には「時の鐘」(別名:追い出しの鐘、写真右)がある。
新宿御苑駅近くの大宗寺には江戸六地蔵のひとつである銅造地蔵菩薩坐像(写真左)があり、甲州街道を旅する人が旅の安全を祈願したそうである。新宿四丁目の明治通り沿いの天竜寺には「時の鐘」(別名:追い出しの鐘、写真右)がある。