| <<What's New>> 2001年11月〜2002年6月 |
新しいバージョン(Green.w 4.20)が出たのでSUMI2000に入っているSPECTRA7400DDRのドライバーを更新した。
遊びに時計の取り扱い説明書をOCRでWordに変換してみているが、図(画像)の割合が大きいとスキャナーで読みとった画像全てをJPEG形式で保存した時のファイルサイズと余り変わらない事がある。そこでWordに貼り付けた画像を一度Photoshopに取り込みPNG(Portable Network Graphics)形式で出力してからWordの挿入で元の画像と入れ替えると画像部分のサイズが1/2以下になることが分かった。PNGで保存した画像データはそれ程劣化しないので、なかなか良さそうである。
では、最初からPNGで保存したらと言う発想も出てくるが、やはり文字データを使うためにはOCRで変換するしかないだろう。OCRは、例のe.Typistで、変換率は98%程度あり、それ程変換ミスに気を使うことなく利用できている。勿論、変換後おかしな所は赤字でポイントアウトしてくれる。
マイクロソフトのMS-Office互換でソフトのソースを公開しているフリーソフト(OpenOffice.org 1.0)を試してみた。Word, Excel, PowerPointとも相互に読み書きができた。ただし、OpenOfficeのデフォルトが英語仕様となっているため、MS-Officeで作成したファイルを読み込んだときに日本語フォントで表示されないなどの問題がある。また、表の形は殆ど引き継がれない様だ。それと、試してみた98SEでは保存時にフリーズするなど、まだ不安定だ。
日本のFTP DLサイトは混んではいるが、一度接続されればDLは意外と高速だった。
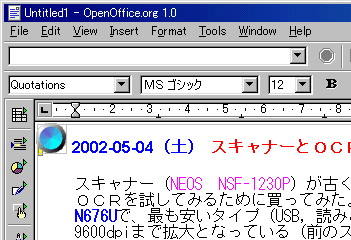
SUMI2000に入っているCanopusのSPECTRA 7400 DDRのドライバーを更新した。元々安定していたので、改善は目立たない。
- BIOS S2.13.04v
- Green.w Driver Ver.4.11
スキャナー(NEOS NSF-1230P)が古くなったのと、OCRを試してみるために買ってみた。スキャナーはキャノンのCanoScan N676Uで、最も安いタイプ(USB,読みとり精度600dpi)。ソフトウェア補完で9600dpiまで拡大となっている(前のスキャナーNSF-1230Pはハードで600dpi,ソフトウェア補完で1200dpi)。USBバスパワーなので、電源が要らず、配線がスッキリしている。さて、スキャン速度はと言うと、下表の通り。NSF-1230P(パラレル接続)に比べると実用範囲て約3倍となった。それほど速いわけではないが、実用上は問題ない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CanoScan N676Uのハンドルソフトの1つに、メディアドライブ(株)の日英バイリンガルOCR e-Typistエントリーがあった。
スキャナーのバンドルOCRソフトとしては、「読んでココ」とこの「e-Typist」が有名。
Webから両ソフトの体験版をダウンロードして変換精度を比較してみた。結果は、
- 英文・和文単独の変換精度は、e-Typistの方が上
- 日英混在文は、読んでココに軍配、と言うよりは、e-Typistには日英混在文の読みとりモードが無い。
- e-Typistには変換精度を上げる画像のノイズ除去機能がある。
この結果と、アップグレード版が使えると言う理由で、e-Typist V.7.0を購入した。
P.S. 日英混在文は、e-Typistでノイズを除去した後に、読んでココで変換するのがベストの様である。
プレインストールで入っていたウィルスチェックソフト(ノートンアンチウィルス2002)の有効期間が切れたので、ライセンスの余っていたウィルスバスター2002をインストールした。そこで気がついたのだが、登録されているメールアドレスが今は使っていないMedia Bank(mbn)だった。早速Webから新メールアドレスの変更手続きをしたが、1時間経ってもまだ通知が届かない。
PS. 4/8(月)10AMにやっと変更通知のメールが来ました。
先週、ケーブルを外して付け直して依頼、今の所は無事HDDもDVD-ROMも認識している。やっぱり原因は接触不良だったのか?
M/B側のIDEケーブルをMasterからSlaveにつなぎ変えても変化なし。HDDは別のマシンでは正常動作する。DVD-ROMだけ接続しても認識せず。デバイスマネージャのハードディスクには!マーク。
IDEケーブルを一度完全に外して再度接続したら、何と認識した。原因不明。ケーブル・コネクタの接触不良?。
最初IDEに接続していたHDDの認識がおかしくなったので調べていたら、今度は同じくIDEに接続していたDVD-ROMドライブも認識しなくなってしまった。RAIDドライブやその他の機器には異常はない。マザーボードの故障か?ケーブルが抜けかかっている?後で調べよう。
とある掲示板で話題となったので、調べてみました。SIでは、1k=1,000, 1M=1,000,000ですが、コンピュータの世界では、1KB=1024B, 1MB=1,024×1,024Bです。これが原因で、ADSLの世界では速度表示の定義がまちまちになっています。
(A) 1Mbps=1,000,000bps
(B) 1Mbps=1,024,000bps (1,024kbps)
(C) 1Mbps=1,048,576bps (1,024×1,024bps)現状を調べてみました。ADSL1.5Mはどうも(B)らしい。
▲1024派と●1000派を調べたら、2対5で●1000派の方が多いみたいです。以下データ
- ▲SpeedEye http://www.oak.dti.ne.jp/~flash/speedeye.html は1K=1024、1M=1024×1024(明記)派。
- ▲Line Speed Tester http://www.ne.jp/asahi/tsu/i/kubota/index.htm は1M=1024k派。
- ●インターネット回線速度調査 http://junkhunt.net/icsi/ は、1k=1000派(M表示無し)。
- ●ブロードバンドスピードテスト http://speed.on.arena.ne.jp/ は1k=1000、1M=1000×1000派。
- ●ぷらら http://wwwf.plala.or.jp/measure_speed/speed1_javaapplet/main.html は1k=1000派(M表示無し)。
- ●Radish Network Speed Testing http://hpcgi2.nifty.com/Radish/netspeed/index.cgi は1k=1000、1M=1000×1000派。
- ●SPEED TEST http://member.nifty.ne.jp/oso/speedtest/avg1M.html は1M=1000k派。
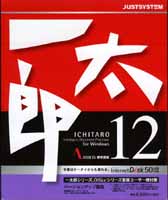
2/8(金)に発売された一太郎12を今日買ってきた。目的は従来と同じく、ATOKである。ヨドバシカメラでは、ATOK15単体が¥8,480なのに、一太郎12バージョンアップ版が¥7,680だったので、一太郎12にした。ATOK15には、最初の数文字を入力しただけで、使いたい言葉を推測して表示する推測変換機能が追加された。どんなものが登録されているか楽しみである。
これからインストールしてみる。
2/11追記
推測変換は、Tabキーだった。いくらスペースを押しても出てこないので、HPを見たら分かった。独自のキー操作は良くないよ→Just。
SUMI2000の方は、WinCDRの「起動ディスクの作成」で、ドライバー無しを選択。起動FDを作成後、OAKCDROM.SYSをそのFDにコピー。FDの中にあるCONFIG.DMPファイルを開き下記を追加したら、無事ブータブルCDの作成に成功した。
DEVICE=OAKCDROM.SYS /D:MSCD001
因みに、このOAKCDROM.SYSのタイムスタンプは、2001年3月30日、21:56:42このFDを使ってSUMI2000で作成したブータブルCDは、Proside改造機でもブートに成功。これで、一件落着となった。
Proside改造機、SUMI2000、何れのケースも最新のWinCDRでは、標準で作成したFDでブータブルCDを作成した場合、特定の環境ではCD-Rからブート出来なくなってしまったようだ。

CD-R/RWドライブによるブータブルCDの作成不具合の続きである。
1/23に書き込みソフト(WinCDR)を最新版(V7.0)にしてみたが、改善されなかったので、第2弾としてドライブを買ってみた。購入したのは、交換前と同じメーカー(ヤマハ)のCRW2100SX-VK(外付けSCSI型, R16X, RW10X, ROM40X)。ヨドバシカメラで特価の9,800円だった。40倍が出ている今時16倍と言うのも時代遅れだが、失敗しても安いのでこれにした。右の写真は、上からパナソニックのDVD-RAM(LF-D102, 2.6GBの旧タイプ), ヤマハのCD-R/RWドライブ(今回買ったCRW2100SX-VK), Proside改造機(P-III 800MHz, DVD-ROM, MO, HDラック付)。
結果はと言うと、やっぱりダメだった。
単にドライブの故障ではなかったようだ。もう一度、これまでの症状を整理してみると、
- 12月にProside改造機で作成したCD-Rや最近SUMI2000で作成したCD-Rは、Proside改造機のCD/DVD-ROMからブートできた。
- 最近Proside改造機で作成したCD-RはProside改造機でもSUMI2000でもブートできない。
- 最近分かった事:SUMI2000で作成したCD-RはProside改造機ではブートできるが、SUMI2000ではブートできなくなっていた。
- Proside改造機のOSはWindows 98SE、SUMI2000はWindows 2000
色々比較していたら、Proside改造機とSUMI2000でブート用FDの内容が違っている事に気がついた。SUMI2000のブート用FDにはOAKCDROM.SYSが入っていてCONFIG.SYSにも記述があるが、Proside改造機用にはなかった。
もしかしたら、と思いProside改造機のブート用FDにOAKCDROM.SYSを入れてCONFIG.SYSにもDEVICEを追記してみたら、無事CD-Rからブート出来るようになった。原因は、ここにあったようだ。Proside改造機は、単純なCD-ROMではなく、DVD-ROM(DVD-RAMやCD-ROMも読めるタイプ)だった事も原因を複雑にしていたようだ。では、SUMI2000で作成したブータブルCDがSUMI2000でブートできないのは何故か。SUMI2000を最初に組み立てた時にもCD-R/RWドライブからブートできたり出来なかったりした事があった。これもCD-R/RWとドライバーとの相性かもしれない。
SUMI2000は、これから調べてみよう。
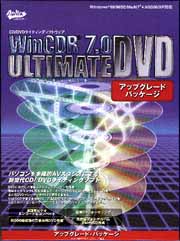 WinCDR
7.0 購入
WinCDR
7.0 購入CD-R/RWドライブでブータブルCDが出来なかったので、まず、書き込みソフトの最新版を購入してみた。買ったのは、アブリックスのWinCDR 7.0 ULTIMATE DVD(アップグレードパッケージ)。DVD-Rにも対応しているソフトである。勿論、NORTON Ghostが入っていて、ブータブルCDが作成できると書かれている。
早速、Proside改造機にインストールして試してみたが、結果は以前と変化なし。結局、焼いたCDからはブートできなかった。予想はしていたが、ソフトの問題ではなかったようである。ドライブを買わないとダメ?
HDDが故障したProside改造機のOS(Windows 98SE)を入れ直した。そこまでは良かったのだが、ある程度ソフトを入れた所でCドライブのイメージをWinCDR6.0(Ghost機能付き)でCD-Rにバックアップしていた所、チェックしてみたら何と焼いたCD-Rからブートできない事が分かった。それも再現性が無く、ブートできる事もあったので、原因を特定するのに手間取った。焼く側のCD-R/Wと読み込み側のDVD-ROMドライブのレンズをクリーニングキットで掃除してみたり、WinCDRやSCSIドライバーソフトなどのバージョンアップをしてみたが、一向に改善されなかった。焼いたCD-Rをもう1台のマシン(SUMI2000)で読み込んで見ると、結果が同じなので、どうも原因は焼く側にあるらしい。CD-R/RWは購入してからもう3年以上経つので、この辺りが怪しい。ただ、ソフトの問題もあるのでまだ結論には至っていない。
故障したHDD(DJNA-370910)をscandiskでチェックした結果、2台の内1台(5インチベイに設置してあった方)が不良クラスタ多発であった。そのHDDをFORMATして見ると更に不良クラスタが増加したので、廃棄した。もう1台のHDDはDOSのscandisk(クラスタスキャン)をクリアした。
今朝、何度かHDDをscandiskでチェックしていたら、遂にドライブCにも不良クラスタが出始めたので、結局HDDを交換した。
- 故障したHDDは、IBM製の9GBで、RAIDのために同じものを2台使用していた。
- HDD交換のためにパソコンのケースを開けたら、故障の原因が分かった。5インチベイ側に取り付けていたHDDのマウント用ファンの電源が接続されていなかったのだ。以前、五月蠅かったので、一寸外したのがそのままになっていた。このため、冷却不足で過熱したのだろう。scandiskがそれを更に助長したのか?
- 冷却用のファンを稼働させてみると確かに音はするが、それ程気になるほどのものではなかった。
- 新しく買ったHDDは、SEAGATEのST-340810A(UATA100、5400rpm、40GB)。低騒音と安さでこれにした。RAIDがUATA66だからこれで十分だろう。
- HDDを交換して起動したら、無事RAIDで76GBと表示された。ところが、Win98の起動FDでFDISKを実行したらサイズが何と10GBと表示された。OSが古いせいか?そこでWinMeの起動FDでFDISKを実行してみたら無事76GBと表示されたので、Cに20GB、残りの56GBをDに割り当てた。
- CをDOSからFORMAT後、Ghostで交換前にバックアップしておいたOSのCD-Rで復元を試みたが失敗。昨日の時点で既にOSがおかしくなっていて書き込みに失敗していたようだ。このCD-Rは即ゴミ箱行きとなった。仕方ないので、2001-12-01にバックアップしたOSをリストア。これは無事立ち上がった。
- DはWindowsからFORMAT(こちらの方がDOSより断然速い)。EにバックアップしてあったデータをDにコピー。
- 不足しているアプリソフトを追加(筆王、この時期これが最も大事)。これで無事復旧。
- 発端となったウィルスチェックを全ドライブで実行。無事完了した。
- 感想:SEAGATEは、動作時のヘッド音が静かだ。スピードは以前より遅くなった。5,400rpmだから仕方ない?
1月2日からProside改造機のHDDの具合が悪くなり、2日かけてDOS modeのscandiskで不良クラスタを修復する羽目に陥ってしまった。
- 今回トラブルが起きたのはWindows 98マシンで、RAIDで2台のHDDをストライプ(並列に接続して速度を2倍にする設定)とし、CとDの2つのパーティションに切っていた内のDドライブ(CがOS、Dがデータ)。
- 事の発端は、ウィルススキャンをしていた所、再起動してしまったので、変だなと思いWindowsのスキャンディスクをしてみたら、Dドライブで応答が無くなり、また再起動してしまった。
- このため、DOS上でscandiskを実行して不良クラスタを修復していた所、家族が電気炊飯器とオーブンと電子レンジを同時に使ったため停電してしまった。これで、さらに不良クラスタが増えてしまった(特に修復をしていた98%辺りで、ここに不良セクタが集中)。
- 不良セクターは全部で41個。殆どのファイルは修復でき、データをEドライブにバックアップ、DドライブをFORMAT後、データを戻した。
- ここで、念のためと思ってscandiskを実行したら、何とFORMAT前と同じセクターが不良で、再修復となってしまった。FORMATでは不良セクターは使用不可となると思っていたのが外れ。
- 不良クラスタ1個修復するのに10分程かかるので、41個修復するのにほぼ1日を費やした。それも2回だから、延べ2日。
- 所で、今回はCドライブも何度かチェックしてみたが、全くエラーなしだった。RAIDがストライプで2台のHDDをパラに使用している事を考えると、不良クラスタの原因は、HDDの劣化ではなく、Dドライブの使い方の問題だろうと推測される。
- したがって、今回はHDDは交換せずに、このまましばらく様子を見る事にする。
SUMI2000とLibretto(OSは共にWindows2000)でRWINによる速度変化を測定してみたら、違いが出た。SUMI2000とLibretto共にRWIN=32,120がピークとなっているが、SUMI2000は33,580で極端に速度低下をしている。この前は、VBのWebTrapが悪さをしていたが、まだ何かありそうな感じである。
BB: ブロードバンドスピードテスト
2MB: SPEED TEST
各点のデータ:測定サイト2MBのデータは10回、BBは2回の平均値。(測定時刻12-14時)
空いている時間帯に測定したらレコード更新。Broad Band Testで、6.8Mbpsが出た。また、昨日買ったLibretto L3でもRWIN=32,120では、BB Testで6.7Mbpsが出た。それでは、なぜ、同じWindows 2000のマシンSUMI2000では、RWIN=27,740で速度が下がるのか調べたら、原因はウィルスバスターのWeb Trapだった。これを外したら、SUMI2000でもRWIN=32,120で、6.8Mbpsが出た。
Windows 98 →
Windows 98/2000 →
SUMI2000 →
携帯用にミニノートパソコン(東芝 Libretto L3)を購入した。ヨドバシカメラで消費税込みで約15万円だった。ポイントが2万なので、実質は13万円。
仕様・その他
- OSがWindows 2000で、Norton AntiVirus 2002が入っていた。AntiVirusのパターン無料更新の有効期限は来年3月末で一寸短い。
- CPUはTransmeta Crusoe 600MHzで省電力タイプ、 Memは128MBで実用レベル、 HDD 20GBも画像を使わなければ大丈夫だろう。 画面は1280×600ドットの横長となっている。仮想モードでは、1600×1024まで対応している。画面は低温ポリシリコン液晶で非常に鮮明で明るい。この画面を見ていると、CRTが暗く感じてしまう。文字は標準では一寸小さいので、画面のプロパティ、デザインで大きいフォントに変更した。
- 本体サイズはA5以下だが、LAN内蔵なのでそのままADSLでインターネットに接続できた。ADSLダウンロード速度は1GHzのSUMI2000と遜色ない。ただし、画像を処理するサイトでは若干遅い。LANに関しては、勿論、SUMI2000の共有データにもアクセスできた(ワークグループ名はSUMI2000他に合わせた)。
- 標準でついているポインティングデバイスは使い慣れていないので、マウスを接続してみた。最初Jusyの光ミニマウス(USB)を接続したら動作しなかったので、Microsoft製のIntelliEye(Optical)に交換したら無事動いた。
このパソコンの最大のメリットは、キーボードの横に置いて2台同時に使えることである。並べて使ってみると、これは本当に便利だ。
ADSLの変更に伴い、HPもこれまでのドリームネットから、So-netに移した。So-netに変えてからレスポンスが非常に良くなった。その内、ドリームネットは退会する予定。
Win98で、MTU=1500, RWIN=32,120にしたら更にスピードが上がった。
測定サイト http://speed.on.arena.ne.jp/ v2.0.7
測定時刻 2001/12/16 19:31:41
回線種類/線路長 ADSL/0.0km
キャリア/プロバイダ ACCA 8Mbps/so-net
ホスト1 WebArena(NTTPC) 6.7Mbps(3063kB,3.8秒)
ホスト2 at-link(C&W IDC) 6.5Mbps(3063kB,4.0秒)
推定最大スループット 6.7Mbps(833kB/s)
コメント ACCA 8Mbpsとしてはかなり速いです!おめでとうございます。10Base-TのLANアダプタをご利用でしたら100Base-TX以上のものに替えるともっと速くなるかもしれません。(1/5)
ADSL 8Mになっても、Windows98は、Windows2000より変動が大きい。しかし、見方を変えると、Windows98は瞬間スピードがWindows2000よりも速い時があるとも言える。Windows98の平均速度は、Windows2000と同じ6.6Mbpsでもこの測定結果のように、瞬間では7.273Mbps(8Mbpsの91%)出ている。変動が大きい分ストリーミングには不利だが、小サイズファイルダウンロードではWindows2000よりも有利かもしれない。なお、WindowsXPは測定するサイトにって速度がマチマチで、RWINの適正値も違うので、調整の難しいOSだ。
測定サイト:SPEED TEST MTU=1500, RWIN=24820, Win98, P3-800MHz
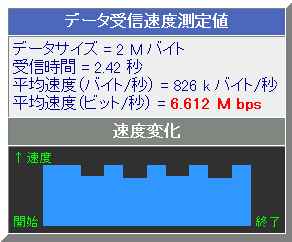
昨日、宅配便の再配達依頼をWebで入力し、確認メールのあて先をSo-netのアドレスにしておいた。所が、いつまで経ってもメールが来なかったので、変だなと思い、DreamNetからSo-netのアドレスにメールを送ってみたら、こちらも届かなかった。試しに、So-netからDreamNetへメールしたら、こちらは届いた。So-netで全受信を実行しても別にエラーも出なかったが、アカウントのプロパティを調べて見たところ、何故か「セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)」にチェックが付いていた。このチェックを外したら、無事受信出来るようになり、宅配便の確認メールも届いた。
そこまでは良かったが、一斉に受信されたメールの中に、以前ぷららの解約手続きをしたものに関するサポートセンターからの回答メールがあり、「入力不備ですので再登録してください」と書かれていた。もうとっくに手続きは終わって、「従量制のライト会員」になっていると思っていたのに、まだ解約されていなかったことが判明した。ぷららサポートセンターからのメール日付は11/21。と言うことは、3週間以上そのままになっていたようだ。慌ててもう一度、手続きをした。まあ、ぷららは1カ月1000円だから大した事はないが...。どうも、So-netのADSLが開通した11/17以降So-netのメールが届いていなかったようだ。回線がSo-netになった時点で他の3つのプロバイダーのメールは、幾つか送信できなくなったのでチェック・SMTP等の修正していたが、So-netは大丈夫だろうと思ってチェックしていなかった。ぷららの解約メールアドレスは、慣れないSo-netではなく、これまで使っていたDreamNet(mbn)にしておけば良かった。
昔のWordは、FD利用厳禁だった。空き容量の少ないFDで、FD内にあるWord文書を編集すると、FD内のデータが全て消えるという重大な不具合があり、長い間「Wordは、FDを使うな!」と言うのが定説だった。現在、それがどうなっているかをチェックしてみた。
FDに画像ファイルを入れて残り容量を少なくしてから、FDに入っているWordファイルを編集してみたら、次のようなエラーメッセージが出てFDのデータを壊すことは無かった。
ただし、編集中にFDを交換してみたら、下のようなメッセージが出て、やっぱり使えなかった。
今でもWordでFD利用はダメなようだ。
フリーの時刻合わせソフト(TClock)をSUMI2000とProside改造機に入れてみた。60分毎に時刻合わせ(同期)をする様に設定。サーバーは、clock.nc.fukuoka-u.ac.jp。これでパソコンも秒単位の精度になった。
RWIN=24820で再度速度を測定してみた。結果はピークは6.6Mbpsだった。
ただし、最近テレホーダイ時間帯になると速度が多少低下する傾向が出始めた。
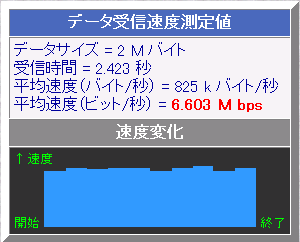
Windows XPでもほぼ同じスピードだった。↓
注)最適MTUの求め方: ping -f -l 1472 www.so-net.ne.jp でOKなら、
MTU=1472+28=1500 ダメなら2づつ小さくしていく。
MSS=MTU-40=1460
RWIN=MSS*n (n=10-200で実験で決める)
最適MTUは1500だったので、RWINを変えて速度を測定してみた。マシンはSUMI2000。
MSS=1460なので、その倍数でN=10から上げていった。
N=17(RWIN=24,820)にピーク(約6.5Mbps)があり、それを過ぎると急激に速度が低下した。
安定性を考慮するとN=16(RWIN=23,360)が良さそうだ。ここでも、6Mbpsは優に超えている。ブロードバンドスピードテストの80%領域の上側が5.0Mbpsを考えるとかなり高速である。
フレッツADSLの時の1.3Mbpsと比べると約5倍になり、1Mbpsのストリーミングでも、全く問題なく見られるようになった。
この2日間の様子を見た所では、テレホーダイ時間帯でも速度の低下はない様である。因みに、自宅は、NTT収容局から直線で約100m。
モデムの状態を見ると、Down=8,064kbps, Up=1,024kbps, SNR Margin=10.0dBとなっている。
昨夜(11/16)モデム(写真)が到着して、So-net ADSL 8Mが開通した。RWINを調整したらブロードバンドスピードテストで、何と、5.9Mbpsが出た。23時台の速度低下もなく快調だ。
MTU=1500 RWIN=20440
測定サイト http://speed.on.arena.ne.jp/ v2.0.7
測定時刻 2001/11/16 22:23:41
回線種類/線路長 ADSL/0.0km
キャリア/プロバイダ ACCA 8Mbps/so-net
ホスト1 WebArena 5.8Mbps(1441kB,2.2秒)
ホスト2 fas.ne.jp 5.9Mbps(1441kB,2.2秒)
推定スループット 5.9Mbps(737kB/s)
コメント ACCA 8Mbpsとしてはかなり速いです!おめでとうございます!(1/5)
友人からデジカメで撮影した写真の配信を頼まれたが、メモリーが普段使っていないSmart Mediaだったので、データをパソコンに取り込むためにPCカードリーダーを購入した。購入したのはLogitecの LPM-CA30MSUでメモリースティックやSmart Media、CFなどのメモリーの読み書きができ、パソコンとはUSBで接続するタイプ。ヨドバシカメラで10,800円だった。Smart MediaとCFからは写真データが読み取りできた。メモリースティックは持っていないので、チェックできず。友人の写真データをPhotoshopで加工して無事配信の準備ができた。
so-netのADSL 8Mに切り替えるため、フレッツADSLを解約して、昨日から普通の電話回線に戻っている。so-netのADSL接続(キャリア)会社はACCAで、フレッツADSLの解約時期について何度か電話した結果、電話回線の変更が昨日になった。このまま順調に行けば、来週、ACCAがNTTに依頼した回線の調査結果がメールで通知され、その次の週、11/19(月)頃に8MのADSLが開通する予定である。それまでの間約2週間は、昔のアナログモデムでインターネットに接続することになる。ADSLの掲示板を見ると、同日にフレッツとACCAの切り替えができた人もいるようで、随分とバラツキがあるようだ。
11/2(金)にウィルスバスター2002(VB2002)が発売された。Web側でもバージョンアップが開始されたので早速ダウンロードしてVB2001をVB2002にしてみた。ファイルサイズは33.3MBと大きく、モデムでは無理なサイズだが、ADSLだと4分程度でダウンロードが完了した。
HPの指示どおりに、VB2001をアンインストールしてから、VB2002をインストールした。
見た目は、少しカラフルになった程度で、操作体系は余り変わっていないようだ。多少変わったところと言えば、ファイアウォール(FW)のセキュリティレベルが3段階になり、簡単に変えられるようになっている位である。VB2001のWindows2000用FWはネットワークに設定があったため使いづらかったので、この点は改良されている。
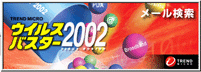
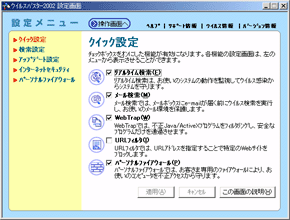
![]()
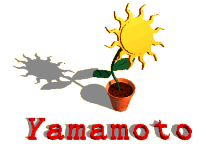
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る