| <<What's New>> パソコン奮闘記 2002年6月〜2002年10月 |
![]()
![]() 2002-10-19(土) 今日のリンク速度は9568kbps
2002-10-19(土) 今日のリンク速度は9568kbps
TVを消した状態でモデムの電源を入れると下りのリンク速度が9568kbpsとなった。まだ、10Mには達していないが、まあ、この程度なら良いだろう。
試しにNTT-ATのフィルタ(DMJ 6-2L)を付けてみたがリンク速度に変わりはなかった。むしろ、ATENが10dBに増加した。TVノイズが多い時には効果があるかもしれない。
下り方向 上り方向 回線状態 ADSLリンク速度 9568 kbps 1024 kbps SNR 6.5 dB - インタリーブディレイ 4 msec 4 msec ATEN(線路損失) 9 dB 0 dB 回線警報 ADSLレイヤ FEC(エラー訂正数) 784 647 CRC(エラー数) 0 0 ATMレイヤ HEC(ヘッダエラー数) 0 0 送受信フレーム数 30793 17113 スループットは、測定時刻によって大きく変化する。IP網が混んできたためだろう。今朝測定した中のレコードは7.1Mbpsだった。これまでの最高値だが、変動が大きくたまたまの値と言う感じだ。10Mになっても、RWINは、従来からの32120が適当な様である。これよりも大きいと、実行速度測定掲示板の図に途切れが出てしまう。
![]() 2002-10-18(金) 今日からADSLが10Mになる
2002-10-18(金) 今日からADSLが10Mになる
やっと今日から10Mになった。下りのリンク速度は、僅かに10Mを切る 9,440kbps だった。モデムの直ぐ近くにTVがあるので、それが影響しているかもしれない。 上りは、最大の 1,024kbps。
モデムの回線状況
下り方向 上り方向 回線状態 ADSLリンク速度 9440 kbps 1024 kbps SNR 6.5 dB - インタリーブディレイ 4 msec 4 msec ATEN(線路損失) 9 dB 0 dB 回線警報 ADSLレイヤ FEC(エラー訂正数) 1418 121 CRC(エラー数) 0 0 ATMレイヤ HEC(ヘッダエラー数) 0 0 送受信フレーム数 4 4 エラー訂正数が一寸多いようだ。
10Mになったので、スループットを測定してみたが、8Mの時と殆ど変わりない。午後9時で3-5Mbpsしか出ていないので、やはりSo-netのバックボーン(横浜の地域IP網)が細いようだ。
午後11時には、いつもより早く1Mbps以下まで低下してしまった。23日に緊急メンテナンスがあるらしい。これで早くなる?
2002年10月23日(水) 02時00分 〜 05時00分
【緊急】神奈川エリア通信機器メンテナンス作業先ほど、ACCAの12M対応スケジュールを見てみたら、この地区は既に「対応完了」となっていた。このまえは、10/28と書かれていたので、早まったようだ。でも、まだACCAからの連絡はない。モデムが不足しているのか?
![]() 2002-10-14(月) 防振ケースの中のHDDが動作不良、静穏HDDを購入
2002-10-14(月) 防振ケースの中のHDDが動作不良、静穏HDDを購入
昨日、振動が大きくなった防振ケースの中のHDDが動作不良となってしまった。BIOSで時々検出されなくなったり、シーク音が止まらず、なかなかデータの読み書きが出来ない状態になったりする。HDDを防振ケースに入れたのと、パソコンケースのファンを静穏タイプに交換したために、冷却不足となって過熱で動作不良となったのだろうか。使っていたHDDは、IBMのIC35L040AVER07。IBMのHDDは熱に弱いと言う噂がある。
仕方ないので、横浜へ行って新しいHDDを買ってきた。今回買ったのは、静穏で定評のあるSeagateのBarracuda ATA IV ST360021A (7,200rpm、60GB、流体軸受け)(ヨドバシカメラで10,490円)。最近発売されたIBMの静穏・高性能HDD Deskstar 180GXP IC35L060AVV207-0 (7,200rpm、60GB、流体軸受け)と比べてどちらにするか迷ったが、結局、値段と実績からSeagateにした。ちなみにIBMのIC35L060AVV207はソフマップで12,799円。なぜか一世代前のAVVA07も同じ値段だった。
行ったついでに、熱対策としてIDE用のスリムケーブルも買ってきた。一応UltraATA133対応。60cm、2ドライブ用で、2,480円。コネクタを抜くための輪がついているので、使い勝手はよさそう。
Barracuda ATA IV ST360021A と IDE用スリムケーブル 
買ってきたSeagateのHDDは、今度は防振ケースには入れず直接3.5インチベイに組み込んだ。SUMI2000の3.5インチラックは取り外せるので簡単にHDDを取り付けられる。ケーブルもフラットからスリムタイプに交換した。電源を入れてみると流石に新HDDは殆ど振動がなかった。ヘッドの音が気になったので、シーク音を減らすソフトsmscanをダウンロードして実行したら少し静かになった。ただ、シーク音の低減は、IBMのFeature Tool程ではなかった。
そう言えば、SUMI2000には、データ保存用としてIBMのDTLA307030が入っている。今まであまり気にしていなかったが、こちらは以外と静かだ。たまたま当たりだったのだろうか。
ソフトの入れ直しは、これから。ただし、一昨日Ghostでシステムをバックアップしてあるので、NTFSフォーマットができればRestoreは10分程度で完了する。
<動作不良HDDのチェック>
動作不良の起こったIBMのHDDを防振ケースから取り出して、リムーバブルケースに入れ、セカンダリのスレーブに接続してみたら、何と動作するではないか。ただし、うるさくてとても静穏PCに使えるレベルではない。どうも防振ケースに入れると、振動はパソコンケースには伝わらないがHDDそのものはかえって振動が大きくなってしまっていたようだ。この結果、ヘッドがトラックを捕まえきれずにデータのR/Wが出来なかったようだ。HDDそのものも振動が購入時よりは増加しているかもしれないが、防振ケースも今一だ。
やっぱり、静穏PCには流体軸受けか5,400rpmのHDDが必要なようだ。
![]() 2002-10-13(日) 振動は微妙、HDDの防振ケース調整
2002-10-13(日) 振動は微妙、HDDの防振ケース調整
なぜか、SUMI2000の電源入れたら低音の振動がする。ケースの蓋を開けて調べてみたら、防振ケースの振動がパソコンのケースに伝わって音が出ている事が分かった。この前、防振ケースの位置を変えたら共振が止まっていたのだが、やはり不安定な改善だった様だ。本質的には、低振動HDDを使用するのが正解だろうが、とりあえず出来る範囲で調整してみた。
- 防振ケースの蓋が5インチベイに取り付ける金具と接触しないように、蓋をずらす。
- 取り付け金具と防振ケースを繋ないでいるビスを緩める。締めすぎていて防振ゴムの効果が発揮されていなかったみたいだ。
これで、完全ではないが振動が減った。振動音はするが、安定しているので、それほど耳障りではない。それにしても振動は微妙だ。
関係ないが、ADSL 10M開通予定の10/18まで、あと5日。Adobe GOLiveは文字化けするので、今回から、PageMillに戻した。
![]() 2002-09-30(月) 12M対応は10月下旬
2002-09-30(月) 12M対応は10月下旬
ACCAのHPを見たら、12Mの対応スケジュールが載っていた。この地区は10月下旬のようだ。10M対応が10/18だから、その後直ぐと言うことになる。モデムも交換だろうから一寸無駄のような気もするが、楽しみが増えたのは歓迎。
![]() 2002-09-26(木) ハードディスクが無音になる
2002-09-26(木) ハードディスクが無音になる
SUMI2000には、IBMのハードディスクが2個入っている。試しにIBM Feature ToolでLowest acoustic emanation setting (Quiet Seek Mode)にしたらシークが無音になった。今更だが、駄目押し改善で安心感が増した。
![]() 2002-09-24(火) SUMI2000が殆ど無音になる
2002-09-24(火) SUMI2000が殆ど無音になる
昨日まで、ハードディスクの振動がパソコンケースに伝わって低音のうなりがあったが、防振ケースの取り付け位置を10mmほど手前にズラしたら振動がなくなった。この結果、耳障りな低音成分がとれて殆ど無音に近い状態になった。耳を澄ますと僅かにファンの排気音がするだけで、全く気にならない。これで、SUMI2000の静穏化は完了。
![]() 2002-09-23(月) HDD防音/防振ケースを購入(SUMI2000用)
2002-09-23(月) HDD防音/防振ケースを購入(SUMI2000用)
ハードディスクの動作音を更に抑えるために、ジャパンバリューのHDD防音/防振ケース(Hard disk quiet sound box PH-35B Light)を購入した。高速電脳で4,800円(写真を取り忘れたのでマニュアルからスキャナで取り込んだ→)。このケースの売りは、静穏・防振・冷却効果、電磁波対策である。
HDD(IBM-IC35L040AVER07)のコントロールチップ3つにグリースを塗ったアルミ板を取り付けケースに組み込んだ。
結果:シーク音は完全ではないが、かなり小さくなった。低音成分が少し残っているようだ。
◆SUMI2000は、SUMI05(Owltech Silent)より静かになり、通常の使用では動作音が気にならなくなった◆
![]() 2002-09-23(月) ハードディスクの交換で少し静かに(SUMI2000)
2002-09-23(月) ハードディスクの交換で少し静かに(SUMI2000)
SUMI2000のハードディスク動作音が気になったので、手持ちのものに交換したらヘッド移動時のシーク音が少し減った。でも、まだSUMI05には及ばない。良く調べてみると、SUMI05のハードディスクは、静穏で定評のあるSeagateのST340810A (40GB)だった。安かったので買っただけだったので、静穏とは気が付かなかった。
SUMI2000のHDD:元 IBM-DTLA-307045 → 新 IBM-IC35L040AVER07
![]() 2002-09-21(土) SUMI2000の騒音発生源は電源ファンだった
2002-09-21(土) SUMI2000の騒音発生源は電源ファンだった
Webを検索していたら静穏化対策で「電源ファンの供給電圧を12Vから7Vに落とすとかなり効果がある」と言う記事を見つけたので、試してみようとSUMI2000の電源を外して中をみたらファンの電源ケーブルは、パルス対応の3ピンコネクタだった。これでは、コネクタピンの入れ替えができない。ファンは8cm型でケースファンと同じサイズ、コネクタも同じだ。それならと、この前買ってきた静穏ファンに交換する事にした。
今付いている静穏ファン2個の内、風量の大きそうなORIX製ファンをケース(リア)から外し、電源ファンと交換した。電源に付いていたファンも松下製(PanaFlo FBK-08A12M)だった。タイプはケースのもの(FBM-08A12L)とは違っていた。恐らく高風量型だろう。
ケースのリアには元々付いていた松下製のファン(FBM-08A12L)を取り付けた。
結果はと言うと、今度は効果覿面(てきめん)だった。騒音レベルはSUMI05以下となった。SUMI2000の騒音発生源は電源ファンだった。まだ、CPUファンやHDDから多少音はするが、気になるほどではない。ただし、パソコン起動時のHDDの音は相変わらず大きい。SUMI05のHDDは5400rpmタイプなので、ここに差が出ていると思われる。
![]() 2002-09-16(月) SUMI2000のケースファンを交換
2002-09-16(月) SUMI2000のケースファンを交換
SUMI05が静かになったので、今度はSUMI2000のケースファンを交換してみた。
結論から言うと、あまり効果がなかった。どうも、電源ファンやCPUファンなど、他の部分からも騒音が出ているようだ。立ち上げ時のHDDの音も結構気になる。
試しに、リムーバブルラックの開口部分を塞いでみたら、少し静かになった。


SANYO製ファン(1300rpm, 12dB)をフロントに、ORIX製ファン(1400rpm, 12dB)をリアーに取り付けた。元付いていたファンは、フロント、リアーともに松下製だった。
![]() 2002-09-11(水) また、最速の7.2Mbpsがでる。
2002-09-11(水) また、最速の7.2Mbpsがでる。
まだ、8Mなのにブロードバンドスピードテストで最速の7.2Mbpsが出た。一般には、リンク速度の84%、すなわち6.8Mbpsが最大と言われているので、ネットワークに何らかの変更があったと思われる。
測定サイト http://www.bspeedtest.com/ v2.0.8
測定時刻 2002/09/14 07:39:56
回線種類/線路長 ADSL/0.0km
キャリア/ISP ACCA 8Mbps/so-net
ホスト1 WebArena(NTTPC) 7.2Mbps(2244kB,2.8秒)
ホスト2 at-link(C&W IDC) 7.2Mbps(3063kB,3.9秒)
推定最大スループット 7.2Mbps(897kB/s)
コメント ACCA 8Mbpsとしてはかなり速いです!おめでとうございます。10Base-TのLANアダプタをご利用の場合100Base-TX以上のものに換装すると速度向上が期待できます。(1/5)
![]() 2002-09-11(水) 10M対応10/18に延期
2002-09-11(水) 10M対応10/18に延期
今日9/11は10M対応の日。帰って早速モデムのリンク速度を見てみたら、何と8Mのままだった。変だなと思い、ACCAの判定情報を確認したら、次のようなメッセージが書かれていた。これでは、12Mのスケジュールと変わらないではないか。どうなっているんだACCA!!!
スケジュール: 10月18日10Mbps対応完了予定
設備の都合により、10Mbps対応完了予定日が延期になりました。大変申し訳ありませんが、今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。
![]() 2002-09-10(火) 10Mまであと1日
2002-09-10(火) 10Mまであと1日
今日モデムのリンク速度を確認したが、まだ8Mだった。明日は予定通り10Mになるか?
![]() 2002-09-08(日) パソコンケース交換(PC静音化)
2002-09-08(日) パソコンケース交換(PC静音化)
Proside改造機の騒音が大きかったのでケースを交換した。新しいケースはOwltechのOWL-103-Silent(シーソニック社製300W電源、1,200rpmの2ボールベアリング静音タイプファン×2)。静音を売り物にしているケースである。FRESH FIELDで11,800円だった。
Proside改造機から部品を全て外し、新しいケースに組み直した。静音優先と言う事で、今回は、元入っていたRAID(FastTrak66)と5インチベイのHDDラックは入れなかった。この結果、ソフトはOSから全て入れ直しとなった。
結果は予想以上で、SUMI2000よりも静かになった。ただし、本体が静かになった分外付けのCD-RWやDVD-RAMドライブの音が余計目立つようになった。
ケースを交換したこのマシンは、これで元のProsideの部品が全てなくなったので、新しく「SUMI05」と名付けた。05の意味は?
PS. この記事とは関係ないが、今使っているAdobe Goliveでまた、入力文字の消失トラブルが発症してしまった。このソフトは欠陥か?
![]() 2002-09-07(土) カウントダウン10Mまであと4日
2002-09-07(土) カウントダウン10Mまであと4日
今の8Mが9/11(水)から10Mになる予定なので、現状のモデムのリンク状態を確認しておいた。
下り方向 上り方向 回線状態 ADSLリンク速度 8064 kbps 1024 kbps SNR 9.0-10.0 dB - インタリーブディレイ 4 msec 4 msec ATEN(線路損失) 12 dB 0 dB 回線警報 ADSLレイヤ FEC(エラー訂正数) 0 35 CRC(エラー数) 2 0 ATMレイヤ HEC(ヘッダエラー数) 0 0 送受信フレーム数 299 290 推定伝送距離: 約 0 Km
So-netに申し込んだ12Mコースに対してACCAから受付した旨のメールが届いた。10月中旬以降、順次開通の計画だそうだ。それまでは、今の8Mをそのまま使えると書かれていた。9/11開通予定の10Mがそのまま使えるのかは不明。
3ヶ月間利用料金が安くなる様なのでコース変更を申し込んだ。本当に12Mになるのは10月以降らしい。
前々からcoregaの切り替え器を接続すると、[Ctrl]キーや[Alt]キー、[Shift]キーの反応が鈍くなって使いづらかったので、外すことにした。キーボードとマウスが2セットになってしまったが、キーの反応が良くなったので、ストレスは少なくなった。それと、モニタの表示画質も良くなった(グレーバックの黒字右側に僅かにゴーストがあったのが消えた)ので、当分はこのままにしよう。
この地区の10M対応は9/11だが、早めに今使っている富士通のADSLモデムのファームウェアをバージョンアップしておこうと思い、モデムをチェックした所、バージョンはR2.30b1で既に10M対応となっている事が分かった。9/11まで、あと25日。
ファームウェアバージョン R2.30.b1
DSPファームバージョン Annex-C V.72
最近は色々なドライバーがWindows XPに対応してきたので、久々にXPを使用してみた。
この前入れたI-O DATAのUSB2.0ボードも問題なく使えたし、スキャナもスムーズだった。
XPの使用感は、2000よりも画面に中間色系が多用され、ボックスも丸みを帯びているので、柔らかい感じである。動作も安定してきたので、全体にXPの方が使いやすそうな雰囲気であった。
試用後、Windows2000に戻したが、そろそろメインマシンをXPに変えても良さそうな印象を受けた。
プロサイド改造機に使用しているASUSのP3用マザーボードP2B-FのBIOSの新Revisionがリリースされたので、更新した。新Revisionは1014 Beta 003。なぜ今頃、新Revisionが出たのかは不明だが、何はともあれ新しい方が気分は良い。
昨日8/9(金)にMicrosoftから日本語Wondows2000用のサービスパック3がリリースされたので、導入してみた。高速インストールを選択したらダウンロードを含めても5分程度で完了した。再起動後、プロパティを見ると確かにSP3となっていた。
NTT-ATのフィルタDMJ 6-2L(EMCフィルタ内蔵)の有無による差を比較してみた。どちらもリンク速度は最大の 8,064 kbps 、SN比も 10.0dbと同じだったが、キャリアチャートは微妙に違っていた。フィルタありの方は、ギザギザが多く、1,100kHz の低下が大きい。エラー訂正数はフィルタなしの方が少なかったので、こちらの方が良さそうだ。
フィルタあり
フィルタなし
7/24にモデムの交換を依頼しておいたら、何の連絡もなく突然今日モデムが届いた。依頼受理のメールが来ないのでそろそろ確認してみようかと思っていた所で、本当に突然だった。
早速、スピードを測定してみたら、これまでの最速である6.9Mbpsが出た。9/11の10Mbpsまで、あと、約1ヶ月だ。
測定サイト http://speed.on.arena.ne.jp/ v2.0.8
測定時刻 2002/08/07 16:59:15
回線種類/線路長 ADSL/0.0km
キャリア/ISP ACCA 8Mbps/so-net
ホスト1 WebArena(NTTPC) 6.9Mbps(3063kB,3.8秒)
ホスト2 at-link(C&W IDC) 6.8Mbps(3063kB,3.8秒)
推定最大スループット 6.9Mbps(860kB/s)
コメント ACCA 8Mbpsとしてはかなり速いです!おめでとうございます。10Base-TのLANアダプタをご利用の場合100Base-TX以上のものに換装すると速度向上が期待できます。(1/5)
旧U-Pageのカウンターから、U-Page+のカウンターに変更した。U-Page+カウンターは20種類あるが、黒バックに合うのが少ない。その中からNo.8(SC08)を選んだ。
これで、HPは全て新HPサービスU-Page+へ移行した。
GoLive 6.0体験版の立ち上がりが余りにも遅かったので、手持ちのGoLive 5.0をSUMI2000にインストールしてみた。 以下、使用感。
- 立ち上がり時間は30秒以内で、6.0より速い。
- 以前、Windows98SEで見られたような「文字の消失や文字化け」はWindows 2000では起きないようだ。
- 操作は、6.0 も 5.0 も殆ど変わらないように見える。
- 編集モードのマウススクロールボタンの反応が少し悪い。プレビューモードは正常。アップデートしたら直るかな?→自動ダウンロードが効かなかったので、手動でダウンロードしたが、直らなかった。
- 今の所は、GoLiveに付いているFTPで直接アップロード出来るようだ。PageMillも最初はアップロード出来ていたが、途中から出来なくなった。でも、GoLiveではFFFTPと同じPSCV(パッシブ)モードが追加されているから大丈夫かな?
- 色の種類がPageMillより増えている。その分、逆に選ぶのに時間がかかる。
- 画像の配置の仕方が変わっている。PageMillはメニューから挿入だったが、GoLiveでは、オブジェクトを配置してから画像を選択。
<因みに、この文章は、GoLive 5.0で書いています>
so-netのHPサービスがU-Page+になり、現在使っている黒バックのカウンターが12月には使えなくなる。このため、トップ画面を変更する必要が出てきたので、ホームページ作成ソフトを調べ始めた。IBMのホームページビルダーはメジャーだが、出来栄えが今ひとつである。やはり、MACで実績のあるAdobeが良いだろう。ヨドバシカメラでもトップに出てくるのがAdobeのGoLiveである。
AdobeのHPを見ていたら GoLive 6.0の体験版があったので、ダウンロードしてみた。ファイルサイズは107MBあり、8MのADSLでも5分以上かかった。
使ってみての第一印象は、「立ち上がりが遅い」の一言に尽きる。ソフトが立ち上がるまでに1分もかかる。P-IIIの1GHzではパワー不足の様だ。
ただし、一度立ち上がってしまえば、それなりに動くようだ。特殊な使い方をしなければ、今使っているPageMillと操作も似ているので違和感はない。まあ、使えそうだ。
2000年末にAdobe GoLive 5.0 を買った時には、入力した漢字が消えてしまうという不具合があり、使えなかった。もっとも、その時、不具合が出たOSはWindows98SEだった。最近はWindows2000がメインマシンになっているので、問題はないかも知れない。
このGoLive 6.0体験版は、今の所、漢字入力も含めて問題は出ていない。発売が今年4月なので、不具合もFIXされているのかもしれない。体験版の使用期間は30日なので、もう少し使ってみてから購入を考えよう。
もしかしたら、前のGoLive 5.0も今は安定しているかもしれないので、その内にこちらも試してみよう。
<因みに、この文章は、GoLive 6.0体験版で書いています>
e.Typist v.8.0 と 読んde!!ココ を比較してみた。スキャナは、先週買ったEPSON GT-9300UF。認識結果比較データとしては、読み取り解像度400dpiと600dpiの良い方を選んだ。
読んde!!ココは和文字に強く、e.Typistは英文字に強い様だ。
ただし、e.Typist v.8.0は販売開始直後と言う事もあり、パターン認識辞書に登録した文字が時々変換に利用されない事がある。その内修正されるだろう。認識率(文字数:誤/正)
対象 e.Typist 読んde!!ココ 備考 新聞 99.5%(4/846)* 100%(0/850) *問→間 など 雑誌DOS/V 99.8%(4/1816)** 99.7%(5/1815)** **情→惰 など 英和辞書(日本語部分) 99.2%(1/131) 99.2%(1/131) ィ→イ 英和辞書(英語部分) 99.1%(1/108) 95.4%(5/104)*** ***大文字小文字のミスが多い。 英語テキスト 100%(0/665) 99.8%(1/664) /→I
so-netから10MBまで無料のホームページサービスU-Page+が開始された。たまたまサービス開始日(7/10)にso-netのHPを見ていたらお知らせに出ていたので早速その日に登録しておいた。現在のホームページサービスU-Pageは5MBまで無料なので容量が2倍となっている。
新サービスでは、ホームページアドレスも新しいものとなる。アドレスが変わってしまうので、移行時には旧ページにメッセージを載せる必要があり、一寸面倒だ。現在のU-Pageは12月で終了するらしい。
現アドレス http://www18.u-page.so-net.ne.jp/sc5/sumiyama/
新アドレス http://www001.upp.so-net.ne.jp/yamamoto/
現在のデータを新アドレスにコピーして見た所、内容はそのままで利用出来きた。ただし、新カウンターは現在利用している黒バックがないので、U-Pageが終了する12月より前にはトップ画面のデザイン変更が必要だ。
7/26追記: 7/27から画面が新HPへ自動移動する様に設定(so-netに登録)した。
現在使っているNECのADSLモデム(ATUR110RC)は、10Mbpsに対応する予定がないらしいので、今日、ACCAのHPで富士通ADSLモデムへの交換を依頼した。数日中に配達日の連絡があるそうだ。ACCAによると、この地区の10Mbps対応は9月11日の予定。
今日、ACCAからメールが来ていたので、早速新バージョン(1.53NEFC.C1R)にアップした。バージョンアップは無事終了し、これでDNSアドレスを入力する事無く、2台目のマシンをインターネットに接続出来るようになった。スループットを測定してみたが、特に変化はなかった。ACCAでは、富士通モデムへの交換を推奨している様だが、熱暴走の噂があるので、このままにしておこう。機能は富士通の方が上のようだ。
PS. 比較表を良く見るとNECモデムは「10Mbps対応ファーム予定なし」となっているではないか。これは、期限の8/31までに交換すべきか?
スキャナがUSB2.0対応と言う事で速度を計ってみた。
- 48bitカラー、24bitカラー、グレーとも読み込み時間に差がない。
- EPSONのHPと同じ条件(カラー300dpi)での測定値は15秒(HPの16秒より多少速い)
- 最大は、48bitカラー600dpiの時で 5.54MB/s
- これはUSB1.1(MAX 12Mbps=1.5MB/s)の約4倍(USB2.0の効果あり)、
USB2.0(MAX 480Mbps=60MB/s)の10%以下(まだまだ余裕あり)読み込み時間(秒)
解像度 48bitカラー グレー 参考(N676Uのカラー) 75dpi
9
9
19
150dpi
12
12
22
300dpi
15
15
41
600dpi
37
37
178
1200dpi
197
197
- 読み込んだファイルサイズ(MB)
解像度 48bitカラー グレー 参考(N676Uのカラー) 75dpi
3.2
0.5
1.6
150dpi
12.8
2.1
6.4
300dpi
51.2
8.3
25.5
600dpi
204.9
33.2
102.0
1200dpi
819.4
132.6
- 読み込み速度(MB/秒)
解像度 48bitカラー グレー 参考(N676Uのカラー) 75dpi
0.36
0.06
0.08
150dpi
1.07
0.17
0.29
300dpi
3.41
0.55
0.62
600dpi
5.54
0.90
0.57
1200dpi
4.16
0.67
- このGT-9300UFは、48bitカラーやフィルムスキャンに対応しているので、その内、速度だけでなく、こちらの機能もチェックしてみよう。ただ、現在の画面は最大で32bitなのでどうなるのか?
スキャナの画質がOCRの結果に影響する事が分かったので、EPSONから今日発売されたGT-9300UF(2400dpi, USB2.0, フィルムスキャナ付)を購入してみた。付属のOCRソフト「読んdeココ」とこの前買った「e.Typist」で色々な条件でスキャン変換してみた結果、e.Typist v.8.0のスキャナドライバーでの濃度自動が最適であることが分かった。OCR付属のサンプルは、300dpi、雑誌は600dpiが適当なようだ。600dpiで、例のDOS/V SPECIAL 8月号P158を読んで見た所、アンダーバーが空白となった以外は、完全に変換された。アンダーバーが空白となるのは、e.Typistの自動範囲指定の問題のようだ*1。
<GT-9300UF, e.Typist v.8.0の変換結果>
今回はファイルが作成された時を監視したいので、Createdを選択します。すると、FileSystem Watcher1□Createdプロシージャが作成されます。
USB2.0のスピード効果はこれから測定。
*1: 読みとり時に少し角度を付けたらアンダーバーまで認識範囲に入って変換できた(7/20追記)。
試しに、古いスキャナNEOSのNSF-1230Pでスキャンしてe.Typist v.8.0で変換してみたら、昨日の例が完璧に変換された。
<NSF-1230Pで読み込み変換>
今回はファイルが作成された時を監視したいので、Createdを選択します。すると、FileSystemWatcher1_Createdプロシージャが作成されます。
両スキャナーの画像を比較してみると、僅かではあるがNEOSの方が文字の縁が鮮明である。取り込んだ画像の質が認識率に影響しているようだ。
Canon N676U
NEOS NSF-1230P
昨日、7/12(金)にe.Typistのv.8.0が出たので、買ってみた。DOS/V SPECIAL 8月号のP158をv.7.0とv.8.0で、同条件でスキャンしてみた(日本語モード、グレースケール、400dpi)。v.8.0の方がレイアウトをより正確に判定した。ただし、変換時間が長くなっている。
文字変換精度:v.7.0もv.8.0も日本語は殆どミスなく変換しているが、v.8.0は「ー」が「・」に化ける事が多い。宣伝ほどは改善されていないようだ。学習効果が発揮されていない事も一因かもしれない。
誤変換した所を比較してみると英字部分は多少改善されている。英字誤変換部分の原文は、FileSystemWatcher1_Created で、どちらも完全ではない。英語モードなら問題ないが、日本語と英語の2回変換するのは面倒だ。その点では、読んでココの方が良くできている。v.7.0を買ったときにアンケートに改善要望を出しておいたが、今回のv.8.0では反映されなかった。<誤変換の例>
v.7.0
今回はファイルが作成された時を監視したいので、C旧制を選択します。すると、Fik∋SystemWatcherlC鰍edプロシージャが作成されます。v.8.0
今回はファイルが作成された時を監視したいので、Createdを選択します。すると、Fi・eSystemWatcherlCreatedプロシ・ジャが作成されます。試しにアップデートを試してみたら、何と発売されたばかりなのにアップデートが実行された。(R1a)
追加)pdfファイルからの変換は以外と便利だ。
USB2.0のスピードを見るために、I-O DATAのHDA-iU80 (80GB) を買った。接続したHDDのプロパティを見るとSAMSUNG SV8004H USB Device と表示されている。
708MBのファイルを転送してみた所、20MB/s(160Mbps)程度は出ているようだ。
Window2000のコマンドプロンプトでcopyすると、画面上は、25秒でコピーが終了したので、28.3MB/s(227Mbps)出ているのかと思ったが、その後もHDDのランプは当分点灯しているので、そこまでは出ていない。USB2.0の転送速度(MAX 420Mbps)よりもHDDの書き込み速度がネックとなっているようだ。
速度とは関係ないが、SUMI2000のハードディスクは、これで3台になり、総容量が155GBとなった。
デジカメのデータが増えてきたので、久しぶりにDVD-RAM(LF-D102J)でバックアップした。画像データは、容量が1.22GBで、UDF形式で書き込んだら1時間ほどかかった。WinFM2000で測定したら、書き込み速度は 0.37MB/sだった。この数値は以前測定した時と同じだ。CD-Rの書き込み速度で言えば.2.5倍速と、今では非常に遅い部類に入る。
同じものを×16倍速のCD-Rで焼いたら、10分程で完成した。こちらの方がストレスが少なくて良い。
DOS/V SPECIAL 8月号の付録CD-ROMにWinCDR 7のアップグレードプログラムが入っていたので、バージョンを7.20にアップした。元は7.13だった。
その後、アブリックスのHPを見たら、最新版が7.23になっていたので、さらにバージョンをアップした。
USB2.0のスピードを体験してみたくて、とりあえずボード(I-O DATAのUSB2-PCI2)を購入し、SUMI2000に入れてみた。(ヨドバシカメラで\4,470)
まだ、USB2.0対応の機器がないので、USB1.1対応のCanonのスキャナーを接続して、オンボードのUSBと転送速度を比較してみた。
結果はと言うと、残念ながらI-O DATAのボードの方が遅かった。差はわずかだが、恐らくドライバーの出来の差だろう。マザーボードのUSBドライバーはVIA製である。
USB1.1では能力がフルに発揮出来ないようなので、USB2.0に期待しよう。
でも、このボード、取り付けると上下が写真とは反対になるので、字が全て逆さまになってしまう。PCIなので仕方なしか?
SUMI2000はあまりゲームに適したマシンではないがSPECTRA7400DDRはどの程度のスピードなのか測定してみた。
最初インストールしようとしたらDirectX8が入っていなかったので、拒否されてしまった。Windows UpdateでDirectX8.1を入れたら無事3D Markがインストールできた。最新版のpatchもあてた。
結果は、SUMI2000のトータルスコアが1581だった。この数値がどの程度なのかは不明だが、Proside改造機(G400)の1274よりは速かった。どちらのマシンも測定途中でサポートしていない機能があるらしくその項目はスキップされた。スキップ数はG400の方が多かった。
測定中に表示される値を見てみると、10-30fps(Frame per secound)なので、まだ改善の余地はありそうだ。
![]()
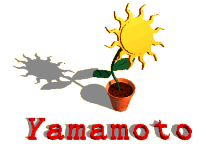
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る