| <<What's New>> パソコン奮闘記 2003年10月~2004年3月 |
![]()
![]() 2004-03-30(火) HPの最大容量を20MBに変更
2004-03-30(火) HPの最大容量を20MBに変更
今日ようやく変更手続きのメニューに入れるようになった。HPの容量は20MBまで無料なので、基本の5MBに15MBを追加して20MBにした。これで当分空き容量を気にしなくて良くなった。
![]() 2004-03-21(日) 59.4Mbps
2004-03-21(日) 59.4Mbps
モデムの電源を入れ直す度にリンク速度がかわる事が分かった。何度か入れ直してスループットを測定したら、これまでの最高の 59.4Mbps が出た( MTU = 1500 RWIN = 151840 )。
![]() 2004-03-20(土) RWIN調整
2004-03-20(土) RWIN調整
MTUは、1448 でも 1454 あるいは 1500 でもスループットにあまり違いがなかったので、MTU = 1500 で RWIN の影響を見てみた。
結果は、RWIN = 140000 辺りでスループットが約 58.5Mbps となり、その後は頭打ちとなった。余裕を見て、RWIN = 150000 程度にしておけば良さそうである。
ADSLの頃と違い、今回は RWIN をいくら大きくしてもスループットが下がることはなかった。
![]()
![]() 2004-03-20(土) 光プラスで今度は57.33Mbps
2004-03-20(土) 光プラスで今度は57.33Mbps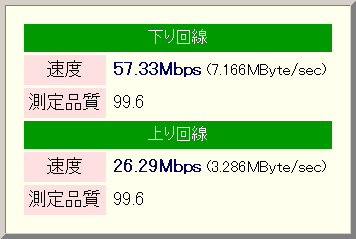
今回のレンタル機器の中で、MJ(モジュラージャック)からVDSLモデムと電話機への分岐用には、いかにも安そうなモジュラー分岐コネクタ(良く電気店で売っているもの)がついてきたので、こんなもので大丈夫かと思いながらもマニュアル通りにそれを使っていた。
今日、試しに、これを手元にあったADSL用のスプリッタ(相菱電子化学のSP-01)と交換してみたら、スループットが更に上がった。恐らくリンク速度がアップしたのだろう。
KDDI光プラスのVDSLは16MHzまでの周波数を使うので、ASDL用のスプリッタ(~数MHz)では高周波域がロスする可能性があるが、電話機用のモジュラー分岐コネクタよりは、分岐ロスが少ないと思われる。
因みに、今回使用したスプリッタSP-01は2003年1月、モア(12Mタイプ)の頃に購入したものである。今でも販売されているので、もう少し高周波数側まで対応できるように仕様が変わっているかも知れない。
タイプ 使用周波数帯域 フレッツADSL 1.5Mタイプ 約 30kHz ~ 552kHz フレッツADSL 8Mタイプ 約 30kHz ~ 1.1 MHz フレッツADSL モア(12Mタイプ) 約 30kHz ~ 1.1 MHz フレッツADSL モアII (24Mタイプ) 約 30kHz ~ 2.2 MHz フレッツADSL モアII (40Mタイプ) 約 30kHz ~ 3.8 MHz KDDI光プラス(70Mタイプ) 約640kHz ~16 MHz これで、下りのスループットは、最大70Mbpsの81.9%となった。上りが最大30Mbpsの87.7%なので、同比率なら下りのスループットは61.3Mbpsまで上がる可能性がある。目指すは60Mbps超えか?
![]() 2004-03-19(金) 光プラスで54Mbpsが出た
2004-03-19(金) 光プラスで54Mbpsが出た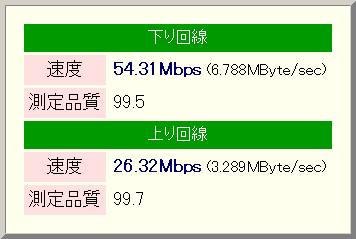
モデムの電源を入れ直してスループットを測定してみたら、これまでの最高の54.31Mbps(70Mbpsの77.5%)が出た。
フレッツADSLモア40Mの時の最高が約27Mbpsだったからほぼ2倍、2.4GHz無線LANのIEEE802.11g(54Mbps)と同じ速度になった。
速度は下りに合わせて上りも上がっている。上りのスループット26.32Mbpsはこのサービスの最大速度30Mbpsの87.7%にも達している。
因みに左の測定結果は、SUMI2000(W2K P3 1GHz)によるもので、MTU = 1500、RWIN = 134328。
SUMI05(W2K P4 2.53GHz)で測定しても殆ど差がなかったので、マシン側にはまだ余裕がありそうだ。
![]() 2004-03-18(木) 光プラスで50Mbpsを超えた
2004-03-18(木) 光プラスで50Mbpsを超えた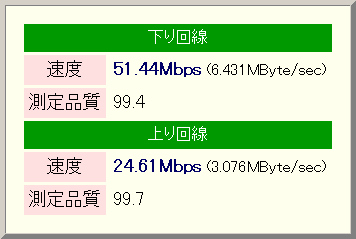
SUMI05で空いている時間帯に http://www.studio-radish.com/tea/netspeed/ で測定してみたら下り速度が50Mbpsを超えた。
因みに、RWIN = 1454、RWIN = 260176
所で、ホームゲートウェイ(Aterm BL150HV)の設定をみたが、プロバイダーを指定する所がない。どうもKDDIの光プラスはDION以外のプロバイダーは利用できないようだ。
それと、モデム(MegaBit Gear VTE5010)の説明書にはリンク速度に関する記述がないので、現在のリンク速度も不明である。
PS.インターネット検索していたら、光プラスのMTUは1454ではなく1500が最適であるとの記事が見つかったので、試してみた。結果は殆ど変化なかった。
現在の設定は、MTU = 1500、RWIN = 134328
![]() 2004-03-16(火) 光プラス(70Mbps)開通
2004-03-16(火) 光プラス(70Mbps)開通
今日、予定通り工事が行われた。モデムなどの機器も夕方届き、光プラスが開通した。
届いた機器は、モデムが住友電工ネットワークのMegaBit Gear VTE5010、ホームゲートウェイはNECのAterm BL150HVだった。
配線が完了したので、試しに、MTUとRWINは以前のADSL40Mのままで測定してみた(SUMI2000)。
下りが31Mbps、上りは約22Mbpsと上りはADSLとは雲泥の差だ。
(MTU = 1448 、RWIN = 50688)
これからもう少し調整してみる。
![]() 2004-03-14(日) 光プラス工事の開通進捗状況(その4)
2004-03-14(日) 光プラス工事の開通進捗状況(その4)
「ご利用開始のご案内」が来たが、あまり目新しい情報はなかった。
開通進捗状況(なぜか矢印が10個になった)
KDDI光プラスサービス申込書受付、手続中
受付 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 回線工事日確定
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 回線工事中
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ご利用可能PS.今日はVDSLモデムとホームゲートウェイは届かなかった。3/16開通だから明日だろうか。
![]() 2004-03-13(土) e.Typist v.9.0でトラブル
2004-03-13(土) e.Typist v.9.0でトラブル
e.Typist v.9.0をインストールしたら、最終段階で自動的に最新版にアップデートした。その後、起動したら何とスキャナーのTWAINが反応しなかった。
スキャナーは、EPSONのGT9300UF。
もしかしたらと思い、Photoshopで試してみたら、ここでも「TWAIN機器が反応しません」と出て使えなくなっていた。「読んde!!ココ」でも症状は同じだった。
e.Typist v.9.0のインストールでTWAINドライバーがおかしくなってしまったようだ。
結局、スキャナー(GT9300UF)のドライバーを再インストールして、無事使えるようになった。
読んde!!ココVer.10を入れた後にe.Typist v.9.0を入れたのが原因(相性問題)?さて、本来の目的であった認識精度はと言うと、予想通り、e.Typist v8.0と e.Typist v.9.0では殆ど差がなかった。つぶれ、かすれ文字でないと差が出ないのか?
![]() 2004-03-13(土) e.Typist v.9.0購入
2004-03-13(土) e.Typist v.9.0購入
「DOS/V magazine (No.247 2/4 号)」で、e.Typist v.9.0が、「Tester’s Choice 賞」と「Observer’s Choice 賞」のダブル受賞した。
これを記念して、e.Typist v.9.0のアップグレード版(7,500円)がキャンペーン価格として4,900円で3/5から販売開始された。キャンペーン版は、5千本限定なので、早速ヨドバシカメラへ行ってみた。ソフトフロアーのOCRコーナーに僅かに2本残っていたので1本を買ってきた。
これまでのv.8.0と、どの程度違うか、読んde!!ココVer.10とはどうか等をこれから試してみる。
ただ、以前v.9.0のお試し版を使ってみた時は、v.8.0とあまり差が無かったように記憶している。
![]() 2004-03-11(木) 読んde!!ココとe.Typistの認識精度
2004-03-11(木) 読んde!!ココとe.Typistの認識精度
読んde!!ココVer.10とe.Typist v.8.0の認識精度を比較してみた。結論から言うと、一長一短で、優劣をつけられなかった。
読んde!!ココVer.10は、細かい罫線で囲まれた部分も変換できるが、その分、本来1つの枠内にある物が複数に区切られてしまい、後で繋ぎあわせる手間のでるものがあった。
e.Typist v.8.0は枠の判定は読んde!!ココVer.10よりも正確だが、細かい枠内は文字として認識しないケースがあった。
通常の文字だけの場合は、変換精度は99%以上で殆ど同じだった。
DOS/V magazine 2004/2/15号では、読んde!!ココ Ver.9とe.Typist v.9.0の比較があり、ここではe.Typist v.9.0優位と書かれていた。確かに、バージョンを考えると、そうなりそうである。
![]() 2004-03-10(水) 光プラス工事の開通進捗状況(その3)
2004-03-10(水) 光プラス工事の開通進捗状況(その3)
やっと工事日が決定した。
回線工事予定日は、2004年03月16日(来週の火曜日)になった。開通進捗状況
KDDI光プラスサービス申込書受付、手続中
受付 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 回線工事日確定
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 回線工事中
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ ご利用可能
![]() 2004-03-08(月) 読んde!!ココVer.10購入
2004-03-08(月) 読んde!!ココVer.10購入
読んde!!ココVer.10のダウンロード版を購入した。オンラインで3,800円。
Ver.9に比べて見た目がすっきりしたのと、ガイドメニューが充実した。
読み取り精度も向上したと書かれているので、これからe.Typist v.8.0と比較してみる。e.Typistも v.9.0が出ているので、一寸比較のバランスが良くないかも知れない。
![]() 2004-03-06(土) 光プラス工事の開通進捗状況(その2)
2004-03-06(土) 光プラス工事の開通進捗状況(その2)
矢印が更に2つ進んだ。後3個進むと回線工事日確定?
受付 ⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 回線工事日確定
![]() 2004-03-03(水) 光プラス工事の開通進捗状況
2004-03-03(水) 光プラス工事の開通進捗状況
進捗の矢印が少し進んだ。2/28は1個だった矢印が4個になった。後5個進むと回線工事日確定に届くように見える。
受付 ⇒⇒⇒⇒ 回線工事日確定
![]() 2004-02-28(土) 3D GALLERYのコンテンツをDIONに移動
2004-02-28(土) 3D GALLERYのコンテンツをDIONに移動
3D展示館のデータを「ぷらら」からサーバーレスポンスの良い「DION」に変更した。これで幾分ストレスが減るか?
![]() 2004-02-28(土) KDDIから光プラスの申し込み確認が届く
2004-02-28(土) KDDIから光プラスの申し込み確認が届く
昨日、KDDIから封書で光プラスの『お手続き開始のご案内』が届いた。これが最初の通知で次に『ご利用開始のご案内』が来るようだ。今回の通知の中に、開通までの進捗状況がウェッブで確認出来ると書かれていたので、早速確認してみた。
契約申込受付日が2004年02月25日で、開通進捗状況は、
KDDI光プラスサービス申込書受付、手続中
受付 ⇒ 回線工事日確定となっていた。これから「回線工事日確定」と言うことか?
今回の通知の中に、メールアドレスとホームページURLが取得できると書かれていたので、早速登録してみた。やっぱりどちらも第一希望は既に登録されており無理だった。
新URLは、http://www.h6.dion.ne.jp/~s.yama 初期容量が5MBで、20MBまでは無料だそうだ。
<追記>
「ぷらら」と「DION」の両HPサーバーに同じコンテンツを置いてみた所、「DION」の方がレスポンスが良いようだ。
![]() 2004-02-14(土) KDDI光プラス(70Mbps)申し込む
2004-02-14(土) KDDI光プラス(70Mbps)申し込む
今日、KDDIのマンション向けVDSL方式光プラス(下り70Mbps/上り30Mbps)に申し込んだ。開通は3月中旬の予定。何Mbps出るか。
![]() 2004-02-10(火) 一太郎2004を購入
2004-02-10(火) 一太郎2004を購入
先週の2月6日(金)に発売となった「一太郎2004」を昨日9日(月)に購入した。
目的はいつもの通り新ATOKで、今回はATOK17となっている。バーションアップ版で7980円。ATOK17単体は2月末の発売で、価格もそれ程変わらないので、一太郎を購入した。これまで買った一太郎のライセンスを調べてみたら、Ver.5からVer.13まで全てのバージョンを購入していた。これも目的はATOKである。
一太郎の前バージョンは「一太郎13」だったのに、急に西暦に変更されたのは、Officeに対抗するためか?ATOKは16から17と従来路線の命名法となっている。
初期バージョンは色々トラブルが発生するものだが、今回は今のところ何も不具合は発生していない。逆に何が変わったのかも良く分からない位のマイナーバージョンアップの様だ。
今回目新しいのは、最初からATOK17だけをインストールするメニューがトップにある事だ。やはり、ATOKだけを利用する人が多く、このニーズが高かったのだろう。
まだまだMS-IMEはATOKに追いつかない。
![]() 2004-01-31(土) Canopus RFX5200Aを購入
2004-01-31(土) Canopus RFX5200Aを購入
自作マシンのSUMI05はM/BにVGAが付いているので、それを使っていたが、動画の動きがスムースではなかったので、グラフィックアクセラレータを購入してみた。買ったのはCanopusのRFX5200A。ヨドバシカメラ川崎店で12,800円。Works Partsなので、箱も殺風景な白箱だった。価格もメーカーの標準価格だ。DVIとTV出力が付いていてこの値段はお買い得だろう。少なくともCanopusなので動作は安定している筈だ。
SUMI05のAGPスロットにこのボードを挿したところ、最初認識しなかった。何故かとマニュアルなどを調べてみたが、事は単純でボードの差し込みが不足していた。AGPスロットにボードを挿すのが最初だったので、かなり固かった様だ。相当の力を入れないと奥まで入らなかった。よく見ると、AGPスロットにはメモリと同様にボードが抜けないようにラッチ機構がついていた。奥までボートが入るとこのラッチでボードが固定された。これは便利な機構だ。
認識後、Windowsのドライバーをインストールして動画を見てみたら、動きが大分スムースになった。それでも、まだ画面が大きく変わるときには、ジャギがでるので、この程度のビデオボードではまだ完全ではないようだ。
2/1追記
新しいグラフィックアクセラレータを入れたSUMI05でLindowsCD版を立ち上げてみた。残念ながら1024*768 85Hzには変更できなかった。
![]() 2004-01-11(日) LindowsOSを試してみる
2004-01-11(日) LindowsOSを試してみる
Linuxで作成されたWindows風のOSであるLindowsのCD版が1/9にエッジから発売されたので、アスキーストアのダウンロード販売で購入してみた。値段は何と1980円で、下手なシェアウェアより安い。
ダウンロードしたイメージデータをCD-Rに焼くことでOS CDが完成するものである。B's Recorder GOLDは推奨ソフトではなかったが、無事焼くことができた(ダウンロードしたLindowsOS.isoファイルを画面左下にある「トラックの種類」の所にドロップ)。
LindowsCDはCDから起動するので、今入っているOSを消す事なく利用できる。
SUMI05とSUMI2000で試してみた。
- SUMI05(P4 2.53GHz, M/B:MSI 845GE Max-L)では、VGAでしか立ち上がらずリフレッシュレートが60Hzのためチカチカして見づらい。画面の解像度やリフレッシュレートを変更するとハングアップしてしまった。
- SUMI2000(P3 1GHz, M/B:ASUS P3V4X)では、1024*768 85Hzに変更できたので、こちらは使えそうだ。
特に設定をしなくしてもインターネットには接続できた。ただ、追加したお気に入りが電源を切ると消えてしまうなど、まだまだ使い方を勉強する必要がある様だ。もしかしたら、HDDがNTFSになっているのが問題なのかも知れない。
Windowsマシンとのネットワーク接続もまだ出来ていないので、右の写真は、FDを使ってLindowsからWindowsへコピーした。
![]() 2004-01-10(土) Office 2000
SP-3にアップ
2004-01-10(土) Office 2000
SP-3にアップ
久々にOffice 2000のWebダウンロードをみたらアップデート対象があったので、アップしてみた。アップしたのはSP-3。
アップ前は、多少サイズの大きなパワーポイントファイルを開くとメモリー不足になっていたのが、解消されたようだ。
それ以外は、今のところ効果は不明。
![]() 2004-01-03(土) USB2.0のトラブル
2004-01-03(土) USB2.0のトラブル
データをUSB2.0接続の外付けHDD(IO-DATA HDA-iU80)にバックアップしようと思いエクスプローラを立ち上げたら、何とそのドライブが表示されていなかった。以前にもUSB2.0接続のDVDドライブ(IO-DATA DVR-iUN4)を接続したときに、同様の現象が起こった事があった。今回、内蔵のDVDドライブを付けた事が誘因となったと思われる。
USB2.0にはIO-DATAの4ポートカード(USB2-PCI2/写真)を使用しており、「HDD」と「スキャナー」と「USBメモリー」を接続している。
色々試したら、USBメモリーを接続したまま電源を入れるとHDDが認識されない事が分かった。USBメモリーを抜いて立ち上げ、HDD認識後にUSBメモリーを繋ぐと両方とも認識された。ドライブレターを変えてみたが現象は変わらなかった。
もしかしてと思い、IO-DATAのWebにあるダウンロードを見たら、USB2-PCI2の新しいドライバーが載っていた。早速ドライバーを更新してみたら、嘘のようにこのトラブルが解消した。このために、また随分と時間を無駄にしてしまった。
![]() 2003-12-30(日) 8倍速書込みのDVDドライブを購入
2003-12-30(日) 8倍速書込みのDVDドライブを購入
SUMI2000のHDDバックアップ用として、内蔵タイプのDVDドライブを購入した。
今回買ったのは、IO-DATAのDVR-ABN8で、DVD-RもDVD+Rも8倍速で記録できるドライブ。ただ、まだ正式には8倍速に対応したメディアは販売されていない。ドライブそのものは、NECのOEMなのでバルク品を探してみたが見つからなかったので、パッケージ品を買うことにした。ヨドバシカメラで 20,800円。最近DVD-RAMにも対応したドライブが発売されたので、このDVR-ABN8が少し安くなった。
SUMI2000に付いていたPLEXTORのCD-Rドライブ(PX-W1210TA)を外して、この新ドライブを取り付けた。トレイの動作はスムースだが、モータ音が少し大きい様だ。
これまてCD-Rドライブ用に使っていたWinCDR7.0を立ち上げたら「対象外のドライブで正常に書き込みができない」とメッセージがでたので、WinCDRはアンインストールして、付属してきたB's Recorder GOLD7Basic Winをインストールした。
このB's Recorderで、Cドライブの4.2GBをバックアップしようとしたら、4.7GBのDVDメディア2枚を要求してきた。HDDの中を整理して約4.0GBにしてみたが、まだ2枚を要求してくる。何故だろう。
<追記>
更にHDD内を整理して3.93GBにしたら、要求メディアが1枚になったので、バックアップ時の圧縮レベルを最高にしてDVDを作成してみた。HDDのイメージ作成に約30分、DVD-RW(2.4倍速)への焼き込みに約30分の計1時間を要した。出来上がったDVDからブートしてみたら、無事OSが立ち上がり、リストアのメニューが出たので作成は成功したようだ。
出来たDVDの容量を見たら使用領域は、2.23GBで元の3.93GBが57%に圧縮されていた。でも、2.23GBは、メディア(4.7GB)の47%しかしか使っていないので、4GBを超えると2枚要求する理由は依然不明だ。念のためDVDからBOOTして、HDDにデータをRestoreしてみた所、正常終了した。所要時間は約40分。BOOTシーケンスをDVDからHDDに変え、再立ち上げした後の最初のWindows起動時にはDisk Checkが行われ、その後の再起動で無事Windowsが立ち上がった。
![]() 2003-12-27(土) 160GBのHDDを購入
2003-12-27(土) 160GBのHDDを購入
SUMI2000のHDD空き容量が少し減ってきたので、160GBのHDDを購入した。
買ったのは、SeagateのBarracuda 7200.7 ST3160023A (160GB)。ツクモで11,979円。SUMI2000に入っていたIBMのDTLA-307030 (30GB)と交換した。
最初はOSで128GBまでしか認識しなかったのに気づかず、そのままフォーマットしてしまった。フォーマット後の使用可能領域は127GB。その後、レジストリーの変更で138GB以上にも対応する事が分かったので、レジストリーを(HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Services \atapi \Parameters, EnableBigLba=1に)書き換えたら残りの21GBも認識するようになった。フォーマット後のこの部分の使用可能容量は何故か変わらず21GB。全体を再フォーマットするのも大変なので、このまま2つのパーティションで使うことにした。これで新HDDのトータル使用可能容量は149GB。
元々あった内蔵の60GB(Seagate)と外付けの80GB(I-O DATA)を併せて、SUMI2000のHDD容量合計は、160+60+80=300GBとなった。フォーマット後の実利用可能容量は280GB。
![]() 2003-12-23(火) モアII(40M)用モデムのリンク速度
2003-12-23(火) モアII(40M)用モデムのリンク速度
拡張自動設定で各モードのリンク速度を確認してみた。
特筆すべきは、モアII(40M)のQuad SpectrumとモアII(24M)相当のG.dmt Annex Iで下りのリンク速度が大きく違うことである。NTTが公開している図(伝送損失とリンク速度の関係)では、これ程の差が出るとは想像が出来ない。図がおかしいのか、現在利用している回線に特殊な条件があるかの何れかであろう。
また、今使用しているMN4モデムのモアII(24M)相当のリンク速度18.688Mbpsは、以前使っていたMN3モデムの時の約15Mbpsよりも速い。モデム自体の性能も向上しているのだろうか。
【ラインモード別ADSL回線速度(拡張自動設定)】
モード 下り[リンク速度(kbps)] 上り[リンク速度(kbps)] Quad Spectrum 31808 1248 G.dmt Annex I 18688 1248 G.dmt Annex C 10176 1216 G.dmt Annex C(FBMsOL) 4032 384 G.lite - -
![]() 2003-12-22(月) モアII(40M)のリンク速度
2003-12-22(月) モアII(40M)のリンク速度
今日は調子が良い。僅かだが下りのリンク速度がアップしてこれまでの最高の 31968kbps となった。もう少しで32Mbpsに届く。上りもフルリンクしている。
Line mode : G.dmt Annex Q
ADSL status : ShowTimeL0
Payload ADSL Line rate(Down): 31968(kbps)
Payload ADSL Line rate(Up) : 1248(kbps)
Interleave Delay(Down) : 2(mS)
Interleave Delay(Up) : 1(mS)
Interleave Depth(Down) : 64
Interleave Depth(Up) : 1
Current SNR Margin : 6(dB)
Current Output Power(Down) : 8(dBm)
Current Output Power(Up) : 12(dBm)
Current Attenuation : 8(dB)
![]() 2003-12-21(日) モアII(40M)の実効速度
2003-12-21(日) モアII(40M)の実効速度
RWINを変えて実効速度を測定してみた(SUMI05, BR1500H)。
測定サイトは、Radish Network Speed Testing。RWIN=50688(N=36)までは、ほぼ直線的に速度が増加し、その後は僅かながら増加傾向にある。RWIN=64768をピークにその後は速度が低下する様である。速度のバラツキ・安定性を考えると、モアII(40M)の最適RWINは、59136 と推定される。この値はモアII(24M)の時の最適RWIN(42420)に比べると約40%上がっている。
なお、測定時のリンク速度(下り)は、31872kbpsなので、RWIN=59136の速度(27.15Mbps)はリンク速度の85%となっている。
N RWIN 実効速度(Mbps) 10 14080 7.42 20 28160 14.17 30 42240 21.16 32 45056 22.65 34 47872 24.69 36 50688 25.64 38 53504 25.58 40 56320 26.22 42 59136 27.15 44 61952 26.87 46 64768 27.22 48 67584 23.76 50 70400 21.41
参考) RWIN = N * ( MTU - 40 ) = N * 1408
![]() 2003-12-20(土) フレッツADSLモアII(40M)その後
2003-12-20(土) フレッツADSLモアII(40M)その後
40M用のモデム(MN4)は開通日の12/17に写真を撮ってはいたが、
掲載する暇がなかったので、遅ればせながら今日アップした。24M用のMN3より少し大きい。
旧モデム(MN3)は今日引き取り予定だったので、玄関先に置いて外出した。夕方帰宅した時にはまだ引き取りに来ていなかった。22時頃見たらまだあったので、諦めて家の中へ回収した。結局今日は引き取りに来なかったようだ。
今日の下りのリンク速度は 31776kbpsで、開通以来ほぼ31.8Mbps程度で安定している。
Line mode : G.dmt Annex Q
ADSL status : ShowTimeL0
Payload ADSL Line rate(Down): 31776(kbps)
Payload ADSL Line rate(Up) : 1248(kbps)
Interleave Delay(Down) : 2(mS)
Interleave Delay(Up) : 1(mS)
Interleave Depth(Down) : 64
Interleave Depth(Up) : 1
Current SNR Margin : 6(dB)
Current Output Power(Down) : 8(dBm)
Current Output Power(Up) : 12(dBm)
Current Attenuation : 8(dB)
![]() 2003-12-18(水) フレッツADSLモアII(40M)の状況
2003-12-18(水) フレッツADSLモアII(40M)の状況
今日のリンク速度は昨日よりも僅かだが好転している。上りも1248kbpsでフルリンクした。24Mの時は日毎に悪化していたので、このときに比べると安定している。
Line mode : G.dmt Annex Q
ADSL status : ShowTimeL0
Payload ADSL Line rate(Down): 31872(kbps)
Payload ADSL Line rate(Up) : 1248(kbps)
Interleave Delay(Down) : 2(mS)
Interleave Delay(Up) : 1(mS)
Interleave Depth(Down) : 64
Interleave Depth(Up) : 1
Current SNR Margin : 6(dB)
Current Output Power(Down) : 8(dBm)
Current Output Power(Up) : 12(dBm)
Current Attenuation : 8(dB)ビットマップを見ると、高周波数側でもそれ程レートが低下していないので、回線状態は良さそうである。Output Power(Down)が8dBmと低いので、ノイズフィルターを入れてみたりしたが、変化はなかった。
DR utility 1.0.0 によるBitMap表示結果 実行速度が出ない原因は、BUFFALOのルータWBR-G54/Pだった。これを外してBR1500Hだけにしたら25.6Mbpsが出た(マシンはSUMI2000)。WBR-G54/Pの最大スループットは40Mbpsと書かれているが、実際は16-18Mbpsで頭打ちになるようだ。
とりあえず、これでリンク速度(31.872Mbps)の80%が出たのでOKとしよう。
![]() 2003-12-17(水) フレッツADSLモアII(40M)開通
2003-12-17(水) フレッツADSLモアII(40M)開通
ADSLモデムMN4が届いたので、交換して見たら、何と下りのリンク速度が、31.68Mbpsになった。モアII(24M)の時の15Mbpsの2倍以上だ。やはりモデムMN3は故障していたのか?
【ADSL回線の状態】
ラインモード Quad Spectrum 上り回線速度[リンク速度(kbps)] 1216 下り回線速度[リンク速度(kbps)] 31680 ただし、何故か実行速度は15~16Mbps程度。接続をIIJからplalaにしてもあまり変化なし。ISPをinfoPepperにして測定しても15~16Mbps程度。どうも何処かにボトルネックがありそう。もしかしたらRWINが小さすぎるのか?現在のMTUは1448で、RWINは42240。
![]() 2003-12-03(水) フレッツADSLモアII(40M)の日程決まる
2003-12-03(水) フレッツADSLモアII(40M)の日程決まる
NTT東日本からスケジュール等のお知らせメールが来た。
モデム到着が12/16(火)で、開通が12/17(水)。初日に開通する様だ。
モデムはMN4で、IP電話非対応。
モアⅡ(24M)からモアⅡ(40M)へ変更なので工事費は無料らしい。
![]() 2003-11-27(木) ADSLモデム回復
2003-11-27(木) ADSLモデム回復
ファームウェアバージョンを2.01から2.00に戻したら、自動でリンクするようになった。それも下りのリンク速度が 16,192kbps と最初の頃と同じになった。その後バージョンを2.01にしてみたら、問題なく繋がるようになった。原因不明。
![]() 2003-11-24(月) ADSLリンク不良
2003-11-24(月) ADSLリンク不良
昨日からADSLモデムが自動ではリンクしなくなった。中距離にすると何とか繋がるので、恐らくモデムの故障だろう。今モデムを交換しても良いが、12月17日開通予定のフレッツモア40Mに申し込んであるので、とりあえずこのまま使うことにしよう。
現在の中距離モードでのリンク速度は約9Mbps。これも当初の11Mbps台に比べると低いので、正常ではなさそうだ。
![]() 2003-11-09(日) 東プレのキーボードRealforce
106
2003-11-09(日) 東プレのキーボードRealforce
106
速く打てて疲れにくいと言う東プレのキーボード Realforce 106 を買ってみた。 BLESS秋葉原本店で15,980円。
106キーなので、Windowsスタートキーはない。
静電容量無接点方式と円錐バネでチャタリングが無く、動作力も接点式の55gに比べて30~45gと軽い。スイッチング位置が荷重の減少域にあるため軽いタッチ感があるそうだ。確かにキーは軽く打てる。使い勝手はこれから評価するが、キーボード本体は結構重い。カタログでは1.4kg。
![]() 2003-11-08(土) ウイルスバスーを2004にアップ
2003-11-08(土) ウイルスバスーを2004にアップ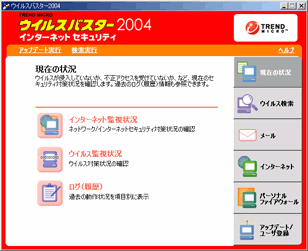
TREND MICROからウイルスバスターの無料アップグレードの通知メールがきたので、早速バージョンをにアップしてみた(VB2003からVB2004へ)。
第一印象:操作画面がシンプルになっている。
このVB2004からはアップデート機能を利用するためにはユーザーとパスワードの登録などと言う面倒な手続きが増えている。
また、アップグレードを開始するとデフォルトでは以前のVB2003が削除される。IDをどこかに記録しておかないと、VB2004がインストールできない仕組みになっており、ライセンス管理がしっかりしていないと面倒な事になりそうだ。
パーソナルファイアーウォールは、接続によって、「(1)ホームネットワーク1(ルータなし)」、「(2)ホームネットワーク2(ADSL/ルータ)」、「(3)オフィスネットワーク」、「(4)公共の無線LANネットワーク」から選べるようになっている。デフォルトは(1)のルータなしになっているので、(2)のルータ使用に変更する必要があった。
<11/9追記>
家にあるパソコン3台ともVB2004にしてみたら、他のパソコンの共有ホルダーが見えなかった。どうもパーソナルファイアーウォールの設定は(3)のオフィスネットワークにする必要がある様だ。
![]() 2003-10-25(土) Adobe Photoshop
Elements 2.0購入
2003-10-25(土) Adobe Photoshop
Elements 2.0購入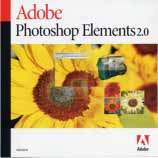
そろそろPhotoshopも古くなってきたので、Elementsだが最新バージョンを購入した。ヨドバシカメラで9,980円。
一見した所ではヘルプが充実している様だ。ただ、デフォルトにナビゲーションが無いのは、一寸使いづらそう。
ビデオファイルからのフレームをキャプチャやブラシ効果を使用したペイントなど、新機能が幾つかある筈なのでこれから試してみる。
![]() 2003-10-20(月) AtermBR1500Hのソフトウェアバージョンアップ
2003-10-20(月) AtermBR1500Hのソフトウェアバージョンアップ
ブロードバンドルータAtermBR1500Hのソフトウェアを見たら、9/19付けで新バージョン(7.97)が出ていたので、バージョンアップしてみた。
今回のバージョンは、PPPoEを複数同時接続できる「PPPoEマルチセッション」に対応している(最大3セッションまで同時接続可能)。複数のISPや、特定のプロバイダとフレッツ・スクウェアへの同時接続が可能と書かれていた。
バージョンアップ後、次のように設定したら通常の接続で、フレッツのスピード測定もできた。
- No.1の優先接続(UPnP優先)をplala(IIJ経由)
- 静的ルーティングのNo.4をフレッツ・スクウェア(www.flets)
- 静的ルーティングのNo.5をフレッツ・スクウェア(speed.flets)
![]() 2003-10-19(日) Adobeのpdf形式Readerを6.0に
2003-10-19(日) Adobeのpdf形式Readerを6.0に
Adobeのpdf形式Readerは、Acrobat Reader 5.0でも別段支障はないが、機能が追加されている様なのでSUMI2000のバージョンを6.0にアップしてみた。
右はそのタイトル画面だが、複数の線が四角からはみ出している所が面白い。特許の数が増えて過ぎて上下のバランスが悪くなったのか?
最初は左上が人だとは気が付かなかった。一度それが分かるとその後はそう見えるのも不思議だ。
名前は、Acrobat Writerとの混乱を避けるために変えたのだろう。使い勝手は5.0とあまり変わらないようだ。
Acrobat Reader 5.0 → Adobe Reader 6.0
![]()
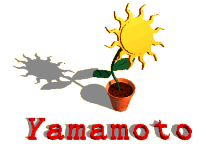
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る