
折鶴蘭、学名:Chlorophytum comosum
斑がはいる細長い葉の間からランナー(走出枝)がのび、その先につく子株は、折り鶴のよう。 子株を地面に降ろせば、容易に根づき、ふえる。花は白色で、春にそのいくつかの節に咲く。
ランと名がつくがユリ科で、南アフリカ原産。
撮影地:兵庫県フラワーセンター、 年月日:'01/ 5/ 1
|
 |
オリヅルラン(ユリ科) 折鶴蘭、学名:Chlorophytum comosum 斑がはいる細長い葉の間からランナー(走出枝)がのび、その先につく子株は、折り鶴のよう。 子株を地面に降ろせば、容易に根づき、ふえる。花は白色で、春にそのいくつかの節に咲く。 ランと名がつくがユリ科で、南アフリカ原産。 撮影地:兵庫県フラワーセンター、 年月日:'01/ 5/ 1 |
 |
キジムシロ(バラ科) 雉筵・雉蓆、学名:Potentilla fragarioides var.major 葉を四方に広げ、そのまわりを黄色の花がふちどる。この姿をキジの座る敷物に見立てた。 根もとの葉は奇数羽状複葉で、2〜3対の小葉がある。先端の小葉がもっとも大きく、つけ根に近いものほど小さい。 撮影地:八方尾根、 年月日:'03/ 8/ 4 |
 |
クジャクアスター(キク科) 孔雀アスター、Aster アスターは、ギリシャ語で「星」の意で花の形に由来している。 野菊のような小さな花がたくさん咲く様子は、孔雀が羽を広げたような花姿。優しいイメージがあり、花束の添え花としても人気。 白花はシロクジャク、紅花はベニクジャクと呼ばれる。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'04/ 9/18 |
 |
クジャクサボテン(サボテン科) 孔雀サボテン、Epiphyllum 月下美人と同属、といっても花の雰囲気は別。片や夜咲きの白花で強く香るが、昼咲きで有色、香りはほとんどない。 萼から花弁に連続する鮮やかな花被を羽を広げたクジャクに見立て、美しく命名。 花は非常に豪華で、巨大輪の品種では花径は30cm近くにもなる。 撮影地:大阪府立花の文化園、 年月日:'03/ 5/17 |
 |
クジャクソウ(キク科) 孔雀草、フレンチマリーゴールド、学名:Tagetes patula ハルシャギクも孔雀草と呼ばれ、美しい鳥にあやかる名だけに、2つの植物の名となってしまった。 花は直径3〜4cmで、外側に舌状花、中心に筒状花がある。黄色や橙色、赤褐色などがあり、霜が降りる晩秋まで咲き続け、花期が長いので「万寿菊」とも。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'02/10/11 |
 |
トキソウ(ラン科) 鴇草・朱鷺草、学名:Pogonia japonica 同じ運命をたどらせてはなるまい。絶滅寸前のトキの名をもらった野生蘭。 色がトキの羽の色そっくりで、美しく愛らしい花。サギソウとともに、鳥の名前のついた花の代表といえるだろう。 湿地にはえる多年草、葉は長楕円形で茎の中央に1枚だけつく。 撮影地:六甲高山植物園(鉢)、 年月日:'05/ 5/ 2 |
 |
ツバメズイセン(ヒガンバナ科) 燕水仙、学名:Sprekelia formosissima スプレケリア・フォルモシッシマ。3〜5cmの有皮鱗茎で、春から秋まで生育し、冬は休眠する。花期は4〜7月。 花は径約13cm、光沢のあるビロード状暗緋紅色で、花形がツバメの飛ぶ姿に似る。アマリリスの花弁を細くしたような形からつばめ咲きアマリリスの名も。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'02/ 6/ 2 |
 |
ガチョウソウ(キンポウゲ科) 二輪草、学名:Anemone flaccida 山野の林下にはえる多年草。1本の花茎から不思議に2輪ずつ(1、3輪のことも)語らうように仲良く花を咲かせるので「二輪草」。 葉が足の形に似ていることから別名「鵞鳥草(がちょうそう)」とも言われている。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'01/ 4/15 |
 |
ケイトウ(ヒユ科) 鶏頭、学名:Celosia cristata にわとりのトサカにそっくりなので「鶏頭」。花言葉の「色あせぬ恋」は、燃えるような紅色の花が長く咲くからだろう。 扁平な帯状に変化したトサカケイトウ(写真)のほか、スギの樹冠に似たヤリゲイトウ、細かい花穂が密集したフサゲイトウなどがある。 撮影地:豊中・服部緑地、 年月日:'01/10/ 1 |
 |
キンギョソウ(ゴマノハグサ科) 金魚草、学名:Antirrhinum majus 名がゆかい。左右相称花で花筒はふっくら。下部の唇弁は3つに裂け、ランチュウの尾を思わせる。英名はスナップドラゴン。ほかにライオンの口という英名、ドイツ名も。 春に穂状に咲く、花色豊富な派手やかな花は、「でしゃばり」という花言葉をもらうほど。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'05/ 5/14 |
 |
キンギョノキ(イワタバコ科) ネマタンサス、学名:Nematanthus gregarius 茎が長く伸びて蔓状に下垂し、葉は無毛、光沢ある暗緑色で長さ4cmの楕円形。 花は壷形で橙色。筒部は喉部が細くくびれ、中央は太く、先端部は細くつぼむ。その形態と色から、「金魚の木」ともよばれる。 撮影地:京都フラワーセンター(現在名:花空間けいはんな) 年月日:'03/ 2/15 |
 |
サンゴバナ(キツネノマゴ科) 珊瑚花、学名:Justicia carnea 珊瑚に似た薄桃色の花。その色から、フラミンゴプランツとも。 原種は樹海の中で、サンゴのように赤く花咲く。日本では鉢植えの草花として扱われるが、常緑低木で原産地のブラジルでは背丈ほどに伸びる。筒状花の長さは5〜9cmで、上向きにかたまって咲く。 撮影地:大阪花博記念公園・咲くやこの花館、 年月日:'98/ 8/15 |
 |
スパイダーオーキッド(ラン科) Spider orchid、ブラッシア、Brassia 幾何学模様を思わせる花が整然と並び、コーラスダンスをしているようなユニークさをもつ。 中南米原産のランで、花弁が細長く伸び、その姿からスパイダーオーキッドという愛称で呼ばれている。 撮影地:浜名湖花博会場、 年月日:'04/ 4/30 |
 |
スパイダーフラワー(ヤマモガシ科) Spider flower、学名:Grevillea spp. グレビレア‘ロビン ゴードン’。歯ブラシやクモのようなユニークな形の花を咲かせるが、花には花弁がなく長い花柱が飛び出す。 英名:spider flower。花期は4〜10月。 常緑低木。繊細な葉と個性的な花を通年楽しめる品種。 撮影地:大阪花博記念公園・咲くやこの花館、 年月日:'03/ 4/13 |
 |
スズムシソウ(ラン科) 鈴虫草、学名:Liparis makinoana 鈴虫に良く似たとても珍しい蘭。 落葉樹林の林床や岩上に自生し、草丈は15〜30cm位。 バルブの基部から2葉を出し、初夏に暗紫褐色の花が10個ほど咲く。唇弁は幅が広く、スズムシが翅を広げたように見える。 撮影地:神戸・相楽園(山野草展)、 年月日:'06/ 5/ 3 |
 |
スズムシバナ(キツネノマゴ科) 鈴虫花、学名:Strobilanthes oliganthus 山地の木陰に生える多年草。茎には鈍い4稜がある。枝の頂上に紫色の花を1つまたは2つつける。 花は一日花で、鈴虫が鳴く頃から咲き出すのでこの名があるといわれている。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'06/ 9/30 |
 |
マツムシソウ(マツムシソウ科) 松虫草、学名:Scabiosa japonica 高原のハイカーに秋の訪れを知らせてくれる、清々しい紫色の花。 頭花の、外側の花は5つに切れ込み、外側の萼片が特に大きく、舌状花のように見える。 名の由来は、マツムシの好みそうな草地に生えるから、マツムシが鳴く頃に咲くからなど諸説。 撮影地:六甲高山植物園、 年月日:'01/10/ 2 |
 |
ホタルカズラ(ムラサキ科) 蛍葛(蛍蔓)、学名:Buglossoides zollingeri よく目立つ青紫色の花をホタルの光にたとえたものという。葛は花のあとに走出枝(ランナー)をだすことによる。 丘陵から山地にかけての日当たりのよいところに生える多年草。 初夏に、茎頂が二またに分かれ、直径約1.5cmほどの小花が咲く。 撮影地:六甲高山植物園、 年月日:'01/ 5/12 |
 |
ホタルブクロ(キキョウ科) 蛍袋、学名:Campanula punctata 山野に生える、高さ40〜80cmの多年草。初夏に、白・淡紫・紅紫色で内側に紫の斑点のある鐘形の花を下垂。 名の由来は、子供が虫篭がわりに花の中に蛍を入れた、提灯のことを火垂(ホタル)ということからなど諸説。 撮影地:西宮市北山緑化植物園、 年月日:'05/ 6/ 6 |
 |
モスキートフラワー(アカバナ科) ロペジア・Mosquito flower、学名:Lopezia cordata 小さな羽根を広げたような花を蚊に見立てたのが、英名のモスキートフラワーの由来。 紅色の茎がたくさん立ち上がり、先端付近から伸びた花梗の先に小さな花がつく。 撮影地:神戸市立布引ハーブ園、 年月日:'02/ 4/29 |
 |
ハクチョウソウ(アカバナ科) 白蝶草、ガウラ、学名:Gaura lindheimeri 名は花を見れば、すぐ納得できる。白い蝶が羽を広げたような清楚な花。雄しべは細く長く足のよう。花は咲き終わる頃には桃色に変わる。花が群がり風に揺れると、白蝶の舞う風情。 繊細さに似合わず丈夫で育てやすい宿根草。別名:やまももそう。 撮影地:宇治市植物公園、 年月日:'01/ 6/16 |
 |
ヘビノボラズ(メギ科) 蛇不登、学名:Berberis sieboldii 枝には大きな鋭い刺があり、「ヘビでも登れない」ということから蛇登らずの名がある。また、葉の鋸歯も刺状である。 晩春に、直径6mmほどの黄色の小さな花が数個ずつ下向きに咲く。果実は秋に赤く熟す。 撮影地:滋賀県希望が丘文化公園、 年月日:'10/ 5/14 |
 |
マムシグサ(サトイモ科) 蝮草・蝮蛇草、学名:Arisaema japonicum 薄暗い樹林地に不気味な紫色の姿で立つ、個性豊かな草。まだら模様のある太い茎が、マムシを思わせることからの名。 4〜5月頃、淡緑紫色で白い縦筋のある仏炎苞と呼ばれる筒状の苞に包まれた花をつける。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'03/ 4/27 |
 |
カメバヒキオコシ(シソ科) 亀葉引起こし、学名:Plectranthus kameba(Isodon Kameba) 語源がおもしろい。カメバは亀葉。葉は先が急に細く尖り、尾を出したカメのよう。 ヒキオコシはその名の同属別種が、腹痛で倒れた旅人を「引き起こした」とされる弘法大師の伝説に因むという。 青紫色の唇形花が多数集まって花穂をつくる。 撮影地:京都府立植物園 年月日:'06/9/30(花)、'05/7/8(葉) |
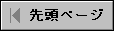 − Photo : Yasuda Hiroshi −
− Photo : Yasuda Hiroshi −