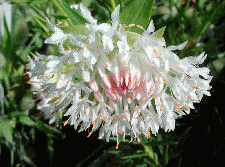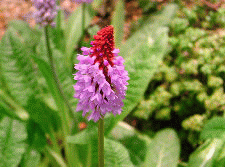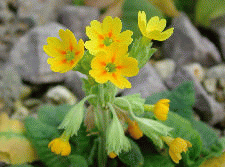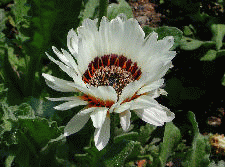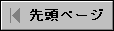− は −

H.coccineus。アカバナマユハケオモト(赤花眉刷毛万年
青)。花は密に散形につき、花序の径は5〜10cm。花
はピンクないし赤色、葯は黄色い。(花空間けいはんな)
パキスタキス Pachystachys (キツネノマゴ科) →
緑色の苞の間から赤い花を咲かせる coccinea
(紅珊瑚花)、穂状に並ぶ鮮黄色の苞の間から白い
花を突き出すlutea がある。 (大阪府立花の文化園)


寒さに強く、背が低く育つので吊り鉢や大きな鉢植え
の根元に植えると美しい。かわいらしい5弁の白い
花をたくさん咲かせる。 (服部都市緑化植物園)
ハシカンボク 波志干木、ブレディア (ノボタン科) →
常緑小低木。葉は対生し、有柄で卵形。7〜9月頃、
枝先に径約1.3cmの淡紅色の4弁・5弁花を頂生の
集散花序に多数つける。花弁は菱形。 (鉢植え)


愛らしい名。花もそれにふさわしい。花は乾いても
しおれない。そのまま頭にかんざしのように飾っても
大丈夫。開花は3〜4月。 (淡路ファームパーク)
パナマソウ 巴拏馬草 (パナマソウ科) →
Carludovica palmata。鑑賞用に栽培。エクアドルで
は若葉でパナマ帽を編む。花は肉穂花序、実は熟す
と朱赤色の果肉が現れる。 (名古屋市東山植物園)