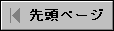− さ −

花が桜に似て、葉がランの仲間に似ることからの名
だが、桜でも蘭でもない。中心が淡紅色の星形の白
い小花がボール状に集まって咲く。 (咲くやこの花館)
サフランモドキ (ヒガンバナ科) →
タマスダレと同じゼフィランサス属。花は金色の葯と
白色の雌しべを持ち、濃い桃色。晩春から夏に咲き、
花弁は重なる。 (淡路島公園)


ウツギはふつう白花。それが本種は花弁の外側が
赤紫色を帯び、内側が白い。加えて八重咲きで、2色
が微妙な色合いを織りなす。 (大阪市立長居植物園)
サンゴシトウ 珊瑚刺桐 ・ヒシバデイコ (マメ科) →
変わった名は、花、枝、葉の特徴に基づく。 赤く密生
する花を珊瑚に、枝の刺と、3小葉だが広い葉を桐
のようだとして名づけられた。 (京都府立植物園)