
兎菊、学名:Arnica unalaschcensis var.tschonoskyi
厚みのあるへら形の葉をウサギの耳にたとえた名。
北海道や本州の中部地方以北の高山の草地に生える多年草。
花は明るい黄色。高さは20cmくらいなのに花は径4〜6cmもあり、まるで小さなヒマワリ。別名キングルマ。
撮影地:湯沢高原アルプの里、 年月日:'02/ 6/ 9
|
 |
ウサギギク(キク科) 兎菊、学名:Arnica unalaschcensis var.tschonoskyi 厚みのあるへら形の葉をウサギの耳にたとえた名。 北海道や本州の中部地方以北の高山の草地に生える多年草。 花は明るい黄色。高さは20cmくらいなのに花は径4〜6cmもあり、まるで小さなヒマワリ。別名キングルマ。 撮影地:湯沢高原アルプの里、 年月日:'02/ 6/ 9 |
 |
ウサギゴケ(タヌキモ科) 兎苔、学名:Utricularia sandersonii 南アフリカ原産の食虫植物。ミミカキグサ(耳掻草)の一種。 春〜夏の間につける白い(うすい藤色)花がウサギに似て大変人気がある。 撮影地:六甲高山植物園(食虫植物展)(園内は自宅鉢植え)、 年月日:'04/ 8/10 |
 |
ウシノシタ(イワタバコ科) 牛の舌、学名:Streptocarpus wendlandii ストレプトカーパスは、葉は根生し長楕円形でしわがある。5月頃、細い花茎に筒状の青・紫・桃・白色の花を横向きに咲かせる。 南アフリカ原産で、英名はCape primrose。 50cmもある大きな葉を1枚だけつけるウェンドランディーは、その葉の形から「牛の舌」と呼ばれている。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'03/ 4/27 |
 |
ウシノヒタイ(タデ科) 牛の額、学名:Polygonum thunbergii 葉の形がソバに似ていて、溝のそばに生えるところから、和名は「みぞそば」(溝蕎麦)。 「牛の額」は、葉の形を牛の顔に見立てての別名。 白色〜淡紅色の花が10数個集まってつき、コンペイトウグサの名も。 撮影地:箱根湿性花園、 年月日:'05/10/ 3 |
 |
ウマノアシガタ(キンポウゲ科) 馬の脚形、学名:Ranunculus japonicus 一面に咲いた黄金色の花がわずかな風に波打つ様は、まさに春そのもの。山野でふつうに見られ、茎は細く直立する。 4〜5月、つやのある黄色い5弁花を咲かせる。名は根出葉が馬蹄に似る?からとのこと。 一般にキンポウゲ(金鳳花)の名で親しまれているが、本来のキンポウゲは八重のものをさすという。 撮影地:六甲山最高峰、 年月日:'04/ 6/17 |
 |
キツネアザミ(キク科) 狐薊、学名:Hemistepta lyrata 枝先に紅紫色の頭花を上向きにつける。頭花は直径2.5cmほどで、筒状花だけでできている。外側の総苞片にはトサカ状の突起が目立つ。 「アザミにそっくりの花をつけるがよく見ると違い、キツネにだまされた」ようなのでこの名があるという。 撮影地:万博自然文化園、 年月日:'04/ 5/24 |
 |
キツネノカミソリ(ヒガンバナ科) 狐の剃刀、学名:Lycoris sanguinea 花が鮮やかなのに、命名は葉をよりどころにした。春先にのびだす白みがかった葉でキツネが顔を剃る、と面白がった。 しかし、花が咲く頃には葉は枯れてない。黄赤色の花が長い花茎の先に数個咲く。花は長さ5〜6cm。雄しべは花より短い。 撮影地:万博自然文化園、 年月日:'04/ 8/ 8 |
 |
フォックスフェース(ナス科) fox face、学名:Solanum mammosum 果実は実にゆかい。耳のような突起が2個ほどあって、形は動物を思わせる。 熟すと色は真っ黄に。キツネの顔を連想させるというので、通称はフォックスフェース。形が個性的なので、よく生け花に用いられる。 ナスと同じような花が咲き、和名はツノナス(角茄子)。 撮影地:豊中・服部緑地都市緑化植物園、 年月日:'06/11/ 4 |
 |
サルスベリ(ミソハギ科) 百日紅・猿滑、学名:Lagerstroemia indica ユーモラスな名前は、木肌がツルツルして猿でも滑るという意味。夏から秋に長く咲き、漢名は百日紅。 花弁は6枚で縮緬状に縮れ、枝先に桃色のフリルをいっぱいつけたようである。 冬はスベスベした幹だけとなり、夏の華やかさとは対照的に枯れた趣となる。 撮影地:草津市立水生植物公園みずの森、 年月日:'08/ 7/13 |
 |
タイガーオーキッド(ラン科) Tiger orchid、学名:Grammatophyllum speciosum 「世界で一番大きなラン」といわれており、大きなものでは高さが3m以上になる。 花は黄緑色地に褐色の縞模様があり、名前のとおりトラを思わせる。 株が大きくならないとなかなか開花しないので、日本では珍しい花のひとつである。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'02/10/11 |
 |
クフェア‘タイニーマイス’(ミソハギ科) 学名:Cuphea purpurea ’Tiny Mice’ 一般にクフェアの名で知られるヒッソピフォリア(メキシコハナヤナギ)は這うように伸びてから立ち上がる茎に、ピンクの小さな花を咲かせる。 ほかに赤い葉巻タバコのようなイグネア(タバコソウ、ベニチョウジ)や、ネズミの顔のような花の‘タイニーマイス’などがある。 撮影地:大阪府立花の文化園、 年月日:'02/11/12 |
 |
ネコジャラシ(イネ科) 猫じゃらし、学名:Setaria viridis 花穂で猫をじゃらすと猫が喜ぶので、「ネコジャラシ」。身近で楽しい命名である。和名は、エノコログサ(狗尾草)。犬ころ草の意味。穂の柔らかい毛が子犬の尾を思わせる。 道端や畑などにはえる一年草。高さ40〜70cm。葉は線形。 撮影地:大阪府立花の文化園、 年月日:'01/ 8/15 |
 |
ネコノシタ(キク科) 猫の舌、学名:Wedelia prostrata この奇妙な名の由来は、葉に触れてみれば、瞬時に解ける。葉は厚ぼったく、かたくて短い毛があり、さわるとザラザラして、「猫の舌」の感触。 和名は、ハマグルマ(浜車)。 海岸の砂地に自生、晩夏に黄色の頭花をつける。 撮影地:兵庫県フラワーセンター、 年月日:'02/ 3/14 |
 |
ネコノヒゲ(シソ科) 猫の髭、学名:Orthosiphon aristatus 花が面白い!。赤紫色を帯びた茎の先端に、白い(または淡紅の)花を総状に咲かせるが、 長く伸びる雄しべが「猫のひげ」のように見えることから、Cat’s whiskers の名が・・・。 利尿・血圧降下作用もある薬用植物。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'02/ 9/13 |
 |
ネコノメソウ(ユキノシタ科) 猫の目草、学名:Chrysosplenium grayanum 助け合うかのように寄り添って咲く、色淡く、柔らかい、湿地の花。花には花弁はなく、黄緑色の萼片が4個ある。 果実は熟すと2つに割れる。この裂開した果実の形が猫の目に似ているというので、この名がついた。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'07/ 4/ 8 |
 |
ネコヤナギ(ヤナギ科) 猫柳、学名:Salix gracilistyla 柔らかい早春の日差しにきらきらと輝く、銀色の毛に覆われたお馴染みの花穂。 だが、開花した黄色い花(円内)を見た人は少ないかも・・・。 ふわっとした銀色の柔毛の質感はネコの毛にそっくり。で、「ねこやなぎ」の名がつけられた。 撮影地:万博自然文化園、 年月日:'02/ 2/16、'03/ 3/29 |
 |
キャットテール(トウダイグサ科) Cat tail、学名:Acalypha hispaniolae 非耐寒性常緑多年草で、猫のしっぽのような紅色の花が密に集まってひも状に垂れ下がる。 この赤い花穂を「猫の尾」に見立てて、キャットテールの名で出回る。鉢からこぼれんばかりに咲き、美しい。 葉の美しい観葉種アカリファの中で、ベニヒモノキとともに花も観賞。 撮影地:豊中・服部緑地都市緑化植物園、 年月日:'03/ 2/28 |
 |
ブルーキャッツアイ(ゴマノハグサ科) blue cat's eye、学名:Otacanthus caeruleus 花弁の中心に白いアクセントがあり猫の目のように見えることからつけられた愛称で、正式にはオタカンサスという。 ブラジル原産の多年草で、高さ60〜120cmになる。葉は対生し、茎の上部の葉脈に花がつく。上下2唇の大きい花弁が紫色で美しい。 撮影地:大阪花博記念公園・咲くやこの花館、 年月日:'01/10/24 |
 |
ブタノマンジュウ(サクラソウ科) 豚の饅頭、学名:Cyclamen persicum 「シクラメンのかほり」で唄われた、うつむきかげんに咲く、真綿色や薄紅色のシクラメンの花は、頬を染めてはにかんでいる少女を思わせる。 別名:かがりびばな(篝火が燃えるように見えることから牧野富太郎が命名)、ぶたのまんじゅう(球根を豚が食べることから)。 撮影地:大阪花博記念公園・咲くやこの花館、 年月日:'04/12/21 |
 |
パンダスミレ(スミレ科) 学名:Viola hederacea オーストラリア原産の数少ないスミレの一つ。 おもわせぶりな愛称は、白と紫の花のコントラストがパンダを連想させるので。 ツルスミレとも呼ばれるように茎が長くのび、吊鉢栽培もおもしろい。花期は長く、晩秋まで咲く。 撮影地:滋賀農業公園ブルーメの丘、 年月日:'03/ 7/10 |
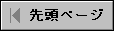 − Photo : Yasuda Hiroshi −
− Photo : Yasuda Hiroshi −