
学名:Cananga odorata
「イランイラン」とは変な名前だが、マレー語のアランイラン(花の中の花)という意味だとか。
花弁が淡い緑色から黄色になった頃に、良く香る。香りはエキゾチックな甘い香り。花からとる精油は香水として利用される。
撮影地:とっとり花回廊(鉢)、 年月日:'03/10/26
|
 |
イランイランノキ(バンレイシ科) 学名:Cananga odorata 「イランイラン」とは変な名前だが、マレー語のアランイラン(花の中の花)という意味だとか。 花弁が淡い緑色から黄色になった頃に、良く香る。香りはエキゾチックな甘い香り。花からとる精油は香水として利用される。 撮影地:とっとり花回廊(鉢)、 年月日:'03/10/26 |
 |
モッテノホカ(キク科) 食用として栽培されている菊の一種。 独特の芳香があり、生鮮品に添えるほかキク海苔にして酢の物や和え物など各種の料理に使われる。また花壇や切り花にも向く。 おもしろい名のいわれは、「思いのほかうまい」など諸説あり。 細い薄紫の花びらで、筒状に丸まっているのが特徴。 撮影地:国華園、 年月日:'04/11/16 |
 |
オシロイバナ(オシロイバナ科) 白粉花、学名:Mirabilis jalapa 種子の中に白い粉状の胚乳があり、白粉(おしろい)花と名づけたのは貝原益軒。夏の夕方ほの白く咲くことから「夕化粧」の名も。 都会の路地裏などにも栽培されている、どこか親しみを覚えさせる花。 この花の近くでデートすれば蚊に刺されないとか・・・、ほんとかな。 撮影地:吹田市、 年月日:'01/10/31 |
 |
マーマレードノキ(ナス科) 学名:Streptosolen jamesonii 輝くようなオレンジの花が印象的。花色がマーマレードを連想させ、園芸店では「オレンジマーマレード」の名でも見かける。 室内では2月頃から、戸外では春から秋まで咲き続ける。 コロンビア、エクアドル原産の非耐寒性の常緑低木。 撮影地:鉢植え、 年月日:'03/ 3/ 2 |
 |
オジギソウ(マメ科) 含羞草、学名:Mimosa pudica ちょっと触っただけでお辞儀する礼儀正しい葉。閉じるとわかっていても、触ってみたくなる。 葉が刺激に感応して開閉運動をするので、ネムリグサ(眠草)の名もある。 夏、淡紅色の愛らしい小花が咲く。 撮影地:名古屋市東山植物園、 年月日:'02/ 5/ 4 |
 |
センリョウ(センリョウ科) 仙蓼・千両、学名:Chloranthus glaber 万両(ヤブコウジ科)とともに縁起をかついだ命名で、正月の縁起物として馴染み深い。真冬につぶらで小さな赤い実が熟す。 カラタチバナは百両、ヤブコウジは十両と呼ばれたりするが、一両に該当する植物はない。 葉の上に実を現すのが千両、葉の下に垂れるのが万両。 撮影地:自宅切り花、 年月日:'99/11/28 |
 |
ローソクノキ(ノウゼンカズラ科) candle tree、学名:Parmentiera cereifera 果実は長さ30〜120cmの円柱形で、下垂し、淡黄緑色に熟し、ローソクのよう。リンゴ様の香りがあり、牛が食べる。 花は長さ6〜7cm、白色、波状縁で、短命である。萼は大きく、外側は褐色を帯びる。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'03/11/27 |
 |
ローソクラン(ラン科) アーポフィラム・ギガンティウム、学名:Arpophyllum giganteum 花茎はバルブの頂部から直立し、総状に密に小花をつける。円筒状に開花させる花姿から「ローソクラン」の愛称でも呼ばれている。鮮明な濃桃紫色の花。 メキシコ、コスタリカなどの中央アメリカに分布。 撮影地:神戸らん展、 年月日:'04/ 4/ 1 |
 |
チャルメルソウ(ユキノシタ科) 哨吶草 渓流沿いなどの湿ったところに生える多年草。花弁は紅紫色で長さ約2mm、羽状に切れ込み、うしろにそり返っている。 裂開した果実の形がラーメン屋の吹くチャルメラに似ているのでこの名がある。 写真は、モミジチャルメルソウ(Mitella acerina)。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'04/ 4/16 |
 |
ノコギリソウ(キク科) 鋸草、学名:Achillea alpina 糸鋸のように細かく切れ込む葉、平安時代には占いに使われた茎、でも花は可愛い。 茎の先に直径1cmほどの頭花が密に集まってつく。頭花の外側には白色の舌状花が5〜7個あり、中心に筒状花が多数ある。 撮影地:吹田市、 年月日:'01/ 5/23 |
 |
キランソウ(シソ科) 金襴草、学名:Ajuga decumbens 名は、その生えている様子が金襴の織物の切れ端に似ていることに由来。畑や庭のすみ、道ばた、林のふちなどに生える多年草で、春に濃紫色の唇形花を開く。 葉が放射状に広がり、地面にふたをしたようにへばりついていることから、「地獄の釜の蓋」とも呼ばれる。 撮影地:六甲高山植物園、 年月日:'05/ 5/ 2 |
 |
パイナップルリリー(ユリ科) Pineapple lily、ユーコミス、学名:Eucomis autumnalis 聞き慣れない、見慣れない観賞植物だが、花の咲く姿を目にすれば、強く焼きつく。パイナップルそっくりなのである。 長さ50cm近い太い花茎をあげ、100ほどの花がかたまって咲き、その上に30枚前後の葉が出る。一つずつの花は星形。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'02/ 7/12 |
 |
バニラ(ラン科) Vanilla、学名:Vanilla planifolia 中南米の熱帯地方原産の多年草。 バニラの花を見たことがある人は少ないのではないでしょうか?。花は咲いても半日しかもたない。 ちなみに、花からはあのアイスクリームなどに使われるいい香りはほとんどしない。バニラの香りは、果実を醗酵させることによって香る。 撮影地:大阪花博記念公園・咲くやこの花館、 年月日:'06/ 5/10 |
 |
ヒトリシズカ(センリョウ科) 一人静、学名:Chloranthus japonicus 早春の林の中の日陰にひっそりと、白い花穂を静かに伸ばして咲く、しとやかな花。花といっても花弁も萼片もない、雄しべと花糸だけの花である。 白く美しい花糸を静御前にたとえて、名付けられた。一人は、花穂が一つであることに由来する。 撮影地:万博自然文化園、 年月日:'06/ 4/24 |
 |
ヘクソカズラ(アカネ科) 屁糞蔓、学名:Paederia scandens 全草に悪臭があり、和名はヘクソカズラ。だが、愛らしい花を見ていると、この名はちょっと気の毒。 花は可憐で、早乙女花の名もあり、花の中心部が赤く、お灸(やいと)の跡に似ているので、ヤイトバナとも呼ばれる。 撮影地:吹田市、 年月日:'02/ 8/ 7 |
 |
ポーチドエッグ(リムナンテス科) Poached egg、学名:Limnanthes douglasii リムナンテス。英名のポーチドエッグは目玉焼きのような煮た卵のことで、花の特徴をユーモラスに、ピタリと表した名前。 一年草で寒さに強いので、秋まきすると春に咲く。花は、黄色で先端が白い。 北アメリカ(カリフォルニア、オレゴン)原産。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'03/ 5/16 |
 |
ストロビランテス・アニソフィルス(キツネノマゴ科) ランプの妖精、学名:Strobilanthes anisophyllus 葉の緑色が寒くなるにつれ黒紫色になって、うす紫の筒状花を咲かせ、「ランプの妖精」と呼ばれている。自然開花期2〜6月。 長楕円形の葉を対生するが、左右に出る葉の大きさが異なるのが特徴。 撮影地:大阪花博記念公園・咲くやこの花館、 年月日:'02/ 3/ 7 |
 |
サザンクロス(ミカン科) Southern cross、クロウエア、学名:Crowea exalata 「サザンクロス(南十字星)」の名は、南半球の代表的な星と星状の花形にちなむ。 茎葉に柑橘系の香りがあり、濃桃色の5弁の星形の花を小枝に多数つける。 暑さ寒さに比較的強く、鉢物、グランドカバーにも利用される。 撮影地:自宅鉢植え、 年月日:'01/ 9/15 |
 |
ダイヤモンドリリー(ヒガンバナ科) Diamond lily ネリネ(Nerine)。ギリシャ神話に登場する美しい水の妖精ネリネの名に由来する。光が当たるといっそう輝くように咲くことから、ダイヤモンドリリーの名がある。 甘い花色のみずみずしい花は、ほんとうに妖精を思わせるよう。 撮影地:大阪府立花の文化園、 年月日:'02/11/12 |
 |
タバコソウ(ミソハギ科) ベニチョウジ(紅丁子)、クフェア・イグネア、学名:Cuphea ignea 開花は夏〜秋、花筒は鮮紅色、先端部は黒紫の輪があり、口部は白。まるで赤い紙巻きタバコのような花。 クフェアには、このイグネアの他にメキシコハナヤナギ(小さなピンクの5弁花)や‘タイニーマイス’(ネズミの顔のような花)などがある。 撮影地:京都府立植物園、 年月日:'03/ 9/11 |
 |
イチゴノキ(ツツジ科) 苺の木、学名:Arbutus unedo 果実を見立てて、英名は Strawberry Tree と、おいしそうな名の木に。ただし、ヤマモモのイメージ。生食よりジャムや果実酒に利用。 常緑の小高木。花も楽しめ、それはスズラン状で、アセビに似たクリーム色の花。実は1年をかけて真っ赤に熟し、花と共に見られる。 撮影地:大阪府立花の文化園、 年月日:'02/11/12 |
 |
エッグボール(キク科) キバナオランダセンニチ、学名:Spilanthes acmella スピランサス、タマゴボールの名でも出回る。葉は主として根出葉、草丈30〜40cmで、長い花柄を出して頭花を単生する。 頭花は卵形で径2cm、筒状花のみで黄色。花の中心部は褐色で斑点状に見える。花壇縁取り用。花期は夏〜初冬。 撮影地:兵庫県フラワーセンター、 年月日:'02/11/11 |
 |
シューティングスター(カヤツリグサ科) Shooting Star、シラサギカヤツリ、シラサギスゲ、スターグラス 学名:Rhynchospora colorata(=Dichromena colorata) 総苞片のつけ根が白くなり、緑色の先端が長く垂れ下がって、「流れ星」さながら。地味な風媒花が多いカヤツリグサ科の中では異色の虫媒花。開花5〜10月。 撮影地:大阪市・茶屋町、 年月日:'01/11/ 9 |
 |
オニシバリ(ジンチョウゲ科) 鬼縛り、学名:Daphne pseudo-mezereum 樹皮が丈夫で、鬼でもしばれるというのでこの名があるが、冬は緑で夏に落葉することから、ナツボウズ(夏坊主)の名もある。 山地に生える落葉小低木。早春に、葉のつけ根に黄緑色の4弁の香る花を咲かせる。 撮影地:鉢植え、 年月日:'05/ 3/19 |
 |
クンショウギク(キク科) 勲章菊、ガザニア、Gazania 南アフリカ原産の一年草。高さ15〜20cmの花茎を伸ばし、直径5〜6cmの頭花を1個ずつつける。花は朝開き、夕方に閉じる。 舌状花弁の基部に模様があり、頭花は中心の周りに色の異なる輪ができ、華やか。それで「勲章」に見立てられた。 撮影地:自宅鉢植え、 年月日:'00/ 5/ 1 |
 |
スターフルーツ(カタバミ科) ゴレンシ(五斂子)、学名:Averrhoa carambola 一風変わった果実の形で親しまれ、横に切ると断面が星形をしているので スターフルーツ の名が。 果肉は多汁質でさわやかな酸味があり、ビタミンCやペクチンに富む。生食のほかジュースやジャムに。花色は桃〜赤紫。 撮影:京都府立植物園、'02/ 1/24(実)、 咲くやこの花館、'04/ 5/14(花) |
 |
ドラクラ(ラン科) 学名:Dracula cordobae カトレアなどの華やかなランから想像もつかないような、妖艶な花を咲かせるラン。 夏でも涼しい高地雲霧林で、夜の霧の中に浮かび上がる不気味な姿。で、吸血鬼ドラキュラ(Dracula)の名をもらったのか。 撮影:大阪府立花の文化園 、 '09/ 9/ 9 |
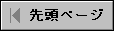 − Photo : Yasuda Hiroshi −
− Photo : Yasuda Hiroshi −