| <<What's New>> パソコンとPCオーディオ奮闘記 2015年後半 |
|
|
![]() 2015-12-22(火) MathAudio
Room EQ のその後
2015-12-22(火) MathAudio
Room EQ のその後
MathAudio Room EQ を使うことで定位が飛躍的に向上し、ZENSOR1 がモニター並の音になったが、色々な曲を聴いてみると幾分造った音になると感じていた。
原因は恐らく音響測定用のマイクの使い方だろうと思いマイクで拾った音をヘッドホンで聴いてみた。するとやはり無指向性のマイクで拾った音は普段聞いている音よりも反響音が強調されている事が分かった。マイクの位置や向きを変えてみたがそれ程改善されなかった。所がマイクを耳の所に持っていくと普段聞こえる音に近づくことが分かった。
ではと言うことでマイクを耳のところに置き測定・補正してみたら好結果が得られた。
定位の向上はそのままに自然な音が出るようになった。測定結果は下図のように高域が上がっているが、今のところこれがベストのようだ。
Reference は Neutral の方が自然に近い。
![]() 2015-12-15(火) 430
MHz 用ループアンテナ GH-4
2015-12-15(火) 430
MHz 用ループアンテナ GH-4
グローバルアンテナ研究会では移動運用向けに様々なアンテナを紹介している。その中でも手軽に利用できる 430 MHz 用の 4 エレループアンテナ GH-4 を研究会から実費で分けていただき使ってみた。
GH-4 は本来屋外で使用するものだが、室内でも十分な性能を発揮した。
固定アンテナと違い偏光面が簡単に調整できるので、反射を利用した電波への対応が容易だ。430 MHz の場合山岳反射を利用した通信が良く行われるが、その時の電波は垂直偏波からズレているケースが多い。ホイップアンテナは垂直偏波用なので水平に偏向している電波を受けると FM 波は音声が歪む。この時の電波をパソコンの SDR を使ってパワースペクトルを見ると、変調波が上下側波帯で異なっている。この波をGH-4で受け、給電点を上下に動かす(偏光面を変える)と多少信号レベルは下がるものの歪みの減るポイントがある。音声がよりクリアになり明瞭度が上がる。これが GH-4 の最大のメリットだろう。
そう言えばサガ電子のアローラインアンテナは利得は低めだが明瞭度は高いと言われている。もしかしたら偏光面が垂直ではなく少し水平側にシフトしているのかもしれない(根拠のない憶測)。
室内に設置したグローバルアンテナ研究会の 4 エレループアンテナ GH-4 (垂直偏波向けの設置。給電点が上下の中心)
![]()
![]() 2015-12-07(月) MathAudio
Room EQ は使える
2015-12-07(月) MathAudio
Room EQ は使える
鮫島さんからご紹介いただいた MathAudio の Room EQ for foobar2000 を試してみた。
foobar2000 の DSP コンポーネントとして組み込んで部屋の反響音を補正するソフトウェアで、無料でダウンロード・利用ができる。補正するためには音響測定用マイクとその音をパソコンに取り込むインターフェースが必要で、今回は EMM-6 と US-366 を使った。リスニング位置に EMM-6 を置き、マイクを天井に向けて反響を測定した。
その結果が下図でいくつかのピークが現れている。 130 Hz あたりのピークは部屋の奥行きの共振周波数と合致している。
補正をかけるとピーク周波数の音が抑えられて反響音が軽減する。補正レベルを変えていくと音が変わっていくのが良く分かる。補正すると確実に定位が向上して音の癖がなくなって行き、だんだんモニタースピーカーの音に近づいていく。−10 dB 位補正した所が定位・音質が最も良い感じになった。
これを使うとこれまで周波数特性を測定してそれを元に手動でパライコを調整していた作業が不要になる。非常に便利なツールだ。このツールを使うと確実に音が良くなる。ZENSOR1 がモニタースピーカーに変わった感じだ。補正量で音色が変わるので、それを楽しむこともできる。
Room EQ for foobar2000 の測定・補正画面 130 Hz あたりに部屋の共振がある。補正は−10 dB 位が適当
![]() 2015-12-04(金) FT-60
の
MIC/SP 端子接触不良
2015-12-04(金) FT-60
の
MIC/SP 端子接触不良
FT-60 はハンディ機だが、家の中で使うときはハンドフリーにしたいので MIC/SP 端子を利用してマイク、スピーカーと送受信切り替えスイッチを外付けにする事にした。
ところが、4P ミニプラグの接触が悪く送受信切り替えスイッチを操作しないのに送信になってしまったり、音声が入らず無変調になってしまったり、動作が不安定になってしまった。
仕方ないので無線機を購入元に送って見て貰うことにした。また、一時 QRT となる。
FT-60 の利用状況 マイク・スピーカーを外付けにした。写真の左下は送受信切り替え用マイクロスイッチ
<追記>
販売元で確認したら「FT-60 側のジャックに不具合が出ていると思う」との事でメーカーのサービスセンターへ送る事になった。販売元が福井市で八重洲のサービスセンターが都内なので効率の悪い輸送が発生している。調べたら八重洲のサービスセンターは羽田空港の近くでここから 5 km 程の所にあるようだ。
![]() 2015-11-15(日) SUMI2013
の HDD が飛んだ
2015-11-15(日) SUMI2013
の HDD が飛んだ
インターネットを見ている時に急に HDD からカタカタという音が出てパソコンが動かなくなってしまった。
調べてみると内蔵の HDD がクラッシュして認識されなくなってしまった。何度か復旧を試みたが結局認識できなかったので、新しい HDD を買ってきて OS から入れ直しとなってしまった。
1 週間前にデータをバックアップしていたが、HAMLOG のプログラムはルートディレクトリーにあったためデータがバックアップ対象外となっていた。交信記録を全て入れ直す羽目になってしまった。
完全復旧にはもう少し時間がかかりそうだ。
![]() 2015-11-01(日) QSL
カード完成
2015-11-01(日) QSL
カード完成
QSL カードのデザインが決定したので印刷に出した。今回選んだ印刷会社は、通販の iColor。最初は QSL カード専門のキュービックを候補としていたが、インターネットの使い勝手が悪かったのでこちらに変更した。 iColor はメールのレスポンスも良かった。
Photoshop の PSD データを送ってから約 1 週間で納品された。想像していたよりは明るめだった。やはりモニターで見る色とは違っている。まあ写真ではないので、この程度なのだろう。
データ面は iColor の標準様式 7 (2 色)で印刷して貰った。Turbo HAMLOG でプリントすると周波数や RST の位置が少しずれているので微調整した。完成した QSL カード(印刷物をスキャン) ある程度溜まったら JARL に送ろう。
![]() 2015-10-22(木) MUSIC
BIRD を試聴してみた
2015-10-22(木) MUSIC
BIRD を試聴してみた
TOKYO FM が運営する高音質「音楽専門」衛星デジタルラジオ MUSIC BIRD の番組の一部がインターネットで試聴できるので聞いてみた。
中でもオーディオ実験工房が面白そうなので最初の番組を試聴してみた。この番組では RCA ケーブルの違いによる音の変化を実験していたので、聴くと同時に音声データをそのまま PC に保存して分析してみた。
番組は一部しか公開されていなかったので、試聴では 2 本のケーブルのみの比較となる。保存した音声データの波形を比較するとすぐに両者のレベルに違いのあることが分かった。
高音質とされる 2 本目のケーブルの録音は交換前よりも RMS レベルで 1.4 dB 高かった。もちろんピークレベルも違う。レベルが高いと細かい音まで聞こえるので音が良くなったと錯覚する。1 dB 以上の差があると確実に音が違うと感じるので実に恣意的な操作が行われている。「売るため、スポンサーのためには...」と言う感じだ。ケーブル交換前の波形の統計画面 ケーブル交換後の波形の統計画面 RMS レベルやピーク値がケーブル交換後に上がっている。 レベル合わせをした後のスペクトルには差がなかったので、イコライザーまでは操作していないようだ。
レベル合わせ後のスペクトル ケーブルによる違いはない。
![]() 2015-10-20(火) ワイド FM 試験放送中
2015-10-20(火) ワイド FM 試験放送中
90.5 MHz で TBS ラジオの FM 中継補完局がスカイツリーから試験電波を出していた。12 月から正式に「ワイドFM」として本放送がスタートするらしい。
SDR# で一寸聞いた所では FM 特有のノイズによる歪は少ないようだ。ただ、アンテナの位置が悪いとマルチパスによる歪が出る。
少し聞いていたら急に電波が消え、雑音だけになってしまった。まだ本格運用はしていないようだ。内容も AM とは違っていた。
ワイドFMの周波数
TBSラジオ:90.5 MHz、文化放送:91.6 MHz、ニッポン放送:93.0 MHz。 出力は 7 kW
同じアンテナから送信している筈なのに文化放送は信号が 10 dB ほど弱い。まだフルパワーを出していないのだろうか。ニッポン放送は電波が出ていなかった。
![]() 2015-10-19(月) DSD
のノイズ
2015-10-19(月) DSD
のノイズ
e-onkyo で「ハイレゾで聴くカラヤン& ベルリン・フィルの 25 曲」を買ってみた。FLAC 型式(96 kHz/24 bit)版を買ったのに 25 曲中 18 曲(No. 1, 4, 5, 11 〜 25)は下図のような DSD 特有の帯域外ノイズが入っていた。制作の途中で DSD を使ったのだろう。
買ってみないと分からないのは困ったものだ。
SR-009 で聞いてみると、DSD ノイズの入った曲は超高域がシャリシャリしていて歪が気になる。やはり DSD 版はフィルターをかけないとダメないようだ。
25 曲で 1,400 円と安かったので録音はあまり良くないが、クラシックは音割れが少ないので安心して聞ける。
【雑 感】
10 月 17 日に音展(おとてん)に行ってみた、STAX の新しいイヤースピーカーとドライブアンプが展示されていた。今使っている SR-009 よりも中音がきれいに鳴っていた。
音のサロンで最新スピーカー 6 機種を聞いたがどれも満足の行くものはなかった。声がきれいに再生できないものはスピーカーではないと力説していたが、そうすると今回のものは全てがスピーカーではないことになってしまう。それはそれで正しい判断かもしれない。原理的に振動板を使う方法では正確な再現はできないのかもしれない。マイクも然り。
![]() 2015-10-13(火) USB
ケーブルで音が変わるか
2015-10-13(火) USB
ケーブルで音が変わるか
結論は『機器が正常なら変わらない』
以前から USB-DAC の USB ケーブルで音が変わるか否かが話題になっているので簡単に試してみた。
【測定条件】
入力波形:FLATSWEEP_131072/60秒
再生ソフト:WaveGene/192 kHz,24ビット/−6 dB
PC:SUMI2013(Core i7-3770)/USB 2.0
DAC:DA-300USB/192 kHz,24ビット
ADC:US-366/RCA入力/192 kHz,24ビット【試したUSBケーブル】
ケーブル1 Belkin ハイスピード 高品質オーディオ用 USB 2.0 ケーブル F3U133V-06-GLD 1.8m ケーブル2 フルテック ハイエンドオーディオグレード USB ケーブル【A】タイプコネクターオス【B】タイプコネクターオス GT2 USB-B 1.2m
【比較内容】
ケーブル 1 とケーブル 2 の比較
ケーブル 2 を使って 2 回測定した結果の比較
【結 果】
下図の通り。
20 kHz 以下では変動幅は最大でも 0.005 dB 以下。
80 kHz 以上で少しバラツキが大きくなっているがそれでも 0.03 dB 以下。殆ど測定誤差の範囲内でとても耳で聞き分けられるレベルではなかった。
80 kHz 以上でバラツキが大きくなった原因は、ADC に使った US-366 のノイズによると考えられる。SN 比が 50 dB の時の誤差は 0.03 dB になるので、下図の結果と合っている。
もし、USB ケーブルで本当に音が変わるなら機器内の回路が不安定で、USB 規格を満足していない時ぐらいだろう。昔 USB が不安定で機器を認識しないと言う事例が良くあったので、その延長とも考えられる。ノートパソコンは USB の能力が低いので、不安定になる可能性はある。USB は 2.0 でも最大データ転送速度が 480 Mbit/s なので、電波では UHF に相当する。この周波数で 0 と 1 を切り替えるのだから相当ハードルが高いことは想像に難くない。規格が古いので電子回路が不安定になる可能性は十分にある。
【雑 感】
USB 2.0 の最大データ転送速度 480 Mbit/s は、周波数に換算すると 480 MHz。アマチュア無線では、430 MHz 帯が許可されているので移動用によく使われている。この周波数の波長は 70 cm で、ホイップアンテナは 50 cm 位で使う事が多い。430 MHz はコネクタやケーブルのロスが大きいので利用に当たっては注意が必要だ。これに近いビットレートの USB 2.0 のコネクタを見ると実にロスが大きそうな形をしている。インピーダンスが 90 Ω と少し高めなのでケーブルロスも大きそうだ。この上に更に USB 3.0 の規格があるが本当に詳細を検討したのだろうか?
![]() 2015-10-12(月) Sound
Forge Audio Studio が最も音が良い
2015-10-12(月) Sound
Forge Audio Studio が最も音が良い
PC のプレーヤーソフトは幾つか使ってきたが、これらの中では Sound Forge Audio Studio が最も音が良いようだ。
この結果は忠実度と言う観点からは 2014-08-17 の評価と変わっていない。これまで使ってきた主なプレーヤーソフト:
Audacity
Audials 12
AudioGate 2
AudioGate 3
Bug head Emperor
foobar2000
GOM Player
HQPlayer Desktop
JRiver Media Center 20
MusicBee
Sound Forge Audio Studio
TASCAM Hi-Res Editor
uLilith
Wave File Player
Windows Media Playerどのソフトも ASIO 対応であれば大差はないが、サウンドマッパーを使うソフトの中では、Audacity は 15 kHz 辺りで高域をカットするので再生忠実度は低い。
PCM 再生には Sound Forge Audio Studio が良い(音質面)
Google Play Music からダウンロードしたデータの波形
なぜか−4 dB で抑えられている。最も音が良い Sound Forge Audio Studio は、ファイルを開く時に少し時間がかかるので、ファイル全体をメモリーに展開しているようだ。これが音の良い要因かもしれない。JRiver Media Center 20 もメモリーからファイルを再生できるが、随時読み込みなので能力を発揮しきれていないのだろう。 AudioGate はバッファリングしているらしく 2 回目からはファイルを読みに行かないので性能的には 2 回目以降の方が良いようだ。
Sound Forge Audio Studio は音は良いが、DSD に対応していない事とファイルを読み込むと余計なファイル(*.sfk)が作成され終了しても消えないのが難点だ。
DSD を再生する場合は音質的には TASCAM Hi-Res Editor が良い。
DSD 再生には TASCAM Hi-Res Editor が良い(音質面)
ファイル読み込み時に CPU 負荷がかなり上がる。
Pure AQUAPLUS LEGEND OF ACOUSTICS は比較的録音が良い。
![]() 2015-10-05(月) たまには安いヘッドホンも良い
2015-10-05(月) たまには安いヘッドホンも良い
SR-009 で音楽を聞いていると、録音の悪いコンテンツは音割れが気になって聞くのが辛くなる。 ZENSOL1 で聞いても同じだが、J-POP は半分以上が音割れしている。R&B は多少質が良いが中には音割れしているものもあるので曲を選ぶ必要がある。
ところが、この音割れした曲でも SONY の MDR-CD900ST で聞くとそれ程気にはならない。SR-009 の後で MDR-CD900ST を使うとまるでオモチャのような音に聞こえるが、その分ディテールが聞こえないので、音割れが気にならないようだ。と言うか元々全体に音が薄くて歪んでいるので、差が出ないと言った方が正しいだろう。感動の度合いは減るものの、耳障りな音も相対的に減るので気楽に聞く分にはこちらの方が良い。
いずれにしても、J-POP は安いヘッドホン(MDR-CD900ST)で聞いた方が精神的には良さそうだ。
■制作側がこれでモニターしていたら音割れは改善しないだろう。
![]() 2015-10-04(日) 旧コールサインの復活手続中
2015-10-04(日) 旧コールサインの復活手続中
![]() 2015-09-27(日) Lepy
LP-2024A+ は特性が良い
2015-09-27(日) Lepy
LP-2024A+ は特性が良い
DALI のスピーカー ZENSOR1 は高域が持ち上がっている。ハードディスクに保存した音楽データを聞く時は再生ソフトのイコライザーである程度補正はできるが、ストリーミングは補正できない。また、再生ソフトでもヘッドホンに切り替える時にはいちいちイコライザーの設定を変更する必要があり面倒だった。そこでスピーカー用のアンプをトーンコントロール付きのものに変えてみた。
今回買ったのは Lepy の LP-2024A+。出力は 20 + 20 W で SA-50 の 50 + 50 Wよりは小さいが、ZENSOR1 を鳴らすには十分なようだ。
買ってすぐに周波数特性を測定してみた。結果は下図のように変化の傾向は SA-50と似ているがその特性は SA-50 よりも良かった(値段は LP-2024A+ の方が安い)。スピーカー(SP)を接続した場合には、可聴周波数内では増幅度(GAIN)が ±0.5 dB 以内に入っていた。TREBLE と BASS のツマミをどちらも中央(50 %)にしてトーンコントロールスイッチ(TONE/DIRECT)を ON にすると低域と高域が多少強調された特性となる。両ツマミを 45 % 程度にするとフラットに近づくがどこかにピークを持ち、DIRECT のようなフラットにはならなかった。
LP-2024A+ は周波数特性は良かったが、電源を入れた時やトーンコントロールをパスする(TONE/DIRECT)スイッチを押した時には多少ノイズが出る。また、電源を入れるとボリュームの周りが青色に光るが LED が強すぎて目に良くない。
今回買ったデジタルアンプ Lepy LP-2024A+(左)とこれまで使っていたデジタルアンプ SMSL SA-50(右)
Lepy のデジタルアンプ LP-2024A+ の周波数特性 SMSL のデジタルアンプ SA-50 の周波数特性 また、今回届いたアンプは初期ロットらしく、入力と出力の左右が反対だった。さすがに位相は間違っていなかった(真空管アンプの場合は回路構成上入力と出力の位相が逆になるケースがある)。LP-2024A+ で左スピーカーを SA-50 で右スピーカーを同時に鳴らしてみたが音の差は分からなかった。
当初の目的である高域低減を試してみた所 ZENSOR1 では LP-2024A+ の TREBLE を 35 〜40 % 位にすると良さそうだ。
【イベント】
26 日に東京国際フォーラムで開かれていた「2015 東京インターナショナルオーディオショウ」を見てきたが、どのブースにも満足できる音はなかった(自宅で使っている SR-009 にも負けている)。中でもアナログを標榜する所の音は歪だらけでこれがオーディオ界かと首をかしげたくなった。音の認識レベルが低すぎる。
![]() 2015-09-21(月) InterFM
は音が良い
2015-09-21(月) InterFM
は音が良い
日本の IP サイマルラジオは音が悪いと思っていたが、InterFM は例外だった。何と言っても音声の音割れの少ないのが良い。
何が違うのか色々比較してみると単にコンプレッションの問題ではなく、低域をカットしていない事が功を奏しているように思われる。そう言えば歪の少ない Audiophile - Stream Network も低音が強調されていた。この辺に共通点がありそうだ。
InterFM は低域をカットしていない。
![]() 2015-09-21(月) 1アマの免許証が届いた
2015-09-21(月) 1アマの免許証が届いた
休日にも拘わらず郵便で免許証が届いた。
新しい免許証はカードサイズのプラスチック製で、表面にはホログラム風に富士山が描かれ「日本国 総務省」の印章も印刷されていた。
免許証の番号が分かったので、早速「電子申請・届出システムLite」の登録をした。休日だが電子システムは稼働していた。 1週間後には郵送でユーザIDとパスワードが届くようだ。 送料は誰が払うのかな?
![]() 2015-09-14(月) adsbSCOPE
を試してみる
2015-09-14(月) adsbSCOPE
を試してみる
SDR# で FM 放送が聞こえたので、次にアマチュア無線や航空機の通信などを聞いてみた。そのついでに航空機の位置が分かる adsbSCOPE を試してみた。ネットワークの設定で多少苦労したが、何とか表示できるようになった。窓際に置いた付属アンテナでも結構広い範囲まで受信できている。
ADSB# を起動した後に adsbSCOPE を起動する。 受信周波数は 1,090 MHz
ADSB# は SDR# をダウンロードしたときの圧縮ファイルの中に入っていたので、改めてダウンロードする必要はなかった。
ネットワーク設定の Local を 127.0.0.1 にするのがミソ
![]() 2015-09-07(月) FM
波のソフトラジオは SDR# が良い
2015-09-07(月) FM
波のソフトラジオは SDR# が良い
この前は Radio Receiver を使って IP サイマルラジオと音質を比較したが、その後たまたま使った SDR# が Radio Receiver よりも音が良かったので HDSDR も含めて再評価してみた。
【受信帯域】
日本のFM 放送の占有周波数帯幅は 200 kHz と規定されているが、SDR# で TOKYO FM ほかのスペクトルを観測してみると、ピーク時は約 200 kHz で、時には 250 kHz をオーバーする事があった。全平均電力としては片側 0.5% まで許されているので、その範囲には入っているようだが、帯域が 192 kHz しかない HDSDR では歪んでしまう。
【音質】
電波を使うタイプはどのソフトも FM 特有のシャリシャリノイズ(検波歪)が完全には消えなかったので、この点では IP サイマルラジオの方が良いようだ。 ただ、 radiko は高域が減衰しているので、聴感上は FM 波の方がクリアに聞こえる。 SDR# で 受信した FM 波は低域も強調されているため比較するとFM 波の方が高音質なのかと錯覚する。
声の音割れは SDR# でも解消しなかった。
SDR# の受信画面 時々周波数シフトが 250 kHz を超える。 S/N は 50 dB 程度とあまり良くない(ケーブルテレビの質の問題かも知れない)。この状況では[RTL AGC]のみ[ON]が最もノイズが少ない。
SDR# と radiko のスペクトル比較 SDR#(FM 波)の音はクリア。 radiko に切り替えると籠もった感じになる(時間が経つとなれる)。
SDR# と radiko のスペクトル値の比較 2 台の PC で測定してみたが傾向は同じだった。 SDR# で 受信した TOKYO FM は高域が伸びている。低音は 40 Hz 付近にピークがあり、それ以下は減衰している(帯域制限のため?)。
![]() 2015-09-04(金) FM
放送の音割れ
2015-09-04(金) FM
放送の音割れ
インターネットの書き込みを見ると、どうも最近の FM は Hi-Fi とは言えない状況になっているようだ。 CD の音圧競争同様に各局とも過剰なコンプをかけて音が歪んでいる。これではいくら FM 受信機を良くしてもダメだ。 FM でこれ以上の高音質を追求するのは止めよう。 CD 同様、音圧競争から抜け出してほしい。今の FM の音声は歪んでいて聞いていられない。
インターネット放送で高音質を謳っている OTTAVA でも音声は割れている。 JJazz.net は多少良い。地デジも良く聞くと音声は時々割れて耳障りになる。コンプが出す奇数次の高調波が気になるのだと思うが、もしかしたらコンプをかけた音声は現在のデジタルデータ圧縮方式と相性が悪いのかも知れない。
海外では、Audiophile - Stream Network のように音割れしていない所もある。コンプの性能の違いなのかビットレートの違いなのか? このサイトは少し低音強調気味だが 320 kbps で 22 kHz まで配信されている。
■1アマの合格通知が届いたので早速免許申請した。
![]() 2015-09-02(水) FM
波は音が良い?
2015-09-02(水) FM
波は音が良い?
TOKYO FM の技術部長が YouTube で「IP サイマルラジオよりも電波の方が音が良い」と言っていた。
音が良くなるならと言うことで、USB 接続の FM チューナーを買ってみた。買ったのは、DVB-T+DAB+FM USB チューナー RTL2832U+R820T。 Amazon.co.jp で 1,560 円。【USB チューナーの設定】
- USB チューナー(写真右にある黒いドングル)のアンテナ端子から変換ケーブルで壁の TV コンセントに接続
- USB チューナーをパソコン(SUMI2013)に接続
- Zadig で RTL-SDR 用ドライバーソフトをインストール
- Radio Receiver Google Chrome plugin を Google Chrome に追加
Radio Receiver を立ち上げてスキャンすると自動で FM 局に同調して音が出た。
USB 接続 FM チューナー右の黒いドングル(スティック)だけ使用
Radio Receiver の画面ケーブルテレビの TV 端子に接続したため受信周波数は FM 局の送信周波数とは違っている。
音量を 90 % 以上にすると出力がクリップする。[Record ]ボタンを押すとボリューム 100 % で録音されるのでピーク時には確実にクリップする。【音の比較】
IP サイマルラジオ radiko と聞き比べると期待に反して音質は殆ど変わらないか、局によっては電波の方が歪が多く音質が悪くなるケースがあった。ただ、どちらもトークでは音割れするケースが多いので元が良くないようだ。
今回買った FM チューナーは STEREO にすると電波が弱い時や周波数がずれている時に起きる高域の不要な音が出て歪んでしまうケースがある(Tuner gain を調整しても改善せず)。 MONO にすると解消するが本来の使い方ではないので、実質では IP サイマルラジオに軍配が上がる。
今回の FM チューナーはオーディオ用ではないので、電波とインターネットとの比較について結論はまだ出せない。ただ、Amazonのカスタマーレビューには「AVレシーバのFMより音は良い」との書き込みもあるので、電波が優位になる可能性は低い。
同じ局を聞くと IP サイマルラジオは電波より1秒ほど遅れていた。今回の FM チューナーで久々に時報を聞いた。この点では電波が優位。
![]() 2015-08-31(月) ダイナミックレンジは 70 dB で十分
2015-08-31(月) ダイナミックレンジは 70 dB で十分
普通に曲を聴くレベルを 0 dB として最小と最大のレベルを探ってみた。
結果、音が聞こえなくなるレベルは−50 dB、うるさいと感じるレベルが+10 dB で、かなりうるさいレベルが+20 dB だった。
これから判断すると、オーディオ機器に必要なダイナミックレンジは 70 dB で、CD の16ビット(約 90 dB)があれば十分な事がわかる。音の大きさと入力信号レベル 入力信号レベルの最大と最小との差は 70 dB 音楽を聴くだけならハイレゾの 24 ビットや 32 ビットは全く必要がない。 ハイレゾの 24 ビットと言っても実際の ADC や DAC は 20 ビット程度の精度しかなく、機器には必ず入ってくるアナログ部分の S/N も 20 ビット(120 dB)位が限界なのでそれ以上は架空の話をしている事も明らかだ。
ハイレゾ音源を CD レベルに落としても聴感上は差がない。そろそろハイレゾの妄想から抜け出しても良い頃か?
【雑 感】
DALI のスピーカー ZENSOR1 は高音も綺麗だが、予想以上に低音が出て聞きやすい。このスピーカーの効率はそれ程高くはないが、通常聴くレベルで入力パワーを測定してみたら 50 mW 位だった。ニアフィールドだとアンプは 数 W で十分なようだ。
![]() 2015-08-28(金) 生の音に近い
2015-08-28(金) 生の音に近い
ZENSOR1 でこの CD を聴いたら定位がハッキリしていてかなり生の音に近い。古い録音も入っているが最近のものよりも録音の質が高い。多少エコーがかかってはいるもののコンプレッションがあまりかかっていないことと、マイクの特性が声や楽器に合っているような気がする。
やはり音の善し悪しは殆どがコンテンツで決まるようだ。
生の音に近い CD(Best Audiophile Voices II)
中でも 3 、4 曲目が良い。
![]() 2015-08-25(火) ZENSOR1
のエージングは?
2015-08-25(火) ZENSOR1
のエージングは?
DALI/ZENSOR1 も 100 時間ほど鳴らしたので周波数特性に変化があるか測定してみた。
結果は下図の通りで、前回(購入翌日)と殆ど差はなく、バラツキは測定誤差の範囲内だった。逆に測定の再現性の良さに驚きだ。
ZENSOR1 も最初の数時間は確かに音が変わっていたが、その後は変化がないような感じがする。前回の測定はその変化の後だったので、既にエージングが終わってしまった後だったのかも知れない。
DALI/ZENSOR1 の周波数特性(右スピーカーの前約 10 cm、EMM-6 を動かして測定。赤:購入翌日、青:100 時間エージング後)
100 時間鳴らしても周波数特性に変化はなかった。
ZENSOR1 の説明書には慣らし運転期間は最長 100 時間と書かれているが、B&W 800 シリーズの説明書では 15 時間、その後の慣らし期間に関してはこんな記述がある。
「スピーカーの変化にはほとんど関係ありません。むしろ、リスナーが新しい音に慣れるまでの時間に関係しています。」
B&W の説明書の方が認識は正しく、どうもスピーカーのエージング期間はそれ程長くはないようだ。
SA-50+ZENSOR1 はスティール弦アコースティックギターの音が素晴らしい。でも長時間聴くと頭が痛くなる。
![]() 2015-08-24(月) SA-50
は負荷に敏感
2015-08-24(月) SA-50
は負荷に敏感
これまで 10 Ωの抵抗負荷で SA-50 の周波数特性を測定してきたが、負荷を変えてみたら高域側のパターンが大きく変わった。
負荷抵抗が大きいほど 30 〜40 kHz 付近のピークが大きくなるようだ。負荷を 5 Ωの抵抗にしたらピークは無視できるレベルまで下がり、全体としては普通の特性になった。これは SA-50 特有の問題なのか、デジタルアンプ全般に共通する問題なのだろうか?
実際にスピーカー ZENSOR1 を接続した時の特性(図中の SP)は 5 Ωと 10 Ωの間にあって 45 kHz 辺りに低いピークがある。このままでは DSD の可聴域外ノイズが増幅されてしまう。やはり LPF が必要なようだ。
いずれにしてもこのデジタルアンプ SA-50 はインピーダンスの低いスピーカー向きのようだ。
SA-50 の周波数特性(4 種類の負荷で測定) SA-50 は負荷により高域の周波数特性が大きく変わる。
![]() 2015-08-23(日) SA-50
の周波数特性(再測定)
2015-08-23(日) SA-50
の周波数特性(再測定)
前回サイン波とデジタルオシロスコープを使って測定した SA-50 (SMSL 製デジタルアンプ)の周波数特性は少し歪(いびつ)だったので、測定方法を変えて再測定してみた。
今回は、FLAT SWEEP 波(131,072ポイント)を使ってみた。
【測定方法】
- 192 kHz, 24 bit の FLAT SWEEP 波を DA-300USB から出力して SA-50 に入力、スピーカー端子に 10 Ωの抵抗を接続してその電圧を US-366 の RCA ラインインプットに入力、WaveSpectra のピークホールド機能でピーク値を測定 ……… 測定結果1
- 同じ波形を DA-300USB から出力して US-366 の RCA ラインインプットに入力、WaveSpectra のピークホールド機能でピーク値を測定 ……… 測定結果2
SA-50 の周波数特性 = 測定結果1 / 測定結果2
なお、上記の計算には EXCEL を使っているが、WaveSpectra からのデータの取り込みには、オーバーレイ機能を利用している。オーバーレイ機能で保存したデータファイル名の拡張子(.wso)を".csv"に書き換えることで EXCEL で読み込めるデータファイルになる。
【結 果】
これで求めた特性は下図の通りで、前回と同様に 30 〜40 kHz 付近にピークがあるものの、 7 kHz 付近の谷は消え、1 kHz 付近の特性がフラットになった。今回の結果の方が正しいように思える。
SA-50 の周波数特性(再測定)
いびつさが取れた
![]() 2015-08-21(金) SA-50
の周波数特性
2015-08-21(金) SA-50
の周波数特性
SMSL のデジタルアンプ SA-50 の周波数特性を測定してみた。
結果は下図の通りで、オーディオ用アンプとしてはあまり良い特性ではなかった。中でも 30〜40 kHz 付近に不要なピークがある。可聴域外だが、混変調歪を発生させる恐れがあるので良くない。低音側は 10 Hz で 3 dB 下がっている。パソコンのライン入力よりも特性が悪い。
SA-50 の周波数特性
周波数特性はあまり良くはない。100 Hz の矩形波を入れて出力波形を見てみると、低域特性が悪いためか平坦部分が減衰傾向になっている。硬質と評価される一因はこれだろう。低音側のカットオフ周波数が高すぎる。これでは SR-009 と同じような腰の弱い低音になってしまうだろう。
100 Hz の矩形波を入力した時の出力波形 SA-50 は評判の良いアンプだが周波数特性は必ずしも良くはないようだ。
![]() 2015-08-19(水) 1アマを受験してみた
2015-08-19(水) 1アマを受験してみた
8月16日(日)に”1アマ(第一級アマチュア無線技士)”の試験を受けてみた。自己採点で法規、無線工学ともに 90 % 以上はとれたようだが、法規に変な問題があった。
それは問題 B−2 の オ で、電波の型式の記号が「G7D」の主搬送波の変調の型式が「角度変調であって位置変調」と書かれていた。正式には「角度変調であって位相変調」となるので、適合しないの 2 が正解となる。ひっかけ問題なのか誤植なのか分からない。試験中に気がついたのでこれには引っかからなかった。
先月の“第一級陸上無線技術士「無線工学の基礎(FK707)」”試験問題に誤植があったばかりなので、これも誤植(タイプミス)かもしれない。
試験勉強にこの2冊を使ったが、これらにも間違いが多数あった。最近はハムのレベルが下がっているのか?
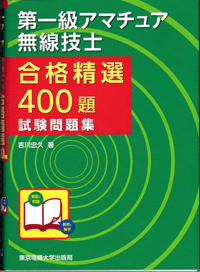
![]() 2015-08-17(月) デジタルアンプの特性補正
2015-08-17(月) デジタルアンプの特性補正
ZENSOR1 + SA-50 は当初イコライザーによる補正は不要と思っていたが、長時間聴いていると頭が痛くなるのでサンプリング周波数を 192 kHz にして再測定してみたら 20 kHz あたりにピークがあった。どうもこれがデジタルアンプの硬質の一因のようだ。
サンプリング周波数 192 kHz で作成したホワイトノイズを再生してスペクトルを見ながらパライコを調整した結果、下図の設定で無理のない特性になった。これで音を聞いてみたら刺さりがなくなりバランスも良くなった。
重低音が出ない事とボーカルの歪感が完全には払拭されてはいないがこれまでの最高の音になっている(昔、コーラルの 10CX50 を 200 リットルの箱で鳴らしていた時(アンプは真空管だった)と同じレベル)。
ZENSOR1 + SA-50 のパライコ設定これで刺さりがなくなった。
![]() 2015-08-15(土) DALI
ZENSOR1 の周波数特性
2015-08-15(土) DALI
ZENSOR1 の周波数特性
新しく買ったスピーカー DALI ZENSOR1 の周波数特性を測定してみた。
【 スピーカー正面 10 cm 】
結果は下図の通りで、低域と超高域が多少持ち上がっているがかなりフラットだった。
ONKYO GX-70HD2 のような左右の差はなく変曲点を持つ凹凸もない。特に超高域は非常にフラットだった。
スピーカー前面では 100 Hz 以下はなだらかに下がっていた。全体としてはフラットだが、さすがに仕様から推測される ±3 dB の範囲には入っていなかった。仕様は、"周波数特性(+/-3dB)/53 Hz 〜26.5k Hz)"となっていて、53 Hz 〜26.5 kHz の範囲内ではどの周波数でも ±3 dBに入っているとは書かれていない。
それでも、GX-70HD2 よりはかなり良い特性だ。ZENSOR1(+SA-50)の周波数特性(スピーカーから 約 10 cm)
FLATSWEEP016384、EMM-6 で測定、30 Hz 以下は測定時の騒音【リスニングポジション】
リスニングポジションではスピーカーの近くよりも超高音域が低下してよりフラットになっている。 当然だがスピーカーに近づくと高域が強調されて鮮明になる。
また、低域が 40 Hz まで伸びて全体のバランスが良くなっている。低域に関してはバスレフのダクト穴が背面にあるため、壁からの反射音が届いているようだ(スピーカーと壁とのすき間は 約 3 cm )。 40 Hz まで出ていればサブウーハーは必要ないだろう。低域に関しては仕様よりも性能が良い。仕様はある条件下での測定結果なのであまり当てにはならないようだ。
リスニングポジションでは 130 Hz 辺りに山があるが、これは設置環境の影響だろう。 壁からの距離 約 1 m が影響している気がする。 パライコで 130 Hz と 100 Hz を補正してみたが、補正しない方が好みに合っていた。
ZENSOR1(+SA-50)の周波数特性(リスニングポジション:左右のスピーカーから 約 70 cm)
FLATSWEEP016384、EMM-6 で測定、30 Hz 以下は測定時の騒音
【その他】
今回の測定で気がついたのは、測定中のフラットスイープ音がうるさくない事だ。高域の特性がフラットだと測定音も聞きやすくなるようだ。
【参 考】
これまで使っていたスピーカーは 1 〜2 kHz あたりに変な山谷があり、補正に苦労した。
ONKYO GX-70HD2 の周波数特性
![]() 2015-08-13(木) DALI のスピーカーを購入
2015-08-13(木) DALI のスピーカーを購入
スピーカーを少しグレードアップしようと言うことで、DALI の ZENSOR1 を購入した。色はモニターに合わせてブラックとした。
以前のスピーカー(GX-70HD2)はアンプ内蔵だったので、今回はパワーアンプも併せて購入した。 買ったのは Amazon で評価の高かった SMSL のデジタルアンプ SA-50 で出力は 50 W × 2 。 超小型で余分なものは一切ついていない。
スピーカーにはケーブルが付属していなかったので、近くの電気店で BELDEN のケーブル(STUDIO 717EX)を追加購入した。ケーブルは太い方が良いだろうと少し太めのものを選んだが、太すぎて撚り線の一部がアンプのスピーカー端子の穴に入りきらなかった。ケーブルは 1 m しかないのでもう1ランク下のものでも良かった。
さて、このアンプとスピーカーで鳴らした音はと言うと、まず GX-70HD2 に比べて中・高域の歪が少ないので音が綺麗に響く。聴いた感じでは周波数のバランスが良いのか全く癖がない。これならイコライザーによる補正は必要ないだろう。低音もそこそこ出ているのでサブウーハーも必要ないようだ。
女性ボーカルの表現は SR-009 よりも上だ。
SMSL のデジタルアンプ SA-50 ゲインが大きいので RCA 接続ケーブルの途中に 20 dB のアッテネータを入れた。
購入した DALI のスピーカー ZENSOR1 評判通りのすばらしい音が出る。
![]() 2015-08-06(木) SR-009 の補正
1つの解
2015-08-06(木) SR-009 の補正
1つの解
400 Hz の矩形波を使って SR-009 の特性をイコライザーで補正していたが、 foobar2000 のイコライザーでは細かい補正ができず、結局 JRMC のパライコ(パラメトリックイコライザー)にたどり着いてしまった。
その設定は単純で、下図のように 1,136 Hz を 4 dB 下げるだけで波形がかなり改善される事が分かった。
まだ完全ではないが、この補正で SR-009 の癖は殆どとれて、ボーカルの声が瑞々しくなった。 これが1つの解(スイートポイント)のようだ。
400 Hz 矩形波の再生波形(上がパライコなし、下がパライコあり) JRMC パライコの設定画面
![]() 2015-08-04(火) BOSE のヘッドホンを購入
2015-08-04(火) BOSE のヘッドホンを購入
スピーカーの周波数特性を正確に測定しようとすると、どうしても大音量になってしまう。長時間の測定はうるさいので、防音のために BOSE のノイズキャンセリングヘッドホン QuietComfort25 を買った。 BOSE のヘッドホンは以前使った事があるが、ノイズキャンセリング能力は抜群だ。
本来の目的とは違うが、早速再生特性を測ってみた。周波数特性を見ると低音がブーストされていて何と 20 Hz でも減衰していない。高域は 6 kHz から急激に下がっている。それでも 10 kHz で −20 dB 程度なので、以前使っていた QuietComfort より高域が伸びているようだ。
400 Hz の矩形波を再生してみると、SR-009 のような変な立ち上がり時のピークはなく、より矩形波に近い波形だった。 ただし、平坦相当部分が減衰せず増加傾向のままなので、ブーミーになっている。 3 kHz 位の振動はイヤーパッドの内寸(約 6 cm)に関係していると思われる。
音を聞いてみると、BOSE 特有の強調された低音と減衰させた高域のために籠もった感じになっている。 SR-009 と比べるとボーカルがかなり引っ込んでいる。 ただ、高域の刺激がないので長時間のリスニングには向いているようだ。
購入した BOSE QuietComfort25BOSE QuietComfort25 の周波数特性(FLATSWEEP016384で測定)
400 Hz 矩形波の再生波形 今回買った BOSE QuietComfort25 は、iPhone・iPod・iPad 対応リモコン・マイク付きで、入力プラグがφ3.5 mm の 4 極ミニプラグとなっていた。ステレオ用ミニプラグが 3 極なので変換コネクタを購入したが必要はなかった。このタイプ(CTIA 規格準拠)は直接ステレオ用 3 極端子に入れても使えるようだ。
![]() 2015-08-01(土) SR-009 の矩形波再生波形
2015-08-01(土) SR-009 の矩形波再生波形
400 Hz の矩形波を SR-009 で再生したときの波形を見てみた。以前にも同様の波形を調べたことがあるが、今回はイコライザーの効果を確認した。
下図の上がイコライザーなし、下が 1.2 kHz を 3 dB 下げた時の波形。どちらも波形がかなり歪んでいるが、イコライザーをかけた方が立ち上がり部分の山が少し下がって平坦相当部分がより直線に近づいている。これが聴感上で癖が減った要因と思われる。
この波形を見ると、まだまだ調整の余地がありそうだ。
400 Hz の矩形波を SR-009 で再生したときの波形(foobar2000、DA-300USB、SRM-323S、XCM6035-2022-354PR使用)
上はイコライザーなし、下は 1.2 kHz を 3 dB 下げた時の波形で、イコライザーをかけた方が立ち上がり部分の山が下がり平坦相当部分がより直線に近づいている。
![]() 2015-07-28(火) 矩形波を入れたらアンプの差が出た
2015-07-28(火) 矩形波を入れたらアンプの差が出た
周波数特性の測定ではドライブアンプの差が出なかったので、今度は矩形波を入力して出力波形を比較してみた。
その結果、下図のようにアンプの差が出た。
入力波形(1,000 Hz 矩形波)
SRM-323S の出力波形
(SR-009 接続時)SRM-007tA の出力波形
(SR-009 接続時)両ドライブアンプの出力波形を見ると、SRM-323S は多少オーバーシュート気味だが入力波形に近いのに対して、SRM-007tA は立ち上がり部分の角が取れて丸くなっていた。よく見るとこの部分には 10 kHz 位に相当するリンギングもある。
これらの波形から SRM-323S は鋭い音、SRM-007tA は丸い音となる事が予想され、実際に聴いたときの感じに合っている。
最初(2014-08-16)に両アンプの音を聞いたときの印象『SRM-323S は優等生の音、SRM-007tA は少し癖のある音』というのがこの波形に如実に現れている。 SRM-007tA で聴くと歪が大きく感じるのはこの立ち上がり部分のレスポンスの悪さが原因と思われる。なお、この結果は周波数特性から推定される波形とは逆の傾向なのでどうしてこうなるのか不思議だ。 真空管の特性だと思われるが、周波数特性は定常時の振幅だけを見ていて各周波数の位相情報が抜けているので、このような結果になるのかも知れない。
音の傾向を観る場合には矩形波で比較した方が良いような気がしてきた。
【雑 感】
STAX のイヤースピーカー SR-009 も 1 年間使用してやっと音が落ち着いてきた感じがする。今の手持ち機器では USB-DAC に DA-300USB、ドライブアンプに SRM-323S を使い、ソフトウェアイコライザーで 1.2 kHz と 1.7 kHz を数 dB 下げて再生するのがベストのようだ。真空管アンプはどうも肌に合わない。
SR-009 はディテールが良く聞こえるので録音の失敗まで分かってしまう。その観点から言えばハイレゾブームの効果か 最近の CD は質が良くなってきた感じがする。 2012 年頃の録音に比べて 2014 年以降の録音は音割れする曲が確実に減っている。 コンプレッサーの使い方が巧くなっているようだ。
![]() 2015-07-27(月) STAX ドライブアンプの特性
2015-07-27(月) STAX ドライブアンプの特性
現在使っている STAX のドライブアンプ 2 台の周波数特性を比較してみた。
SRM-007tA を基準とした SRM-323S の GAIN 差は下図の通りで、80 kHz まで 1 dB 以内に入っている。仕様では SRM-007tA の周波数特性は DC 〜100 kHz/+0,−3 dB、SRM-323S は DC 〜60 kHz/+0,−3 dB となっている。
SRM-007tA の周波数特性が仕様通りだとすると現在使っている SRM-323S の高域特性は 80 kHz 以上まで延びている事になり STAX の仕様は保証値のように思われる。
測定結果では両ドライブの可聴範囲での特性差は ±0.1 dB 以内で殆ど差はなかった。しかし実際に音を聴くと違うので周波数特性以外の別の要因が音に影響しているようだ。可能性としては、真空管特有の応答特性が考えられる。
STAX ドライブアンプの周波数特性比較(SRM-007tA を基準とした GAIN 差、Pro バイアスコネクターの3 番ピン(L+)と 4 番ピン(L−)間の交流電圧を sanwa PC700 で測定(測定時の 1,000 Hz の電圧は約 6 V ))
可聴範囲内では両ドライブの周波数特性に差はなかった。
![]() 2015-07-26(日) Hi-Res と CD
の比較
2015-07-26(日) Hi-Res と CD
の比較
【岩崎宏美 Life】
この Hi-Res 版は CD マスターを K2HD プロセッシング処理した 96 kHz/24 bit 音源だが、なぜか 22 kHz 以上の音は入っていなかった(正確には−100 dB 程度の信号は記録されているが、アナログアンプのノイズに埋もれてしまうレベルで、とても失われた倍音を復元したとは言えない)。
Sound Forge Audio Studio でデータを比較したところ、 Hi-Res 版は CD 版に比べてピークが 0.3 dB 下がっているのに平均 RMS は逆に 1.7 dB 上がっていた。
どうもピークに近いところでコンプレッションをかけているようだ。この Hi-Res 版のスペクトルは見た目では CD 版と大差ない。聞き比べると最初は Hi-Res 版の方が音が良いような印象を受けたが、これは録音レベルが違うためで、レベルを合わせると差はなかった。
この曲は CD でも十分な音質レベルをキープしている。因みに、この曲に限らずビクターの録音は総じて質が高い感じがする。
【平原綾香 My Sailing】
こちらはミックスマスターからリマスタリングしただけあって、 Hi-Res 版は 30 kHz までの音が収録されていた。
スペクトルを比較すると、 Hi-Res 版は超低域と超高域が上がっている。
ピークは大差ないが、 RMS レベルは Hi-Res 化で 0.8 dB 下がっている。リマスタリングでダイナミックレンジを拡げたようだ。ただヘッドホン(SR-009)で聴いても通常の音量ではこの差は分からない。
【ダイナミックレンジはどの程度必要か】
最大音量を 0 dB として音量を下げて行った時、どこまで音が聞こえるかを 1,000 Hz のサイン波で試してみた。
結果、通常の音量なら−60 dB で、少し大きな音でも−70 dB で音が聞こえなくなる。と言うことは、ダイナミックレンジとしては、CD のビット深度 16 ビット(90.3 dB)で十分なようだ。
![]() 2015-07-24(金) SR-009 の周波数特性(低音側)
2015-07-24(金) SR-009 の周波数特性(低音側)
前回は簡便にホワイトノイズを使って周波数特性を測定したため、100 Hz 以下のデータがとれなかった。
今回はサイン波のスイープで各周波数のパワー密度を上げて測定した結果、100 Hz 以下のデータを取得することができた。 ただレベルを上げたためか、測定時の音は若干歪んでいるように感じた。因みに、WaveSpectra に表示された THD は、50 Hz で 0.3 %、1 kHz で 0.2 % だった。 マイク(XCM6035-2022-354PR)の特性もあるので、GX-70HD2 の音を測定してみたら、1 kHz の歪はウーハーが 0.1 %、ツイーターが 0.3 % だった。似たようなレベルなので SR-009 の歪が特に異常な数値ではないと思われる(以前の EMM-6 を使ったGX-70HD2 の測定結果より低い)。
周波数特性の測定結果(下図)を見ると、60 Hz 辺りをピークとする数 dB のなだからな山があった。 増加レベルとしては 1.2 kHz の山よりも低い。また、計測時にピークレベルメーターを見ていると測定開始時の 10 Hz でも確実に音が出ていた。
なお、今回も 3 kHz 以上のデータは装着の度に変わったので下図もこの部分はイコライザー用のデータとしては使えない。
サイン波スイープで測定した SR-009(左側)の周波数特性(10 〜20,000 Hz を 180 秒で Log スイープ、マイクは ECM 素子(XCM6035-2022-354PR)、装着して測定)
低音側では 60 Hz 辺りをピークとする数 dB のなだからな山があった。
![]() 2015-07-22(水) SR-009 の周波数特性
2015-07-22(水) SR-009 の周波数特性
この前買った ECM 素子を使って SR-009 の特性を再測定してみた。
マイクの位置を変えて測定すると、下図のように場所により 3 kHz 以上のパターンが大きく変わった。全体としては 50 Hz 〜1 kHz 辺りまではフラットでその上は減衰傾向となっている。
また、測定時の波形を観察すると、50 Hz 以下の部分は外部の騒音ではなく、装着時の脈の振動を拾っていることが分かった。 したがって、この部分は SR-009 の特性が測定できていない。この部分の特性はマイク位置の影響を受けないようなので装着しないで測定した方が良さそうだ。
マイク位置による SR-009 の周波数特性の違い 左上の図:前側(赤色)と中央(青色)の比較
左下の図:後側(赤色)と中央(青色)の比較
右上の図:上側(赤色)と中央(青色)の比較
右下の図:下側(赤色)と中央(青色)の比較3 kHz 以上ではマイクの位置によりパターンが大きく変わる。
上記の全 5 点を平均すると、下図のようになった。
100 Hz 〜1 kHz 辺りまではフラット(100 Hz 以下のデータは精度が低い)。
1.2 kHz に山があり、そこから上の周波数は低下傾向。ただし、その低下も 20 kHz で 10 dB 位だった。 10 kHz 以上はマイク(ECM)の特性が下がっているので、実際には図ほどは下がっていないと予想される。
![]() 2015-07-21(火) ECM 素子を試してみる
2015-07-21(火) ECM 素子を試してみる
超音波用シリコンマイクは低域の特性が悪かったので、エレクトレットコンデンサーマイク(ECM)素子を買ってみた。
今回買ったのは、WM-61A 相当の SPL (Hong Kong) Limited 製エレクトレットコンデンサーマイク素子で、リードピン付の XCM6035-2022-354PR とリードピンなしの XCM6035-2022-354R の2 種類。どちらも秋月電子通商で 1 個 50 円だった。念のために複数個買った。特性を測定してみたら、リードピンなしはなぜかノイズに弱かった。リードピン付の特性は下図の通りで、低域の特性はシリコンマイクよりも良くなっている。ただし、10 kHz 以上は減衰が大きくこちらはあまり良くなかった。製品のデータシートでは 10 kHz から上は上昇傾向にあるので全く違う結果となっている。因みにリードピンなしも同様の傾向だった。まあ、10 〜 12,000 Hz の範囲では±3 dB に入っているようなので、通常の測定には使えそうだ。
この測定結果のグラフを見て気がついたのは、EMM-6 のキャリブレーション・データシートには 300 〜400 Hz に山があるが、今回の結果ではその山(相対比較なので谷になる筈)が出ていない。と言うことは EMM-6 のデータが間違っている可能性が高い。やはりキャリブレーション・データシートで気になっていた日付 21.11.01 が関係しているのか?
このレベルになると何が正しいのか、多数のデータを取得してみないと分からないようだ。この前測定した超音波シリコンマイクの特性は EMM-6 の特性で補正したが、補正しない方が良かったようだ(今回は補正していない)。
<2015-07-22 追記>
超音波シリコンマイクの特性を EMM-6 の特性で補正しない場合のデータは下図で、こちらの方が素直な特性だ。これを見るとやはり EMM-6 のキャリブレーション・データが間違っている感じがする。
![]() 2015-07-19(日) 260 Hz にディップがあった
2015-07-19(日) 260 Hz にディップがあった
通常聴く位置でスピーカー(GX-70HD2)から出た音の周波数分布を測定したら、スピーカーそのものの特性とはかなり違ったパターンとなっていた。 恐らく左右のスピーカーから出る音波の干渉がピークとディップを作っているのだろう。
高域はバラツキが大きく補正ができないので、低域だけを補正してみた。そのパライコの設定は下図のようになった。 因みに下図にない 140 Hz と 170 Hz の バンド幅(Q)は 5。
今回の補正の中で予想外に効果があったのは 260 Hz のディップで、この部分を Q = 15 で 8 dB 上げたらこれまで痩せていた女性ボーカルの声が芯のある自然な声に近づいた。
この 260 Hz の音の波長は計算上 134 cm(27℃)で、その半波長は 67 cm となる。現在、左右のスピーカー間距離は 68 cm なのでこれに起因していると思われる。 通常の干渉は聴く場所によって音の大きさが変わるが、このディップは場所によらず常に減衰したままだ。 と言うことはどんなスピーカーでもパライコによる補正が有効かも知れない。
なお、このディップ周波数は室温の影響を受けるようだ。
![]() 2015-07-15(水) スピーカーのパライコ再々設定
2015-07-15(水) スピーカーのパライコ再々設定
2015-07-13(月)の設定は音を聴いてみたら失敗だった。 どうもマイクを固定して測定したのが敗因だったようだ。 マイクを動かしながら補正後の特性を測定してみたら凸凹が巧く消えていなかった。
再度スピーカーの特性を測定し、その特性と反対になるようにイコライザーを設定したら下表のようになった。 この設定で試聴したら以前のように音が改善された。
JRMC パライコの設定(GX-70HD2)
周波数 (Hz) バンド幅 (Q) ゲイン (dB) チャンネル 180 1 −4 左; 右 1,100 2 4 左 1,200 10 −6 左 1,520 50 6 左 1,650 10 −4 左 600 2 5 右 960 20 6 右 1,040 20 −6 右 2,800 5 6 右 3,800 3 3 右 設定数は前回よりも減っているが音質は良くなっている。特性がフラットになると音がきれいになって歪み感が減る事を実感できる。
![]() 2015-07-14(火) SR-009 のイコライジング
2015-07-14(火) SR-009 のイコライジング
SR-009 の周波数特性を測定しようと色々試みたが再現性が悪い。 特に 3 kHz 以上のピークやディップは装着状態でコロコロ変わる。 元々 STAX のイヤースピーカーは手を近づけるだけで音が変わるくらい外部の影響に敏感で安定した測定が難しい。 ヘッドホンに手を近づけると 2 〜 4 kHz あたりの音が強調されてキンキンした音になる。 装着の仕方でこの辺りから上の周波数の特性が変化するようだ。ウェブサイトにあるデータがばらついているのも、これが原因だろう。結局これ以上の周波数についてはイコライザーによる補正には無理があると判断して止めることにした。
特性が安定していて確実に効果のある 1 〜 2 kHz の補正だけが無難なようだ。 これだとわざわざ JRMC のパラメトリックイコライザーを使わなくても foobar2000 のグラフィックイコライザーで十分補正できる。 その設定は下図のような簡単なものになった。これだけでも十分効果はある。
この設定で測定した SR-009 の周波数特性は下図で、4 kHz 辺りまではフラットに近くなった。 グラフの 60 Hz 以下は外部の騒音だが、なぜか SR-009 は装着するとこの部分を増幅させるようだ。
foobar2000 のイコライザーで補正した SR-009 の周波数特性(装着状態で超音波シリコンマイクで測定)
60 Hz 以下は外部の騒音。今回使用した超音波シリコンマイクの特性は下図のように 150 Hz 以下は感度が低下しているので、上図の 150 Hz 以下はもっとレベルが高い。
超音波シリコンマイク(SPM0404UD5)の感度特性 秋月電子通商で販売しているシリコンマイクのデータシートを見ると、超音波用ではない普通のシリコンマイクでも特性は変わらないようだ。
一応、上の設定で SR-009 の癖はかなり軽減されるが、より自然に聞こえる設定は下図のようになる。
・ 1 〜 2 kHz を 3 dB 下げて SR-009 の中域の癖を減らす。
・ 3 〜 5 kHz を少し下げてシャリシャリ感を抑える。これでスピーカー用のプレーヤーは JRMC 、イヤースピーカー(SR-009)用は foobar2000 と使い分けができそうだ。 SR-009 の場合は AudioGate + US-366 のイコライザーと言う選択肢もある。
![]() 2015-07-13(月) スピーカーのパライコ再設定
2015-07-13(月) スピーカーのパライコ再設定
オンキヨーのスピーカーシステム GX-70HD2 の振動が下に伝わっているような感じがしたので、標準で付いてきたコルクシートの下にブチルゴム製スペーサー入れてみた。 何となく振動が減ったような感じがするので、パライコの設定を再調整した。
パライコの調整も大分慣れてきたので、それ程時間はかからなかった。 以前よりも設定数が減ったので、ブチルゴム製スペーサーの効果があったのかも知れない。
JRMC パライコの設定(GX-70HD2)
周波数 (Hz) バンド幅 (Q) ゲイン (dB) チャンネル 150 1 −1 左 1,200 10 −9 左 1,400 10 −6 左 1,500 0.5 4 左 1,520 20 6 左 1,650 10 −10 左 220 10 −5 右 600 2 6 右 750 2 −3 右 1,100 3 −2 右 1,330 2 3 右 1,440 30 6 右 2,800 3 8 右 3,800 3 5 右
設定後スピーカーを正面向きから少し内向きしたら定位が向上した。
ReplayGain を使ってデジタルでボリュームを絞ると音が細くなる。何度聞いても結果は同じなのでアナログ部分の微小信号の性能に問題があるのだろうか。デジタル部分は 32 ビット(ないしは 64 ビット)に拡張して処理しているので問題はないはずだ。
![]() 2015-07-09(木) 聴感で SR-009 の周波数特性を補正
2015-07-09(木) 聴感で SR-009 の周波数特性を補正
マイクによる SR-009 の周波数特性測定が難しいので、聴感(耳で聴いた感じ。用語として正しいかは疑問)で特性を推測し、それを基に JRMC のパラメトリックイコライザー(パライコ)で特性がフラットになるように調整してみた。
SR-009 の周波数特性はヘッドバンドやドライバーの位置(上下と前後)で微妙に変化するので、装着感の良い場所を捜して再測定した。
その結果が下図で、音圧のピークは以前よりも高い方に移動した。これに基づいて補正したパライコの設定は下表のようになっている。周波数とバンド幅はロバスト性を考慮して選定している。この補正で前回よりも好みの音に近づいた。この補正をするだけで SR-009 の音が格段に良くなる。JRMC のパライコは良く出来ている。
今回の補正で SR-009 もやっと合格レベルに達した。30 Hz の補正は好みで、クラシックの場合はコントラバスの響きや臨場感・雰囲気の再現から ON にした方が良いが、 POPS 系の曲は録音によっては聞き疲れするので OFF にした方が良さそうだ。
JRMC パライコの設定(SR-009)
周波数 (Hz) バンド幅 (Q) ゲイン (dB) チャンネル 30 1 3 左; 右 1,500 1 −4 左; 右 2,500 4 6 左; 右 4,500 4 2 左; 右 7,000 3 −5 左; 右 8,300 4 6 左; 右
SR-009 の特性(耳で聴いた感じ) 装着状態でピーク周波数やディップの深さなどが変わる
![]() 2015-07-08(水) 電話用マイクの周波数特性
2015-07-08(水) 電話用マイクの周波数特性
電話用マイク ECM-TL3 の前回の周波数特性測定は WaveSpectra の画面からラフにデータを読み取ってグラフ化したためあまり正確ではなかった。
今回は WaveSpectra の Overlay 機能を使って特性をもう少し正確に分析してみた。【今回の測定方法】
・スピーカーで FLATSWEEP 波を再生
・ECM-TL3 と EMM-6 を並べて同時録音
・WaveSpectra で録音データを読み込み再生分析
・WaveSpectra の Overlay 機能で周波数データを保存
・データを EXCEL に取り込みマイクの特性差をプロット【結 果】
ECM-TL3 の特性は前回よりも変動幅が大きく、測定用としては全く使えないレベルにある事が分かった。
また、追加で購入したオーディオテクニカの AT9905 も同様の方法で測定してみた。 電話用マイク 2 つを比較すると AT9905 の方が変動幅が少なく特性は良いが、それでも±10 dB 程度の変動があるので 数 dB の補正をするための測定用としてはこちらも使えないレベルだった。
なお、どちらのマイクも装着するとピーク周波数が下がる傾向にあり、装着状態が測定結果に影響することも分かった(下図は装着時の測定結果)。
SR-009 も装着方法で音が変わるのでヘッドホンの特性測定は難しい。かと言って人口耳は実環境を模擬しているとは思えないので、結局は通常聴く状態での聴感が一番正しそうだ。
電話用マイクの周波数特性 電話用マイクは周波数特性が悪いので測定には使えない
![]() 2015-07-06(月) パライコで SR-009 も更に音が良くなる
2015-07-06(月) パライコで SR-009 も更に音が良くなる
電話用マイクによる SR-009 の周波数特性の測定結果にマイクの特性を考慮してJRMC のパラメトリックイコライザー(パライコ)を設定してみた。
その後、試聴で微調整した結果が下表となっている。まだ調整中だが、パライコで確実に音が良くなっている。まず、変なピークが減ったことでボーカルの声が素直になった。この効果もあってか音割れ感が少し減った。全体的にはバランスの良い YAMAHA の音に近づいた感じだ。
JRMC パライコの設定(SR-009用)
周波数 (Hz) 1,200 2,800 5,000 8,000 バンド幅 (Q) 1.5 1.5 1.5 2 ゲイン (dB) −4 +5 −5 +5 チャンネル 左; 右 左; 右 左; 右 左; 右
パライコでゲインを上げた事が原因で波形がクリップしないようにイコライザーの Pre AMP を−5 dB にして全体のゲインを下げている。
このパライコを細かく調整すればかなり理想に近い音を出せそうだ。
Pure AQUAPLUS LEGEND OF ACOUSTICS
Suara の声もだいぶ生々しくなってきた
BENI COVERS:3
音割れ感が少し減った
![]() 2015-07-05(日) 電話用マイクは周波数特性が悪い
2015-07-05(日) 電話用マイクは周波数特性が悪い
この前の電話用マイク(SONYのECM-TL3)を使った SR-009 の周波数特性を基にパラメトリックイコライザーで補正を試みてみたが、なぜか音が改善しなかった。聴感では 5 kHz のピークが実際よりも高く評価されているような気がしたので、電話用マイクの周波数特性を測ってみた。念のためマイクロホンアンプ(オーディオテクニカの AT-MA2)も購入して使用した。
EMM-6 との比較測定はかなり難しかった。結果は下図の通りで、6 kHz あたりをピークとする 10 dB 以上の山があり超音波用シリコンマイク(SPM0404UD5)よりも特性が悪かった。
このグラフを見ると前回測定した結果では巧く補正出来なくて当然だった。この電話用マイクは測定には向いていないので、もっと特性の良いマイクが必要だ。
電話用マイク(ECM-TL3)の周波数特性
FLATSWEEP016384 で測定
6 kHz あたりをピークとする 10 dB 以上の山がある
測定用に購入したマイクロホンアンプ(AT-MA2)とその周波数特性
AT-MA2 の周波数特性はフラット(30 〜 30,000 Hz まで ±1 dB 以内)
![]() 2015-07-03(金) 電話用マイクで SR-009 の特性を測定
2015-07-03(金) 電話用マイクで SR-009 の特性を測定
STAX のイヤースピーカー SR-009 の特性を電話用マイク(SONY のエレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-TL3)を使って測定してみた。
【結 論】
これまでと違って今回の周波数特性測定結果は聴感と良く合っていた。この方法は使えそうだ。
【測定方法】
- 電話用マイク ECM-TL3 を耳に装着、その上から SR-009 を装着。
- ECM-TL3(プラグインパワー型)のミニプラグを SUMI2013 のマイク入力端子(プラグインパワー対応)に接続。
- WaveGene を使い 44.1 kHz, 24-bit で 10.766 〜 20,000 Hz を180秒でスイープ。
- WaveSpecra でピークレベルを記録。
- DAC は US-366 、ドライブアンプは SRM-323S。
【結 果】
まず、本来の使い方であるすき間なしの結果は下図で、1 kHz 以下はかなりフラットだった。1.2 kHz と 5 kHz に山があり、2.5 kHz と 9 kHz 辺りに谷があった。これは聴感と一致している。超高音域は下がっていた。
すき間なしの時の特性 次にビニタイでハウジングの動きを制限してイヤーパッドの下の方に僅かなすき間を作ると、下図のように 80 Hz 辺りにピークができ、50 Hz 以下は減衰した。これも聴感と合っている。
また、このすき間を作った場合には、全体的に鋭いピークが減り、加えて 6 kHz 以上が持ち上がって高域の特性がフラットに近くなった。これが音が綺麗に聞こえる要因かも知れない。すき間を作った時の特性 本来測定時間として 12 分必要なところを 3 分で測定したため 11 kHz 付近にデータの欠損が出てしまった。
SR-009 は装着方法で大きく周波数特性が変わるようだ。
どちらが良いかは好みの問題だが、少なくとも音が綺麗に聞こえるのはすき間ありの方だ。これらの結果を基にパラメトリックイコライザーでピークを補正すると更に良い音になるかも知れない。
注)使用したマイク(ECM-TL3)の周波数特性は 20 〜 20,000 Hz でSUMI2013 のマイク入力部の特性もそれ程良くはないので、上図間の比較は出来るがスペクトルの絶対値は正しくない。因みに、SUMI2013 のマイク入力部の特性は下図のように高域が持ち上がっている。
SUMI2013 のマイク入力部の特性 SUMI2013 のマイク入力は自動音量調節が働いているらしい。今回の測定は誤差が大きいのでフラットスイープで再測定した方が良さそうだ。
|
|
![]()
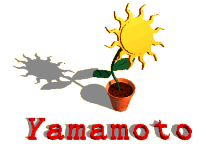
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る