| <<What's New>> ハムとパソコン、PCオーディオ奮闘記 2016年前半 |
|
|
![]()
![]() 2016-05-31(火) Windows 10 にアップグレード
2016-05-31(火) Windows 10 にアップグレード
3 台ある PC を全て Windows 10 にしてみた。
SUMI2009 (DELL) : Windows 7 → Windows 10
SUMI2013 (HP) : Windows 8.1 → Windows 10
LIVA X2 (ECS) : 元々 Windows 10
JRMC などいくつか動かなくなったソフトもあったが、再インストールすると解決した。予想に反して Adobe PageMill は Windows 10 でも動作した。ソフトを入れている SUMI2009 が 32 ビット版なのでこれが良かったようだ。
前回不安定になった SUMI2013 の FT-991 用 USB ドライバーも今のところは安定動作しているので、Windows 10 も完成度が上がったようだ。
![]() 2016-05-26(木) OpenDRC-DI
で 192 kHz 音源が再生できた
2016-05-26(木) OpenDRC-DI
で 192 kHz 音源が再生できた
デジタルオーディオプロセッサー OpenDRC-DI は導入当初 入力のサンプリング周波数は 96 kHz までしか受け付けなかったが、何故か現在は 192 kHz の音源が再生できている。TASCAM の US-366 panel でも 192 kHz/24 bits と表示されているので間違いないだろう。
機器構成は、2016-05-22(日)と同じで、再生ソフトは foobar2000。
LIVA PC (USB) → US-366 (Coaxial) → OpenDRC-DI (Optical) → DA-300USB (RCA) → SA-50 → ZENSOR1
US-366 の出力設定は デジタル出力でコンピュータを選択している。
どうも音飛びがなくなった頃から再生可能になっていたようだ。foobar2000 の Output Device は ASIO : US-366 となっており、このドライバーがポイントと思われる。以前 192 kHz を再生できなかった時の接続は光で、ドライバーは MS-Windows のDigital Output (S/PDIF)/ (IDT High Definition Audio CODEC) だった。元々 OpenDRC-DI の仕様書には入力周波数が 20-216 kHz と書かれているので 192 kHz を再生できないのがおかしかった。
これで入力が 192 kHz 対応にはなったものの出力は相変わらず 48 kHz のままだ。でも一応ハイレゾかな?
![]() 2016-05-25(水) アンテナの性能が良くなった
2016-05-25(水) アンテナの性能が良くなった
7 MHz で FT-991 のスペクトルを見ていると心なしかノイズが減った感じがする。
正確ではないが、SG7500 のグランドループ回避やアンテナ位置の移動など対策前はノイズレベルが 1.8(フルスケールは 4.0)位だったものが、今は 1.5 位に下がっている。 FT-991 のスペクトル表示は S0 で 1.0 位、S9 で 2.0 位なので、ノイズレベルの差 0.3 は S では 2.7 相当、すなわち 8 dB 程度の改善と思われる。数値だけを見ると大きな効果だ。スペクトルのピークも少し上がった感じになるので見やすくなった。試しに藤岡市の 7M4ALV 局と交信してみたら RS 59+を頂いたので飛びも良くなっているかもしれない。
![]() 2016-05-24(火) SG7500
をアースから浮かした
2016-05-24(火) SG7500
をアースから浮かした
現在ベランダには 3 本のアンテナがあり、各アンテナの用途とアースの状況は下表のようになっている。
現在使っているアンテナ 3 本のアースの状況
No. 外 観 使用バンドと種類 アースの状況 1. V/UHF(144/430 MHz)
モービル用ノンラジアル型ホイップアンテナ(SG7500)
不要だが、金具が手すり支柱に接触 2. HF+ V/UHF(7〜430 MHz)
モービル用ホイップ型オートチューニングアンテナ(ATAS-120A)
手すり支柱に容量結合 3. HF(7〜50 MHz)
ロングワイヤーアンテナ
+
オートアンテナチューナユニット(FC-40)手すり支柱に容量結合 これらのアンテナは全て FT-991 に同軸ケーブル(5D-2V)で接続されている。これらのケーブルには全て両端にクランプ式のフェライトコアを付けているが、FT-991 でアースが全て繋がってしまっている。これがアンテナ側でも接地が繋がっている場合にはグランドループができてしまいそれぞれのケーブルに入れたフェライトコアのコモンモード除去がキャンセルされてしまう事がある。このためグランドループができないような接続が望ましい。
上の表にあるアンテナの内、 2. と 3. は接地タイプでベランダの手すりをアースとしているので仕方ないが、1. は本来接地は不要だ。ところがベランダ取り付け金具 BK10 は M 型レセプタを直付けする構造となっており金具が接触している手すり支柱にアースが電気的に繋がっていた。
この電気的な接触を避けるために BK10 と支柱との間に厚さ 1 mm のシリコーンシートを 2 枚重ねて挟み込んだ。これで少なくとも DC 的にはテスターでは計れない程度の絶縁状態となった。これが効果があるのかは検証はしていないが、少なくとも悪くはなっていないだろう。
更にとりあえず FC-40 と ATAS-120A の同軸ケーブル(5D-2V)2 本を #61 のトロイダルコアに通した。このトロイダルコアは後で FT-991 の出口にケーブルを巻いたフィルターとして利用する予定。
![]() 2016-05-23(月) LW
アンテナが少し飛ぶようになった
2016-05-23(月) LW
アンテナが少し飛ぶようになった
以前から Reverse Beacon Network を利用して電波の飛びを確認している。今回もこれを利用して LW(Long Wire)アンテナに対する ATAS-120A(モービルホイップアンテナ)の干渉度合いを調べた。
CW のテスト送信周波数は 7,030 kHz 付近で、CQ を出して Reverse Beacon Network に表示される信号強度(S/N)を確認した。
LW アンテナ 7 MHz の飛び比較テスト
ATAS-120A の
同調周波数LW (FC-40) の
送信周波数JF2IWL 局
受信 S/N7 MHz 7 MHz 14 dB 14 MHz 7 MHz 29 dB 測定は 1 回なので数値の精度は低いが、ATAS-120A の同調周波数が送信周波数と同じ時には S/N が 15 dB 低くなっている。これは大きな数値で、電力では 10 倍以上の差がある。ATAS-120A があると外に飛んで行く電波は 10 % 以下になっていたようだ。これでは飛ばない訳だ。
この結果を基に再調整して SSB で九州の局を呼んでみたら一発で応答があった。リポートは相手が 59 でこちらが 57 なのでまだ弱いが、以前のように呼んでも応答がない状況は脱したようだ。LW アンテナが少し飛ぶようになったのは、エレメントを壁面ギリギリまで押し出したことに加え ATAS-120A の干渉を避けたことが大きく効いている。LW の近くに同じ周波数に同調した ATAS-120A があると LW の SWR が下がるが飛びが悪くなってしまう。ベランダ内アンテナの SWR 値 は飛びに関してはあまり意味を持たないようだ。
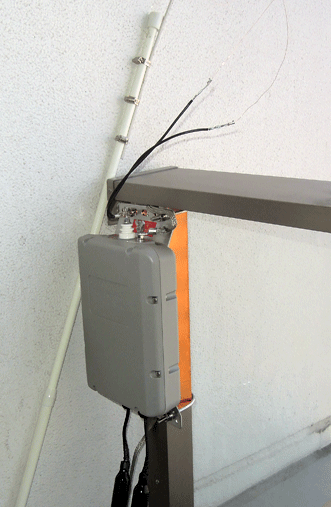
ベランダに設置した LW 用 FC-40 と ATAS-120A
![]() 2016-05-22(日) LIVA
でも音飛びしなくなった
2016-05-22(日) LIVA
でも音飛びしなくなった
夜中に音楽を聴いていたら SUMI2013の 冷却ファンの音が気になったので、以前音飛びしたために使っていなかった LIVA で試しに音楽を再生してみたら何故か音飛びしなくなっていた。CPU 負荷が 100 % でも音飛びしない。プレーヤーは foobar2000 で、音も SUMI2013 と変わらない。
この時の機器接続は、LIVA PC (USB) → US-366 (Coaxial) → OpenDRC-DI (Optical) → DA-300USB (RCA) → SA-50 → ZENSOR1
以前と変わった所と言えば、USB 接続の機器数が減っている事で、今回 LIVA に接続されている機器は、無線マウスと US-366 だけとなっている(キーボードはブルートゥース)。DA-300USB や OpenDRC-DI は音楽を聞く時にはコントロールする必要はないので USB は SUMI2013 に接続したままだった。とすると、DA-300USB のドライバーが US-366 のドライバーと干渉していた可能性がある。検証はしていないが今は音飛びしないので無理に実験する必要はないだろう。接続を変えた時に不具合が出たら原因が特定できる。
これでまた無音PCで静かに音楽が聞ける。
これとは別だが、US-366 と OpenDRC-DI を同軸ケーブルで接続した時に新しい発見をした。これまで PC から USB で音楽データを送った時にはマイクからの入力もミックスされてデジタル出力されるものと思っていたが実はそうではなかった。
デジタル出力(光ないしは同軸)もアナログ出力(サウンドの録音タブにあるライン入力)もコンピュータ出力かミックス出力かを US-366 のコントロールパネル(インタフェースのタブ)で選択できるようになっていた。
デジタル出力をコンピュータ出力に、アナログ出力をミックス出力にして、ミキサーでコンピュータ出力を Mute にしておけば、コンピュータ出力はアナログ側に出力されないことが分かった。と言う事はルーム補正のためにわざわざ UMM-6 を買う必要はなかったようだ。
US-366 の機能も使いこなしていなかった。
![]() 2016-05-21(土) 八丈島と交信できた
2016-05-21(土) 八丈島と交信できた
これまでベランダ内に張った LW アンテナでは八丈島移動運用メンバーとは交信できなかった。アンテナのエレメントがベランダの中なのでローバンドほど飛びが悪い。
そこで LW のエレメントを壁面ギリギリまで前に出してみた。
その甲斐あってか、5/21(土)午後 8 時過ぎに八丈島で移動運用している JH1LMD/1 局と交信ができた。JH1LMD 局の今回の移動運用は CW がメインなので、インターネットで Reverse Beacon Network を監視していたら、7,011.5 kHz の CW で CQ を出しているのを見つけた。早速 FT-991 でその周波数をウォッチしてみたら、59 で入感していた。前の交信が終わり CQ を出していたので呼んでみた。こちらの信号が弱いためか /1 ? と聞かれたので、JA8EZL/1 を送るとリターンコールがあった。EZLに気がついてくれたらしく名前まで返してくれた。
これでやっと八丈島との交信ができた。
Reverse Beacon Network のトップ画面 JH1LMD 局の受信データ(7 MHz でネバダ州まで届いている)
![]() 2016-05-19(木) HF
アンテナの干渉
2016-05-19(木) HF
アンテナの干渉
FT-991 の TUNER SELECT を INTERNAL にして FC-40 の TUNER 機能を OFFにした状態で LW(Long Wire)アンテナの同調周波数を探ってみた。
FT-991 を AM モードにして SWR 計を見ながら周波数を変えてみたら 7.145 MHz あたりが最小で 1.0 となった。LW のエレメント長は 10.5 m なので、計算長とピッタリ合っていたので最初はここに同調していると思った。
ところが、その後 7 MHz に同調させていた ATAS-120A の同調周波数を 50 MHz に変更したら LW の SWR が FC-40 なしでは 2.0 以下には下がらなくなってしまった。
ATAS-120A をベランダ取り付け金具から外しても結果は同じなので、どうも LW から出た電波が ATAS-120A に吸収されて見かけ上 SWR が良くなっていたらしい。ATAS-120A がないと LW の SWR 値が安定するのでやはり干渉していたようだ。垂直系と水平系でもアースが共通なので干渉するようだ。アンテナ切替器はアースが常に繋がった状態になるのでこれも干渉要因だ。そう言えば V/UHF のアンテナもアースが共通している。オーディオでは常に注意していたグランドループを無線ではすっかり忘れていた。フェライトコアのコモンモード除去もこれではキャンセルされてしまう。
少なくとも V/UHF アンテナの取り付け金具を電気的にはベランダ支柱から浮かした方が良いかな?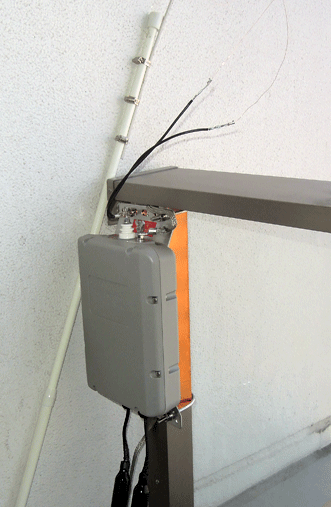
ベランダに設置した FC-40 と ATAS-120A今日は八丈島から JH1LMD 局の CW が 599 で聞こえていた。LW を使って何度もコールしたがパイルアップのため無理だった。やはり八丈島方面には飛んでいないようだ。ATAS-120A に切り替える時間はなかった。
![]() 2016-05-18(水) 八丈島の移動運用を聞いていた
2016-05-18(水) 八丈島の移動運用を聞いていた
ローカル各局が 5/17(火)から八丈島で移動運用をしている。最初に確認できたのは、5/17の 16:20 頃 7.135 MHz SSB で JH1LMD 局が大田区から J-クラスタへのアップの連絡をしていた。八丈島からは JE1GDY 局、JA1UTB/1 局、JH1AQG/1 局が出ていた。
連絡が終わったので呼んでみたら何故か SWR が異常に高かった。外を見たら何とアンテナのエレメントが切れて垂れ下がっていた。これまで何か月も問題なかったのにこの日に限ってタイミング悪く切れてしまった。直ぐに修理して Rig を立ち上げたが時既に遅し。J-クラスタに情報がアップされた後だったので、多数の局が JH1AQG/1 局を呼んでパイルアップ状態だった。何回か呼んでみたがベランダに張った LW では到底太刀打ちできずに諦めた。大田区の JI1ITB 局の交信は確認した。アンテナだけでなくベランダが西向きなので、指向性から考えて真南方向には飛びが悪い事も影響しているだろう。今考えると LW ではなく指向性のないホイップの ATAS-120A の方が良かったかも知れない。その後 3.5 MHz で運用すると言う情報があったので、翌日の午前 0 時までウォッチしていたがその日は聞こえなかった。
今日も朝から 7 MHz や 430 MHz をウォッチしているが何も聞こえてこない。よく考えるとここから八丈島までは 280 km あるので 800 m 級の山(八丈富士の標高は 854 m)では見通せない距離だった(計算上は 800 m の高さから見通せるのは 100 km 程度)。同じ東京でも八丈は遠い。
八丈島(観光協会のサイトより) 【22:00 追記】
21:30 になってようやく 3.559 MHz の SSB が入感した(今回の OP. は JH1HAB/1 局)。ただし、LW アンテナ・エレメントの向きが悪いせいか信号の了解度・強度は 48 だった。やはりベランダ内のアンテナでは HF は難しい。3.5 MHz のアンテナはないので当然交信はできなかった。
![]() 2016-05-17(火) 音楽を聴く環境が整った
2016-05-17(火) 音楽を聴く環境が整った
鮫島さんにルーム補正を紹介頂いてから 6 か月、やっとそれなりに音楽を聴ける環境が整った。
miniDSP 社のデジタルオーディオプロセッサ OpenDRC-DI を使って FIR フィルターで音響特性を補正するとスタジオに近い音を再現できることが分かった。それほど高級なスピーカーを使わなくても良い音がする。デジタル処理の威力が発揮されているようだ。
昔、誰かが良い再生装置は大きな音を出さなくても迫力があると言っていたが、正にそれが当たっている感じがする。ルーム補正で周波数特性だけでなく、定位も向上するので臨場感が出る。これを迫力と表現されたのだと思う。また、再生装置の能力はピアノの音で分かると言った人もいた。ピアノの音色だけではなくアタック感がその性能の指標とも解釈できる。その意味では、現在のシステムはかなりのレベルに達している。
音展やオーディオフェスティバルでこの音が聞けないのは、スピーカーからの距離が遠すぎて位相があわない(合わせていない)ためかも知れない。
miniDSP 社 OpenDRC-DI と DENON DA-300USB OpenDRC-DI のデジタル出力はサンプリングレートが 48 kHz だが、通常の使用では支障はない。逆に DA-300USB は 96 kHz の動作が不安定なのでこれでちょうど良い。
![]() 2016-05-16(月) ヘッドホンの周波数特性比較
2016-05-16(月) ヘッドホンの周波数特性比較
ヘッドホンの周波数特性測定用に簡易治具を作ったので、手元にあるヘッドホンの特性を測ってみた。
結果は下図の通りで全くパターンの違うことが分かった。このカーブを見るだけで各メーカーの音作りが見えてくる。
パターンを見た感想
STAX SR-009 フラットを目指したがハウジングの設計ミスで 6〜7 kHz に深いデップができてしまった。手作りのため左右の特性も違う。 SONY MDR-CD900ST ドンシャリに近い。10 kHzに異常なピークがある。仕様の再生周波数帯域:5〜30,000Hz や歪が少ないは実態と全く違う(どこかの自動車メーカー並)。 SENNHEISER HD598 特性は比較的無難で好みに近い。低域を少し下げればフラットになる。 DENON AH-D2000 中・高域が良く聞こえるように色づけしている。 BOSE QuietComfort25 低音重視(恐らくアンプでEQ)。3 kHzまでは変なピークはない。 ヘッドホンの周波数特性(マイク 2 個の信号を US-366 で合成) パターンからは SENNHEISER HD598 が良さそうだ。試しに PEQ で特性をフラットにしてみたが音は SR-009 には勝てなかった。それと HD598 はケーブルが硬いのでこすれ音がする。
![]() 2016-05-15(日) ヘッドホン特性の FIR による補正
2016-05-15(日) ヘッドホン特性の FIR による補正
ヘッドホン(SR-009)の特性を FIR で簡単に補正してみて効果のあることが分かった。そこでもう少し正確な補正をしようと REW で細かく PEQ データを作成してみたが限界があるため rePhase をマニュアルで調整してみた。
調整結果は下図の通りで、5 kHz 以下はほぼフラットな特性が得られた。6〜7 kHz にある深いディップは無理には補正しなかった。この補正によって 500 Hz の矩形波もこれまでにない良い波形が得られた。聴感上は音がごく自然に聞こえる。元々 SR-009 は自然な音がするという評判だが、この補正で全く癖のない音になる。試しに DR-40 で録音した音をこの設定で聞いてみると、ほぼ録音した時の音がそのまま聞こえる。原音再生の面でもかなりの効果があるようだ。ただし、左右で矩形波の再生波形が違うので、もう少し調整が必要。
マニュアル調整後の特性(図の上半分がヘッドホンの左側、下半分が右側の結果。各グラフは左から EQ 補正曲線、REW で測定した SPL 周波数特性、500 Hz 矩形波の再生波形)
この補正によりこれまで SR-009 の低音不足を補うためにハウジングにつけていたビニタイは不要になった。
![]() 2016-05-14(土) FIR
はヘッドホンにも有効
2016-05-14(土) FIR
はヘッドホンにも有効
OpenDRC-DI を使ってスピーカーの音響特性を補正したところ非常に良い結果が得られたので、これをヘッドホン(SR-009)にも適用してみた。
ヘッドホンの場合は特性の測定が安定しないので、今回は簡単な治具を作ってみた。写真のように厚さ 5 mm のシリコーンゴムシート(10 cm×10 cm)に直径 5 mm の穴を 2 個あけ、そこに特性が良いと言われているマイク素子(WM-61A)を 2 個入れた。測定時はヘッドホン台(STAX のドライブアンプ)とヘッドホンの間にこの治具を挟んでマイクの位置が常に一定になるように調整した。
IEC で規定されている人工耳とは形が違うが、シリコーンゴムは音響的には人体と似ているので、こちらの方が通常の聴取状態に近い特性が得られるような気がする。
WM-61A はプラグインパワー方式のマイク素子なので、AT-MA2 を利用した。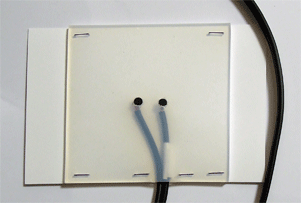
測定用マイクの簡易治具とそれを使った測定の様子 早速この治具を使ってヘッドホン(SR-009)の特性を測ってみた。数回試測定をした結果では再現性は非常に良かった。これまでの測定では良く分からなかったピークやディップが正確に把握できるようになった。左右の特性も違っており右の方が特性が良いことも分かった。
この結果を基に REW で PEQ データを作成し、それを rePhase に入れて FIR フィルターデータを作成、OpenDRC-DI に入れて補正してみた。
その結果は下図の通りで、上のグラフが SPL と位相特性、下のグラフが 500 Hz の矩形波を再生した時の波形となっている。図は左から順に補正前(左)、FIR でゲインだけを調整した結果(中央)、FIR で更に位相を調整した結果(右)となっている。説明するまでもなく補正によって特性が良くなっている。
SPL と位相の周波数特性
500 Hz の矩形波再生波形 今回は、GAIN 調整は Minimum phase ではなく位相の変わらない Linear phase を使ってみた。SPL 特性を良く見るとピークを抑制した周波数の上下が持ち上がっている。Linear phase で調整する場合にはどうも GAIN 設定で Q を 2 倍にする必要はないようだ。
補正は中途半端になってしまったが、これでも十分補正の効果が出ているので、FIR はヘッドホンにも有効な事を確認できた。
![]() 2016-05-10(火) FIR
の効果(矩形波)
2016-05-10(火) FIR
の効果(矩形波)
500 Hz の矩形波を使って FIR の位相補正による波形の変化を見てみた。
下図は左右両方のスピーカーに 500 Hz の矩形波信号を入れてリスニングポイントで測定した波形で、上が音響特性補正前、下が FIR による補正後だ。このように特性の補正で確実に波形が良くなっている。完璧ではないが、立ち上がり時の変なピークが消えて矩形波に近づいている。不要な付帯音が減って音が澄んで聞こえる。これがインパルスレスポンスの効果だろう。金属音がきれいに聞こえるのもこれが効いているのかも知れない。
GAIN だけで周波数特性を良くしても位相補正しなければ波形はそれ程変わらないので、位相補正は原音再生の観点からはかなりの効果があるようだ。
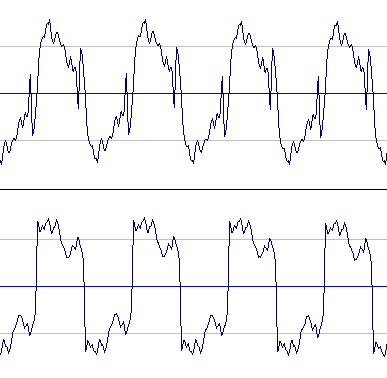
これで音響特性を補正 リスニングポイントで測定した 500 Hz 矩形波(上が FIR 補正前、下が補正後)
![]() 2016-05-08(日) やっとオーディオレベルになった
2016-05-08(日) やっとオーディオレベルになった
OpenDRC-DI の調整には随分時間がかかったが、試聴するとやっとオーディオレベルになったと言う感じだ。音質はもとより音像のクリアさが OpenDRC-DI なしと比べて数段向上した。位相補正による効果はインパルス性の音の鋭さに現れている。
現システムの音の評価は 87 点。矩形波から見た原音再生と言う点ではまだ 60 点位だが、音楽を聴く分にはまあ合格点だろう。
音展やオーディオフェスティバルではまだこのレベルの音を聴いた事はない。その意味でも FIR を使ったデジタル EQ の効果は大きい。
現在のシステム構成は、
Windows PC(光SPDIF)
→ デジタルオーディオプロセッサー OpenDRC-DI(光SPDIF)
→ DAC DA-300USB(RCAアンバランス)
→ 50 W デジタルアンプ SA-50(SP ケーブル 1 m)
→ スピーカー ZENSOR1(壁掛け、SP センター間距離 74 cm)このような簡易システムで高級機を上回る音が出ている。
ただし、FIR フィルターを使うためには音響特性の測定や EQ 作成が必要なので、ハードとして音響測定用マイクとそれを PC に取り込むインターフェースが必要だ。
現在メインで使っているものは、
マイクが EMM-6
インターフェースが US-366で、どちらもそれ程高価なものではない。
また、ソフト(REW と rePhase)を利用するには少し慣れが必要。
![]() 2016-05-07(土) 位相調整方法が違っていた
2016-05-07(土) 位相調整方法が違っていた
これまでの方法で rePhase で位相を調整した後に Impulse Response の波形を見てみたら FIR EQ フィルターをかける前後で形が殆ど変わっていなかった。やはり調整方法が違っていたようだ。
試しに位相が 1 回転する 360°の範囲内でフラットにしてみたら見事に Impulse Response が改善して、定位も安定した。
Impulse Response(左が FIR 適用前、右が FIR 適用後)
【rePhase の位相調整方法(改訂)】
[Ranges]の中の[Phase]の範囲を−360°to 360°とし、[Paragraphic Phase EQ]タブの[range]を±180°として位相が 0°ないしは 360°の線上に乗るように調整する。180°を越える場合は角度欄に数値を直接入力する。
それ程細かく調整する必要はないようだ。なお、調整時は SPL が邪魔なので、gain offset を 0dB にして画面の外へ出してしまうと見やすくなる。
位相調整の様子(上が左 CH、下が右 CH) 音響特性測定結果(左が FIR 適用前、右が FIR 適用後)
(測定時期が違うので高域が微妙に違う。要調整)★ やっと OpenDRC-DI の能力を引き出せたようだ。
![]() 2016-05-06(金) OpenDRC-DI
の使い方(最終)
2016-05-06(金) OpenDRC-DI
の使い方(最終)
【rePhase による位相補正】GAIN を調整すると適用した周波数前後の位相がずれる。これを rePhase の位相調整タブで元に戻す作業をする。これが正しいのかは不明だがやってみた方法は以下の通り。恐らく左右の位相バランスを事前に修正しておく必要があると思われる。ただ、これは位相が大きく変化するので補正は難しい。
- rePhase を立ち上げ直した場合は、Setting データを読み込む。File → Load Settings… で前回保存したファイルを指定。
- [Measure]の[clear]で測定データを消す。すると GAIN(実線)と Phase(点線)だけが残るので、[Paragraphic Phase EQ]タブを使って Phase をできるだけ平らに、そして 0 度に近づける。
- 周波数の低い方ないしは高い方から順番にピークを補正していくと修正しやすい。
- まず、ピーク周波数を画面から読み取り、Hz 欄に数値を入力する。入れる場所はどこでも良いが分かりやすく端から順番に入れていくのが良い。入力した周波数がピークからずれていたら数値を修正する。
- スライドボリュームを動かしてみて変化する周波数範囲が広すぎたら Q を大きく、狭すぎたら Q を小さくする。Q は大きめにした方が調整はしやすい。
- 適用量は次の補正の影響を考えて少し大きめにしておく。
- 次のピークに対しても上記と同様の作業を行い、順番に最後まで修正する。
- 一通り終わったら、次の Bank を使って Q を更に大きくして微調整する。目標は±5 度以内。
rePhase の位相調整画面 【FIR EQ データの作成】
GAIN と Phase の調整が終わったら念のためデータを保存(File → Save Settings)した後に FIR EQ データを作成する。
- [Impulse Settings] で [Taps] に 6144 と入力、[rate] は 48kHz を選択、[format] は [32 bits IEEE-754 mono (bin)] を選択、ファイル名を [file name] の欄に入力、保存先は [directory] の欄をクリックすると保存場所選択画面になるので適切な場所を指定する。
- [generate] ボタンを押すと計算が始まって FIR EQ データが [directory] の場所に保存される。
最大レベルなどの計算結果がボタンの下に表示されたら完成。
Impulse Settings
【FIR EQ データの取り込み】rePhase で作成した左 CH と右 CH の FIR EQ データを OpenDRC-DI に取り込む。
- OpenDRC-DI のプラグインソフト OpenDRC-2x2 を立ち上げて、[FIR Channel 1]をクリック。
- [Browse] をクリックして rePhase で保存した左 CH の FIR EQ データファイルを指定、読み込み。[OK]、[Send to DSP]を押す。
- 同様に右 CH の FIR EQ データを[FIR Channel 2]に取り込む。
FIR EQ データを取り込んだ様子 【補正結果】
位相補正した FIR EQ データを OpenDRC-DI に入れて REW で特性を測定した結果が下図で、FIR EQ 適用により周波数特性がかなりフラットになった。音楽を聴くと定位が向上している。位相補正前後の音を聞き比べると、位相補正により金属音たとえばシンバルやトライアングルの音がきれいに聞こえるようになる事が分かった。
リスニング位置での周波数特性(上段が FIR 適用前、下段が FIR 適用後)
FIR EQ 適用で特性がフラットになっている。【最後に】
念のため調整後にもう一度音響特性を測定して必要なら微調整する。
![]() 2016-05-05(木) OpenDRC-DI
の使い方(その3)
2016-05-05(木) OpenDRC-DI
の使い方(その3)
【rePhase へのデータ取り込みと GAIN 調整】
- REW を立ち上げ、音響特性測定データを読み込んで、File → Export → Measurement as Text で保存。
rePhase は 2バイト文字のフォルダーにアクセスできないので、保存先は rePhase をインストールした場所にサブフォルダーを作ってそこに入れる。- rephrase を立ち上げて、右上にある Measurement → import で先ほど保存した測定データを読み込む。
- gain offset を−80 dB にして振幅データを画面内に表示させる。
ここからは全て手動
- REW で作成した PEQ データ(最大20ポイント)の画面から、周波数, Q, GAIN を読み取る。
- それを[Paragraphic Gain EQ]タブにある数値欄に入力する。
ただし、Q だけは読み取った数値を 2 倍にして入れる。18 個目以降は Bank 02 へ。位相設定はデフォルトの[minimum-phase]を使用。- 次に Bank 03 を使って PEQ データだけではフラットにならなかったピークを手動で調整して振幅応答全体を平らにする。鋭いピークは Q を 10 程度で調整。ディップは補正しない。
ここで一度 Setting データを保存する。 Save Settings as...
![]() 2016-05-04(水) OpenDRC-DI
の使い方(その2)
2016-05-04(水) OpenDRC-DI
の使い方(その2)
【PEQデータの作成】以下の操作は、左と右を別々に(計 2 回)行う。
音響特性を測定した後、右端にある[Controls]ボタンを押して、[Unwrap Phase]、[Generate Minimum Phase]ボタンを押してミニマムフェーズを作成しておく。
次に[EQ]ボタンを押してPEQデータを作成。
- EQを利用する機器はGeneric
- ターゲットのスピーカータイプはNone
- LF Rise Slope は 0.0
- HF Fall Start は 3000 Hzで
- HF Fall Slope は 1.8
- [Set Target Level]ボタンを押して自動で目標レベルを設定
- レンジは 40 to 10,000 Hz
- Individual Max Boostは16 dB(Defaultは 9 dB)
- Flatness Target は 2 dB(Defaultは 3 dB)
- [Match Response to Target]ボタンを押してPEQデータを作成
- グラフの上にある[EQ Filters]を押して、設定値を表示、[by Freq.][↑↓]でソートした後にこの画面をコピーしておく。
この中で必要なのは、Frequency, Gain, Q。
なお、設定の既定値は最初の画面の[Preferences]、[Equaliser]で指定できる。次回以降の測定にはそれが標準で出てくる。
![]() 2016-05-03(火) OpenDRC-DI
の使い方(その1)
2016-05-03(火) OpenDRC-DI
の使い方(その1)
測定のノウハウも含めてこれから手順を少しずつ書いていきます。【音響特性の測定】
- 音響特性測定用マイクEMM-6を標準のリスニング位置(ニアフィールドでは高さが重要)に置き、オーディオインターフェースUS-366でUSBを介してPCで取り込めるようにする。USS-366のマイクボリュームは80〜90%が良い(測定中にUSS-366のpanelを見てクリップランプが点灯しない最大のレベルに設定)。
- EQをOFFにした状態でスピーカーから信号音を出せるように機器をセットする。
- REWの右端にある[Reference]ボタンを押して、入出力機器を選びスピーカーから信号音が出るように、そしてマイクでその音が拾えるようにする。
- 信号音の大きさは通常聞くレベルでOK。Level is Lowと出ても大丈夫。
- 最初は左スピーカーだけから音が出るように、PCのどこかの設定で右側をMuteにするか、単純にアンプの右側入力プラグを抜く。
- REWの左端にある[Measure]ボタンを押し、次に[Start Measuring]を押して測定する。測定の繰り返し数(Sweeps)は1回が良い。現バージョン(V5.14)では複数回を選ぶと高域が異常データになる。
測定してみるとこんな感じのデコボコした特性が得られる。6畳の部屋なら150 Hzあたりにピークが出る。EMM-6はマイクの精度が2dB程度なのでこの程度の変動なら補正用として十分に使える。
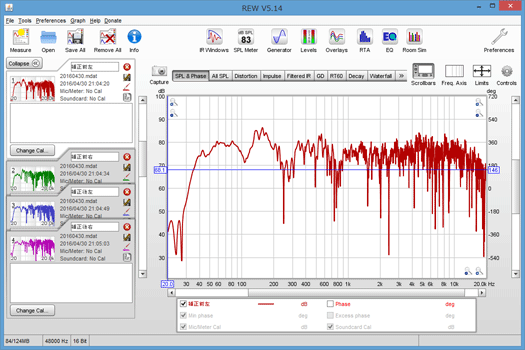
REWによる特性測定結果同様の測定を右スピーカーについても実施。
測定データは[Save All]で保存しておく。
![]() 2016-05-02(月) OpenDRC-DI が使えるレベルになった
2016-05-02(月) OpenDRC-DI が使えるレベルになった
miniDSP 社から購入したデジタルオーディオプロセッサ OpenDRC-DI は FIR フィルターを使えるのが最大の特長だが、それを支えるソフトが限られているため使うのに随分苦労した。
特に rePhase は設定が全て手動で、REW の EQ データを参考に設定したが相当の位相調整が必要だった。何故か REW と rePhase では Q の数値が倍半分なのでここでも面倒なことが起きる。色々と試行錯誤を繰り返してやっと実用レベルになり PEQ よりも良い音が出るようになった。FIR の特長は定位とインパルス応答の正確さだ。定位は PEQ では達成できないレベルの結果が得られた。また、Goodbye Yellow Brick Road[2014 Remaster]を聞いて最後の方にこんなピアノの連打音が入っていたのかと今更ながら驚いた。空気の波動を感じるバスドラとシンバルの金属音がはっきりと聞こえる。これが位相整合の効果だろう。
また、OpenDRC-DI は PEQ だけでもそれなりにいい音がする。同じ PEQ を使ってもminiDSP 2x4 よりも音が良かった。逆に言うと、miniDSP 2x4 のアナログ回路はあまり良くないようだ。値段相応とも言える。
左側の補正曲線(OpenDRC-2x2 の FIR 画面)
右側の補正曲線(OpenDRC-2x2 の FIR 画面)今回の補正ポイント数は 20 程度で、その 2 倍以上のポイントで位相補正をした。位相偏差のガイドは 5 度以内。rePhase は文字が小さいので見づらい。
定位が向上して音が鮮明になると今まで聞き慣れていた曲でもイメージが変わって新しさを感じることもある。
ZENSOR1 でこれ程の音が聞けるとは思わなかった。
OpenDRC-DI は素晴らしい。でも調整は大変だ。
![]() 2016-05-01(日) 春のヘッドフォン祭 2016
2016-05-01(日) 春のヘッドフォン祭 2016
土曜日の午前中、中野サンプラザで開かれていた恒例のヘッドフォン祭に行ってきた(ヘッドフォンはディジタルと同じでこだわりがありそう)。今回は行列もなくスムースに入れた。ヘッドホン熱も少し冷めてきたのか?
これと言って目新しいものはなかったが、audio-technica(オーディオテクニカ)のヘッドホンを試聴してみたら低価格帯ながら良い音が出ていた。競争が激しいので良い製品が出てくるのだろう。
ある出展者は STAX は古い音だと言っていた。確かにそうかもしれない。
ヘッドホンとは直接の関係はないが、S&K Audio のオーディオインターフェイス VT-EtSRC も見てきた。これから民生用でも使われるようになるかも知れない Dante Network 対応の機器だ。Made in Japan が売りらしい。
![]() 2016-04-30(土) 測定用マイクの特性
2016-04-30(土) 測定用マイクの特性
比較的特性周波数が良いと言われている WM-61A(マイク素子)の純正品を入手したので、EMM-6 と比較してみた。
図は WM-61A 素子を基準にした EMM-6 の特性で、ほぼ予想していた通り低域と高域が 2 dB 程度下がっている。ただ、10 kHz 以上のデータはバラツキが大きくこの図も正確ではない。ルーム補正用としては 2 dB は許容範囲だ。
WM-61A 純正品 2 個の平均と EMM-6 との感度差 測定信号は FLATSWEEP004096,48 kHz,右 SP 前約 8 cm,マイクを上下左右に移動しながら 10 秒程度測定,WaveSpectraで録音,CSV ファイルを EXCEL に取り込み分析,US-366,AT-MA2 使用
WM-61A の感度特性(説明書のグラフ)
![]() 2016-04-29(金) 理想のスピーカー その2(振動板の位置を制御)
2016-04-29(金) 理想のスピーカー その2(振動板の位置を制御)
今の振動板方式のスピーカーでも工夫すれば理想のスピーカーに近づく。
現在のスピーカーは振動板の位置をフィードバックしていない非能動の受動タイプなので、これを能動タイプにすれば音が良くなる。位置検出にはデコーダーを利用するのが理想だが、単にレーザー光による反射率の変化だけでもかなりの効果が得られる。振動板の位置をアンプにフィードバックして制御すると信号に忠実な音波が出せる。
最近の電子機器の高性能化でこの程度の処理は簡単に実現できるので早く実用化して欲しい。
(昭和時代に考えた「昭和の日」にふさわしいネタ)
![]() 2016-04-29(金) 理想のスピーカー(気体の状態方程式を利用)
2016-04-29(金) 理想のスピーカー(気体の状態方程式を利用)
現在のスピーカーは振動板を使って空気の粗密を作っているため、その振動板の質量・共振・固定などの影響が出て理想的な音にはならない。
そこで考えたのが空気の温度を変えて直接疎密波を作ろうというものだ。具体的には、おなじみの理想気体の状態方程式で温度を変えると圧力が変わると言う原理を利用する方法だ。
PV=nRT 圧力は温度に比例するので、空気の温度を信号に応じ変化させれば粗密波、すなわち音が出てくる。この方法なら振動板がないので、理想的なスピーカーが作成できる訳だ。
空気の温度を変化させる方法は簡易的には電熱線でもできるが温度が上がる一方なので冷却が必要になる。それを避けるためにはペルチェ素子で発熱部と冷却部で相殺する方法だ。これで温度上昇せずに一定の温度をキープできる。
ただし、これらの方法では金属接合部のサイズを極端に小さくしないと高域特性が悪くなるので、微少カプセルを多数用意する事になる。もう1つの方法としては、冷却は必要だがレーザーで金属など冷却性能の良い物質の表面を加熱して空気の温度をコントロールする方法だ。この方法ならマイクロセルを作るだけで多数の加熱・冷却素子は不要となり、制作は容易だ。ただし、冷却するので効率は悪い。でも音は理想に近いので理想のスピーカーとなる。
早くこの理想のスピーカーができる事を望んでいる。
![]() 2016-04-28(木) 久々に safe mode で起動した
2016-04-28(木) 久々に safe mode で起動した
SUMI2013 の REW が不安定になったので、インストールし直したらアイコンが絵柄なしになってしまった。高速スタートアップは無効にしてあるが、再インストールしても直らないので、久々に Windows を safe mode で起動したら直った。
この再起動でアイコン以外にもドライブの不要アクセスが減るなど色々な所が改善されたような感じがする。偶には safe mode で起動してみるものだ。
ただ、Windows 8 からは[F8]で safe mode が起動できなくなっているので、複雑なメニューからの起動となった。
![]() 2016-04-28(木) OS
が勝手に Windows 10 をインストールしようとする
2016-04-28(木) OS
が勝手に Windows 10 をインストールしようとする
SUMI2013 の動作が重くなったのでタスクマネージャのパフォーマンスを見るとディスクが 100 % になっていた。
調べてみるとOS が Windows 10 をダウンロードしていた。以前一度 Windows 10 にしたら不具合が出たので元の Windows 8.1 に戻した経緯がある。当分 Windows 10 にはしないつもりだが、無料アップグレード期限が迫っているためかダウンロードの集中によるサーバーの負荷を避けるために MS が勝手にソフトをインストールしようとしているようだ。
PC の中のデータも見られている可能性もあり全く困ったものだ。
![]() 2016-04-26(火) 3
本のマイク特性を比較してみた
2016-04-26(火) 3
本のマイク特性を比較してみた
ルーム補正は測定したマイクの特性に合わせるため、利用するマイクの性能が大きく影響する。そこで現在使っているマイクの特性をより正確に把握しようと、もう1 本測定用マイクを買った。今回購入したのは、オーディオインターフェースを利用しないで直接 USB 接続で利用できる Dayton Audio の UMM-6。メーカーは EMM-6(XLR 接続、ファントム電源)と同じだが形状はかなり違う。
今回購入したマイク UMM-6 とこれまで使っていたマイク2本の計 3 本のマイクの特性を測定・比較してみた。
測定用信号は FLATSWEEP004096 で、再生には OpenDRC-DI を使ってなるべくフラットな音を出した。サンプリング周波数は 48 kHz で WaveSpectra の FFT は 4096 ポイント。
結果は下図の通りで、このグラフは 3 本のマイク特性の平均値からの差分をプロットしている。
EMM-6 と UMM-6 は低域を除いて近い特性、ECM 素子(XCM6035-2022-354PR)はこれらに比べると高域が低下する傾向となっていた。ただ、ECM 素子のデータシートデータシートは10 kHz 以上では上がり傾向となっている。ECM 素子 2 個を比較しても傾向は変わらないので何が本当かはまだ不明。
まあ、50〜10 kHz までは±2 dB 程度の範囲にあるのでどのマイクでもルーム補正には使えそうだ。
なお、UMM-6 はブースト機能がないので、音量の小さな測定には向いていない。
どのマイクが良いかを判断するにはもう少しデータを増やす必要がありそう。
![]() 2016-04-25(月) ALL
JA コンテスト (2016) に参加
2016-04-25(月) ALL
JA コンテスト (2016) に参加
先週土曜日の 21 時から昨日の 21 時まで 24 時間 ALL JA コンテスト(2016)が行われたので、オーディオのチェックをしながら片手間に参加してみた。
参加したのは 7, 14, 21, 28, 50 MHz の 5 バンドで、JI1SEE として合計 22 局と交信した。これでアンテナの性能がある程度分かった。
バンド (MHz) 交信局数 最遠方局 アンテナ 7 2 広島 LW+FC-40 14 2 福岡、鹿児島 ATAS-120A 21 8 沖縄石垣 LW+FC-40 28 2 都内 両方 50 8 横須賀 ATAS-120A とりあえずログを JARL へ提出した(参加することが大切と割り切って)。自動計算された得点は 286 点だった。
![]() 2016-04-24(日) FIR
の効果大
2016-04-24(日) FIR
の効果大
OpenDRC-DI で FIR を適用したときの周波数特性の変化は下図の通りで、適用前(上)に比べて適用後(下)は特性がフラットになっている。
聴感上は音質と定位が格段に向上している。
その違いは素人にも分かるレベルで、オーディオ評論家だと驚愕の変化と表現するだろう。
適用後の音はプロ用のスタジオモニターに近く、低音が引き締まっていて高音は耳に刺さらない。
スピーカーから70cmの位置で測定。マイクはECM素子×2+AT-MA2、PC LINE IN、REW 1回。
![]() 2016-04-23(土) OpenDRC-DI
の使い方
2016-04-23(土) OpenDRC-DI
の使い方
OpenDRC-DI を使ってみて分かったことをメモとして残しておく。
【概 要】
OpenDRCでルーム補正をする場合、以下の4つのアプローチがある。
1. Dirac Live を使う
2. AcourateDRCを使う
3. Python Open Room Correction (PORC) を使う
4. rePhaseを使うそれぞれの特徴
1. Dirac Live を使う方法
操作が簡単で見かけ上は高精度の補正ができる。
ソフトは5万円程度(体験版あり)
Dirac Live Room Correctionの体験版ではエコーが付加される。その分音楽は聞きやすくなる。2. AcourateDRCを使う方法
操作は容易。ソフトは 約1万円(体験版あり)
3. Python Open Room Correction (PORC) を使う方法
フリーのコマンドラインツール。Windows 7のPython 2.7が必要、ラインコマンドで操作するので難易度が高い。
4. rePhaseを使う方法
Windows用の位相補正フリーソフト。miniDSPコミュニティのメンバー。
補正は全て手動でFIRデータを出力。
【rePhaseを使った補正方法】<必要なソフト>
1. OpenDRC 2x2 plugin(miniDSP/$10) OpenDRCのコントロール
2. REW(Room EQ Wizard/Free Software) 音響特性測定&EQ生成
3. rePhase(Free Software) 位相補正<注意事項>
rePhase はディレクトリ名に日本語(2 バイト)文字が使えないので、c:\rePhase\を作ってプログラムもデータも全てそこに入れる。
<基本的な考え方>
REWで音響特性を測定し、rePhaseでGAINとPHASEを調整する。
FIRでスピーカーの特性とルームエコーの補正をし、PEQで好みの音に調整する。<手 順>
1. まずREWで左と右の音響特性を測定(測定回数は1回を選択)。
File → Export → Measurement as Textで保存。
2. rePhaseで読み込み(File → Import Measurement...)。3. 右端にある[Paragraphic Gain EQ]タブで振幅応答を平らにする。
位相設定はデフォルトの[minimum-phase]。設定数は最大272(17個×16Page)。
4. 取り込んだデータは一度Clearする。
[Paragraphic Phase EQ]タブでGain EQの調整で変わった分だけ位相を補正する。Page 1で粗調整、Page 2で微調整。
5. FIRフィルターデータを保存。
[Taps]は6144、[Impulse Settings]の[format]で[32 bits IEEE-754 mono (bin)]を選んで、ファイル名は[file name]の欄に入力、[Generate]ボタンを押す。
6. 作成したFIRデータをOpenDRC 2x2 に入れる。
[Config 1]〜[Config 4]のどれかを選び、[FIR - Channel 1]をクリック(通常は左に使用)、[Browse]ボタンを押して、rePhase で作成したEQファイル( .bin)をロードする。右は[FIR - Channel 2]。
7. 特性を測定して必要なら再調整<参 考>
The rePhase FIR tool
https://www.minidsp.com/applications/advanced-tools/rephase-fir-tool
![]() 2016-04-18(月) OpenDRC-DI
が届く
2016-04-18(月) OpenDRC-DI
が届く
ルーム補正の EQ 用に注文していた miniDSP 社(香港)のデジタルオーディオプロセッサ OpenDRC-DI($ 320)が届いた。
miniDSP 社の online webshop で発注したのが 4/10(日)の深夜だったので、実質 1 週間で届いた事になる。
メーカーからの発送は FedEx だったが、配達はセイノースーパーエクスプレスだった。FedEx の輸送履歴を見ると成田で最終業者として委託されたようだ。FedEx の伝票番号でセイノースーパーエクスプレスの輸送状況まで見られた。配送車や作業員の番号まで確認できるのは面白い。
FedEx から届いたメールの配達予定は 4/18(月)〜18:00 となっていたので日限通りに到着した。FedEx が香港で製品をピックアップしたのが 4/14(木)なので輸送期間は 4日間。これでもエコノミー($ 20)なので最近のロジスティクスの進歩は素晴らしい。OpenDRC-DI は入出力ともに光デジタルで、光ケーブルも 2 本付属してきた(φ2.2 mmと細く扱いが悪いと折れそう)。リモコンは付属していなかった。何故か Quick start guide が入っていなかった。その代わりにラックマウント金具が入っていた。何かの間違いだろうがとりあえずは良しとしよう。
デジタルオーディオプロセッサ OpenDRC-DIminiDSP 2x2 はプラグインソフトが 1 本無料で付いてきたが、OpenDRC-DIのコントロール用プラグインソフト(OpenDRC-2x2)は別売り($10)だった。
【今後の計画】
REW で音響特性を測定、REW と rePhase で振幅・位相を調整、 rePhase で FIR フィルタデータを作成、OpenDRC-2x2 を使って OpenDRC-DI にUSB 経由で入力。
rePhase は全て手動なので、慣れるまでは調整に時間がかかりそう。
再生時の信号の流れは、
PC(USB)→ US-366(光)→ OpenDRC-DI(光)→ DA-300USB(RCA)→ AMP → SP となる。
FIRの実力がどの程度なのか結果が楽しみだ。
【別のアプローチ】
Dirac Live Room Correction の体験版を DL して試してみた。測定・調整が楽で定位が向上して音も聞きやすくなるが、エコーがかかるので原音再生の観点からはイマイチだった。一番の問題は価格とガチガチのコピーガードで PC の交換や将来の OS を考えると導入には踏み切れないソフトだ。何かある度に 5 万円は高すぎる。
![]() 2016-04-17(日) HF
アンテナの使い分け
2016-04-17(日) HF
アンテナの使い分け
アンテナチューナー(FC-40)を繋いだ LW(ロングワイヤー)アンテナは 21 MHz の同調が不安定だったので、10.7 m のエレメントを 20 cm 短くして 10.5 m にした。
これで再度 SWR を測定した結果、下表のような結果になった。LW のエレメントはやはり 2 本接続するよりも別々にした方が安定するので、切り替えることにした。
これで 50 MHz を除いて全バンドで SWR 1.0 を確保することができるようになった。ただし、SWR は時によって変わるので交信前には再測定が必要。
![]() 2016-04-17(日) マイクの特性を再測定
2016-04-17(日) マイクの特性を再測定
<2016-04-24追記>
以下は REW に問題があり間違っていました。2015-07-21(火)の結果が正です。
ファンレス PC(LIVA)を購入したので、改めて音響測定マイクの特性を測定・比較してみた。
比較したマイクは、昨年 5月に購入した Dayton Audio 社の EMM-6 と同 7月に購入した SPL(Hong Kong)Limited 製の ECM(エレクトレットコンデンサーマイク)素子 XCM6035-2022-354R(WM-61A 相当)。ECM 素子はオーディオテクニカのマイクアンプ AT-MA2 を介して、EMM-6 は直接 US-366 に接続して USB で LIVA に取り込んだ。
周波数応答の測定には REW を使用した。音源は ZENSOR1 の右側スピーカーでマイクとの距離は約 20 cm。
EMM-6 ECM 素子 結果は下図の通りで、両マイク間の差は 1 dB 以内であることが分かった。この程度の差ならルーム補正の測定にはどちらを利用しても大きな違いは出ないと思われる。
この図をみるとメーカーから提供されたキャリブレーション・データシートはいい加減だったことが分かる。購入した EMM-6 の特性はキャリブレーション・データシートよりもフラットで偏差も少ないようだ。
![]() 2016-04-15(金) SR-009
は格が違う
2016-04-15(金) SR-009
は格が違う
最近はルーム補正ばかりを試していたので、音楽を聴くよりもスピーカーから出る音の変化に気を取られがちだった。
システムを色々変えたので、単純な構成に戻して久々にヘッドホン(SR-009)で音楽を聴いてみたらその音の良さに驚いた。元々音が良かったのかエージングで音が良くなったのか不明だが、ZENSOR1 とは格の違う音がする。やはりSTAX の イヤースピーカーは素晴らしい。
久々に聞いた SR-009 は格の違う音がする。
![]() 2016-04-10(日) LIVA
X2 購入
2016-04-10(日) LIVA
X2 購入
PC(パソコン)オーディオ用にファンレスのミニ PC(LIVA X2)を買った。これまで音響特性を測定すると PC の冷却ファンの音が入ってしまいルーム EQ 補正ではこの部分が不正確になっていた。これを解消するためにオーディオ専用の無音 PC を導入した。
買ったのは ECS LIVA X2 LIVAX2-2/64-W10 で、OS は Windows 10 Home(64 ビット版)、CPU は Celeron Dual-Core N3050(Braswell)、メモリは 2 GB で、ストレージは eMMC 64 GB。PC オーディオはそれ程パワーのある CPU は必要ないのでこれで十分だろう。
PC ケースは幅が 16 cm 弱でコンパクトだが結構重い。製品仕様を見ると約560g となっていた。小型なので付属の VESA Mount を使ってモニターの背面に取り付けた(付属の M5 ねじは短すぎて使えなかった)。
この LIVA は USB ポートが 3つしかないのでキーボードとマウスで USB を利用すると空きが 1つだけになってしまう。これを避けるために Bluetooth のタッチパッド付きキーボード(EWIN Bluetoothキーボード)を購入した。このキーボードは手のひらサイズなので常用の入力には向かないがリモコン感覚で使えるので少し離れた所からの操作には便利だ。
Bluetooth 対応手のひらサイズキーボード
![]() 2016-04-08(金) アンテナの SWR 比較
2016-04-08(金) アンテナの SWR 比較
ATAS-120A と FC-40(LW)の SWR を比較してみた。周波数により SWR の良い方が変わるのでインターフェアの観点からは下表のように使い分けするのが良いだろう。
ただ、相互干渉があるのか測定値が時々変化するので使用前には再度確認が必要だ。先日アンテナ用の同軸切替器(CX210A)を買ったので切替えは簡単になった。ただし、アンテナと FT-991 のアンテナ SELECT が合っていないと TUNE を押した時に誤動作するので要注意だ。
![]() 2016-04-07(木) LW
2 本で全バンド同調
2016-04-07(木) LW
2 本で全バンド同調
八重洲のオートアンテナチューナー FC-40 に繋いだ LW(ロングワイヤー)の調整でどうしても10 MHz が同調しなかったので、10.7 m のエレメントにもう 1 本 6.5 m のエレメントを追加した。長さだけでなく給電点付近のエレメントを手摺から離すことで同調がとれた。これで 7 〜50 MHz の WARC(World Administrative Radio Conference)バンドを含む全バンドを FC-40 で同調させることができるようになった。
エレメント 1 10.7 m エレメント 2 6.5 m 八重洲アクティブ・チューニングアンテナシステム(同調コイル付きモービルホイップ)ATAS-120A と比べてどちらが良く飛ぶかはまだ不明。ただ、少なくとも 7 MHz はエレメントの長い LW の方が良く聞こえるので飛びもこちらの方が良いだろう。
アンテナ調整中に 21 MHz の SSB を聞いたら 9M0O 局が南沙諸島からで出ていたので、試しにコールしてみたら 1 発でコールバックがあり交信できた。ベランダ内に設置した LW でも意外と飛ぶのでビックリした。
![]() 2016-04-04(月) LW
のエレメント長
2016-04-04(月) LW
のエレメント長
アンテナチューナー FC-40 に接続したロングワイヤー(LW)エレメントの長さで同調する周波数を確認してみた。
エレメントを 22 m から少しずつ短くして行き 11 m まで確認した所、全バンドで同調する所はなかった。
狭いベランダでエレメントを何度も折り返しているのが原因かも知れない。
以前仮設置で約 20 m のエレメントを付けた時は全バンド同調したので微妙だ。エレメント長 11 m の時 7 MHz はそれなりに SWR が下がっている。7100 kHz では FC-40 が不要な位 SWR が良い。ちなみに 12 m の時の SWR は 1.2 で 11 m では 1.0 だった。7 MHz で使うなら 11 m が良さそうだ。
![]() 2016-04-03(日) ECM
素子で音響測定
2016-04-03(日) ECM
素子で音響測定
nimiDSP 2x4 の補正 EQ 特性を作成するための音響測定用マイクに以前買った ECM 素子(XCM6035-2022-354PR)を使ってみた。この素子は 50〜10,000 Hz までほぼフラットなのでマイク特性の補正は不要と思われる。
測定結果は Dayton Audio EMM-6 のそれと基本的な所は変わらなった。補正特性を比較すると今回は高域が下がっている。実際には EMM-6 の時はマイク特性を補正するために高域を下げているので結果は同じだ。
音質的にはこの前の FIR セミナーのデモで聞いた GENELEC 社のスピーカーに近づいている。立ち上がりの鋭さが取れて耳に刺さらなくなった感じがする。ZENSOR1 は多少高域が持ち上がり気味なのでこの補正で無難な音になっている。ただ、nimiDSP 2x4 を通すと定位が向上して音像が明確になるものの幾分歪み感が増してモニター系の乾いた音になる。歪み感の増加はコンテンツそのものの問題だと推測している。個人的には低音を少し持ち上げた方が好みに近い。ZENSOR1 は 50 Hz まで難なくこなすのでこの点では優れたスピーカーだ。
左の補正曲線 右の補正曲線 音響測定結果から EQ 特性を作成するために REW を使っている。この REW は詳細な設定ができる分条件によっては EQ 特性が大きく変わってしまうので慣れが必要なようだ。
![]() 2016-04-01(金) PC
オーディオは無線のノイズ源
2016-04-01(金) PC
オーディオは無線のノイズ源
無線で 7 MHz を受信していると、デジタルアンプ SM-50 からのノイズで S メーターが 5 程度振れる。また、DA-300USB を使うと、特定の周波数にキャリア性の強いノイズが発生する。このため、7 MHz で弱い局を受信する時には SM-50 と DA-300USB の電源を切っている。これ以外の周波数でも似たような現象があり、PC オーディオが無線のノイズ源となっているようだ。
また逆に無線の電波でアンプにノイズが入る可能性もあるので、アンテナはできるだけオーディオ機器から遠ざけるのが良さそうだ。
これとは別だが オーム電機の LED 照明から出ている 3.5 MHz のノイズはアンテナを少し離した程度では解決しない。困ったものだ。
![]() 2016-03-31(木) 最初の QSL カードが届く
2016-03-31(木) 最初の QSL カードが届く
昨日 JARL から JA8EZL 宛ての QSL カードが届いた。
昨年再開して最初に QSO 頂いた 7N1MJH 局との交信月の 10 月と翌 11 月分で計 15 枚。8 コール(北海道)は奇数月に発送されるので、今回は 3 月処理分として届いたようだ。
各局のカードを見るとコールサインの文字は意外と控えめだ。
届いた QSL カード(並びは順不同)
![]() 2016-03-29(火) お勧めのアルバム
2016-03-29(火) お勧めのアルバム
Amazon Prime Music を聞いていて見つけた。
アマルフィ 〜サラ・ブライトマン・ラヴ・ソングス〜
サラ・ブライトマンの歌唱力に加えて曲の構成、録音の良さも合わさって完成度の高いアルバムになっている。
サラ・ブライトマン(Sarah Brightman)2009 年 7 月に発売されたようだ。
![]() 2016-03-27(日) オートアンテナチューナ購入
2016-03-27(日) オートアンテナチューナ購入
富士無線電機の決算セールで、八重洲無線のオートアンテナチューナ FC-40 がチラシに載っていたので買ってみた。
FC-40 は FT-991 などに接続すると自動でロングワイヤーアンテナのインピーダンス整合をとる機器で、HF/50MHz で利用できる。設定値を 200 個記憶できるので、通常の使用には十分だ。
箱を開けてみると本体は予想よりも大きく頑丈な作りだった。
7 m のエナメル線をアンテナにしてコントロールケーブルなどを仮配線で試してみた所、同調する周波数帯と同調しない周波数帯があった。まだ、アースが不十分なのとアンテナ線の長さも調整が必要なようだ。
オートアンテナチューナ FC-40
![]() 2016-03-26(土) QSL
カード完成
2016-03-26(土) QSL
カード完成
プリントパックから予定より早くカードが送られてきた。色は予想していた通り少し暗めの感じになっていた。
JI1SEE を本格運用するためには新コールサインで JARL に入会するか QSL カード転送サービスを利用するかのいずれかになるだろう。
固定局の QSL カード(紙をスキャン)
![]() 2016-03-23(水) miniDSP
2x4 の効果
2016-03-23(水) miniDSP
2x4 の効果
miniDSP 2x4 による補正前後のインパルスレスポンスを見てみた。
波形を比較すると補正によって下のヒゲが小さくなっているのが分かる。
補正で音が滑らかになっているのはこの変化も効いていると思われる。
時間軸から推測して補正曲線の 7〜9 kHz 辺りのピークカットが関係しているのだろう。
REW で測定したインパルスレスポンス
![]() 2016-03-19(土) JI1SEE
の QSL カード
2016-03-19(土) JI1SEE
の QSL カード
自宅の固定局 JI1SEE の QSL カード図案が決まった。
移動局 JA8EZL のカードは窓から見える昼間の風景だったが、JI1SEE は夕景にした。固定局は HF 帯がメインなので運用は夕方から夜が多くなるためだ。コールサインは JA8EZL と違って移動運用を示す" /1 "がない。その分文字を大きくできた。" J I 1 " の文字間隔も微調した。
固定局の QSL カードこの前作った JA8EZL のカードは厚すぎて(0.3 mm)プリンターが壊れてしまった。今回は少し薄くて柔らかい紙で印刷して貰おう。
元 JARL 会長原さん(JA1AN 局)の QSL カードには厚さ 3 mm とか 5 mm とか、現 JARL 転送サービスでは認められていない厚さのものもあるそうだ。
<追記>
今回は価格の安いプリントパックに印刷を依頼した。一度入稿したがレイヤーが結合されていなかったため再入稿となった。データ不備の連絡メールが届いたのが 20 時頃だった。ここは年中無休で 24 時まで対応しているようだ。納品は 28 日の週になりそう。
![]() 2016-03-18(金) 好みの設定は MIC の補正特性そのものだった
2016-03-18(金) 好みの設定は MIC の補正特性そのものだった
音響測定に使っているマイク EMM-6 の特性で補正したらどの程度の影響があるのかを試して見たら、何とこの設定が好みの音そのものだった。
事は単純で、マイクの特性補正で本来の音に近づいただけだ。無理のない高音と適度な低音が元々の音だったようだ。
ただ、女性ボーカルの音割れだけは解消されない。リマスターの変な迷信が折角の綺麗な声を歪ませてしまっているようだ。
PEQ でマイクの特性を補正 <余談>
EMM-6 に付いてきた特性グラフは全く使えなかった。ホワイトノイズやフラットスイープ波を別のマイク素子と同時に測定してやっとこの EMM-6 の特性が分かった。
![]() 2016-03-16(水) REW
に Minimum Phase があった
2016-03-16(水) REW
に Minimum Phase があった
現在はフリーソフトのルーム音響解析プログラムREW(Room EQ Wizard)で miniDSP 2x4 の EQ カーブを作成している。
この REW の EQ にピークまでの時間を短くする Minimum Phase Generate 機能があったので試してみた。ノーマルとMinimum Phase で作成した EQ の音を比較すると、音質的には差がないが、ボーカルの位置はノーマルが少し奥に引っ込んでいるのに対してMinimum Phase はスピーカー前面付近に出てくる感じがする。
ステレオマイクで録音するとボーカルは奥に定位するが、通常は1本のマイクで集音するのでスピーカーの前後方向に対しては中央に定位する筈だ。その意味ではMinimum Phase の方が正しいのかも知れない。ピンクノイズを再生してみると、Minimum Phase の方がノーマルよりも中心に固まって聞こえるのでこちらの方が定位は良いようだ。
ノーマルで作成した EQ(左 CH)
Minimum Phase で作成した EQ(左 CH)
ノーマルで作成した EQ(右 CH)
Minimum Phase で作成した EQ(右 CH)
Minimum Phase で作成した EQ の方が幾分デップがはっきりしている(Q が高い)。
![]() 2016-03-13(日) miniDSP
2x4 の補正性能
2016-03-13(日) miniDSP
2x4 の補正性能
マイクスタンドを買ったので、miniDSP の補正前後の特性を測定してみた。
下図は REW で測定した特性で、図を比較すると補正によって周波数特性がフラットに近くなっているのがはっきりと分かる。特に部屋の反響音が影響している 130〜 200 Hz の山がなくなって平らになっている。
なお、補正後の特性で 3 kHz 以上の音圧が下がっているのは miniDSP 2x4 の中の EQ を使って意図的に好みに合わせたもので、設定通りの特性が出ている。
図の黒線は THD(歪み)で、よく見ると補正後の方が歪みが減っているのが分かる。ここでも効果が出ており、miniDSP 2x4 は正常に機能している。
補正前
補正後110, 267, 793 Hz のディップは左右スピーカーの干渉の影響だと思われる。この部分は聴取位置で変わるのであまり気にする必要はない。
![]() 2016-03-12(土) マイクスタンド購入
2016-03-12(土) マイクスタンド購入
より正確なポジションでルーム補正 EQ の音響特性を測定するためにストレートタイプのマイクスタンドを購入した。
買ったのは、K&M の 26010B で、直径 250 mm の円形ベース、高さは 870 〜1,575 mm、質量は 3.6 kg。 ネットの写真だけを見て購入したためサイズの感覚が狂って、直径 250 mm の足ベースは想定以上に大きかった。まあ、安定しているので良しとしよう。
マイクによる音響測定に先立ち聴取位置をメジャーで測定した所、壁に固定したスピーカー(ZESOR1)からの距離は 74 cm で左右スピーカー中心間の距離と全く同じだった。また、高さ方向はツイーターの中心よりも約 3 cm 高くウーハーとツイーターとの間ではなかった。
この聴取位置にマイクをセッティングして REW や Math Audio Room EQ で音響特性を測定してみた。マイクの向きは前方と上向きを試したが大差はなかった。あえて違いを挙げるなら上向きの方には歪のピークが現れていた。スタンドにセットすると手持ちに比べて再現性が格段に向上するので効果はあった。
この測定結果でルーム補正 EQ の効果を比較してみた。無理矢理に点数付けをすると下表のようになる。Math Audio Room EQ は定位の改善は素晴らしいが音質の劣化が足を引っ張ってしまう。
ルーム補正なし 60点 Math Audio Room EQ 70点 miniDSP 2x4 80点 参考(SR-009) 90点 評価に使った曲は MISIA のアルバム Soul Quest <初回限定盤> Disc 2 マイクスタンドにはアダプターは付属していない
![]() 2016-03-07(月) JTSW(J.TESORI
Sound Workshop)に参加
2016-03-07(月) JTSW(J.TESORI
Sound Workshop)に参加
3月4日(金)東京蒲田の大田区産業プラザ(PiO)で開かれた J.TESORI(ジェイテゾーリ)主催のサウンドワークショップ「FIR First」に参加してみた。
J.TESORI は元ボーズ日本代表の栗山譲二さんが立ち上げた会社で、音響関係製品の販売だけでなく音響技術の教育なども展開している。
今回は"FIR First"と題して「FIR デジタルフィルターの基礎と応用」のセミナーが開催された。2 月に miniDSP 2x4 を購入したので無料で参加することができた。参加者は 14〜15名で大半はプロの方だった。一般の人は 1/3 程度で常連さんが多かった。初めての参加だったが、講師(栗山さん)の説明が巧く非常に分かりやすい内容だった。
デジタルフィルターは、プロは遅延が少ない IIR(Infinite Impulse Response)をコンシューマは特性優先の FIR(Finite Impulse Response)を利用するようだ。FIR を利用するためにはそれなりのハードウェアが必要で、J.TESORI では miniDSP社の OpenDRC-AN(48,600円)を推奨していた。測定用マイクとソフトウェア(DiracLive)をセットにすると14〜15万円になる。
DiracLive による音響測定画面ルーム補正EQのデモがあったが、定位や音質の改善については自宅で聞くほどの効果はなかった。恐らく部屋が広かったことと使っていたスピーカー(Genelec)の特性がフラットだった事が主因と思われる。
とすると、ルーム補正EQは狭い部屋で特性の悪いスピーカーを使っている人向きだとも言える。
Genelecスピーカーの音は耳に刺さらない
![]() 2016-03-06(日) Windows
10 はまだ早い
2016-03-06(日) Windows
10 はまだ早い
Windows 10 もそろそろ安定してきた頃だろうと思いメインで使っているWindows 8.1 の PC をアップグレードしてみた所、COM ポートに不具合が発生してしまった。無線機が勝手に送信状態になって止まらないため、1日で元の Windows 8.1 に戻した。
![]() 2016-03-05(土) 固定局の免許状が届いた
2016-03-05(土) 固定局の免許状が届いた
JA8EZL /1 で交信していると時々「出張ですか」と聞かれることがある。毎回「自宅です」と説明するのが面倒なので現住所の固定局を開設した。
新コールサインは JI1SEE で二度目の再割り当てらしい。2 つのコールサインを持っていると運用が難しくなるが、ローカル局と交信する場合には移動局(JA8EZL /1)で、遠くの局と交信する場合には固定局(JI1SEE)と使い分けるのが良さそうだ。
移動局と固定局の免許状を比較すると、空中線電力の違いは別として、1.9 MHz 帯(1910 kHz)の電波形式が違っていた。移動局は 3MA(A1A, F1B, F1D, G1B, G1D)なのに固定局は A1A だけだった。
![]() 2016-02-29(月) SG7500
をベランダに設置
2016-02-29(月) SG7500
をベランダに設置
マグネット基台に取り付けて室内で使用していた 144/430 MHz 帯用モービルアンテナ SG7500 をベランダの手摺部分に設置してみた。
取付金具は ATAS-120A で使用しているものと同じダイヤモンド BK10 で、できるだけ手摺の影響を受けないように支柱の上端に取り付けた。それでもまだ手摺より室内側なので周囲の影響を受けるだろう。
手摺に固定すると室内のように位置による感度調整ができないが、SWR は使用周波数全域で 1.5 以下になった。
144 MHz は室内よりもノイズが少ないようだ。
SX27P で測定
![]() 2016-02-28(日) FT-991
のファームウエアをアップデート
2016-02-28(日) FT-991
のファームウエアをアップデート
FT-991 のファームウエアソフトが新しくなっていたのでアップデートした。
主な変更点は以下の通りだが、心なしか 7 MHz の受信感度も上がった感じがする。
1.弱電界やマルチパスなど受信状態が厳しい条件下での
C4FM デジタル復調制御をさらに最適化2.その他、機能改善および最適化
FT-991用ファームウエア Version メイン Ver.2.10 DSP Ver.1.05 TFT Ver.2.01 C4FM-DSP Ver.4.10
![]() 2016-02-25(木) 室内モービルアンテナの SWR
2016-02-25(木) 室内モービルアンテナの SWR
室内の窓際に置いている 144/430 MHz 帯用モービルアンテナ SG7500 の SWR(定在波比:アンテナのマッチング度合いを示す数値)が置く位置によって変わるようなので少し調べてみた。
430 MHz 帯の測定結果は下図の通りで、使用する周波数とアンテナの位置で SWR が大きく変わる事を確認した。144 MHz 帯はこれほどの変化はない。
SWR は DIAMOND SX27P で測定430 MHz 帯で最も良く使用する 433 MHz 付近では、38 cm と 68 cm に極小値があり、1.1 位まで下がっている。この SWR の低い所ではノイズレベルも下がる。ただし、SWR が最も低くなる位置とノイズレベルが最低になる位置とは数 cm 違っている。恐らくノイズ飛来方向の影響だろう。
SWR が高くなっている位置 10 cm と 95 cm はアルミサッシのフレームの近くで、予想通りアルミサッシの影響を受けているようだ。
この影響は 430 MHz が最も少なく、周波数が高くなるにしたがって大きくなっている。432 MHz 以上では 433 MHz とほぼ同じパターンになっていて周波数が高くなるにつれ全体に SWR が上がって特性が悪くなる。現在の SG7500 は一番高い周波数に調整してあるので、これ以上同調周波数を上げるためにはエレメントを切断する必要がある。ホイップのステンレス棒を切断するのは大変なので今回は止めておこう。
このアンテナを使っている八重洲のトランシーバー FT-991 は壊れやすいようなので、SWR の高いサッシフレームの近くでは使用しないように注意しよう。
![]() 2016-02-24(水) miniDSP
2x4 の入出力特性
2016-02-24(水) miniDSP
2x4 の入出力特性
miniDSP 2x4 のダイナミックレンジを確認するために入出力特性を測定してみた。
【測定方法】
WaveGene で生成した400 Hz のサイン波を DA-300USB から出力し miniDSP 2x4 に入力、miniDSP 2x4 の出力電圧を 2Way Advanced のレベルメーターで確認した。
DA-300USB の最大出力電圧が miniDSP 2x4 の最大入力電圧(2.0 V)よりも高いため出力と入力との間に抵抗を挿入した。当初簡易アッテネータを入れたが、miniDSP 2x4 の入力インピーダンスが予想外に低く 15 kΩしかなかったので、1 kΩのシリーズ抵抗だけで整合がとれた。この時、DA-300USB の最大(0 dB)出力で 2Way Advanced の入力電圧表示は−0.2 dB だった。
サイン波 0 dB 入力時 無信号時 【測定結果】
miniDSP 2x4 の入力レベルを変えた時の 2Way Advanced のレベル表示値は下図の通りで、−70 dB から下は直線から外れている。入力、出力ともに同じ表示なので ADC 段階で既に直線性が失われているようだ。デジタルマルチメーターで測定した電圧も結果は同じだった。
miniDSP 2x4 の入出力特性 注)2Way Advanced はminiDSP 2x4 をコントロールするプラグインソフトウェア
【評 価】
このグラフからダイナミックレンジは約 80 dB(バイナリーで 13 ビット相当)と思われる。以前測定したパワードスピーカー(GX-70HD2)の内蔵アンプと同じレベルだ。DSP としてはあまり良くない値だが通常の信号レベルなら使えるだろう。価格相応の性能とも言える。
![]() 2016-02-22(月) 3.5
MHz は無理
2016-02-22(月) 3.5
MHz は無理
ベランダに設置したアクティブ・チューニングアンテナシステム ATAS-120A の使用可能周波数は 7/14/21/28/50/144/430 MHz で昔(開局当時に)出ていた 3.5 MHz は範囲外だ。
そこで ATAS-120A のホイップ先端にφ0.32 mm のエナメル線を付けて同調周波数を下げてみた。最初に長さ 20 m のエナメル線を付けてみたら、同調はしたが SWR が 2 以下にはならなかった。エナメル線を少しずつ短くして行くとATAS-120A の調整コイルが長くはなるが 6 m でも同調した。接続する線の長さを短くしても SWR は殆ど変わらなかった。カウンターポイズを追加すると SWR が少し改善するが、それでも2 以下にはならなかった。結局この方法では 3.5 MHz の利用は難しいようだ。ただ、受信感度は確実に上がるので聞くだけなら効果はある。
測定中に 1つ分かった事がある。それは、3.5 MHz は LED 照明器具からのノイズが多い事だ。何と今のシャック天井に据え付けたオーム電機のシーリングLED 照明は最悪で「安物買いの何だか」だったようだ。
![]() 2016-02-17(水) GH-4
アンテナの向きを変えられるようにした
2016-02-17(水) GH-4
アンテナの向きを変えられるようにした
室内に設置した 4 エレ円ループアンテナ(GH-4)はこれまで室内に張ったヒモに吊していたため簡単には向きを変えられなかった。
そこで写真のような物干金具を使って簡単にアンテナの方向を変えられるようにした。アンテナは手の届く高さにあるので、信号強度(S メータ)を見ながら振れが最大となるようにアンテナを調整することができる。水平偏波に対しては従来通り接続ケーブルの引っ張り具合で調整できる。
GH-4 で実際に交信してみると、意外な方向から電波が飛んできている事が分かったりする。例えば、渋谷のある局はアンテナを渋谷方面に向けるよりも 90 度違う新川崎方面に向けた方が電波が強い。これは確実に反射波を受けているようだ。ビル反射なのか山岳反射なのかは不明だが、モービルホイップアンテナ(SG7500)よりも受信レベルが高いので、この局の場合は GH-4 の方が適している。
物干金具に吊した GH-4 アンテナ
(物干金具は壁中の鉄板に穴を開けて木ねじで固定)<GH-4 と SG7500 の使い分け>
窓際に置いた 144/430 MHz 用モービルホイップアンテナ SG7500 は置く場所によって SWR が変わる事もあり 433 MHz 付近では常に SWR が低い GH-4 を使用する事が多くなった。
一対一の交信には GH-4 を、ロールコールのように多数の局と交信する場合には SG7500 と使い分けするのが良さそうだ。<SG7500 は室内の方が高感度>
因みに、SG7500 をベランダに設置(ATS-120A と交換)した場合と室内に置いた場合とでは、室内の方が感度が高いことが分かった。
室内の方がベランダ設置よりも給電点が 30 cm 程高い事と手摺の影響がないのが条件として良いのだろう。室内ではアンテナの位置を微調整して最大感度に持って行けるのも良い。
置く場所で感度や SWR が変わるので、もしかしたら窓の桟(縦 1.4 m)がリフレクターの役目を果たしている可能性もある。<GH-4 と SG7500 の相互干渉>
現在の利用方法だと、GH-4 の前に SG7500 がくる。SG7500 がGH-4 の邪魔になるかと思っていたら、予想に反して位置を調整することで SG7500 がない場合よりも GH-4の感度が高くなる事が分かった。
ATAS-120A のアース線もそうだったが、アンテナはやってみなければ分からない事ばかりだ。
![]() 2016-02-16(火) MJ
オーディオフェスティバル
2016-02-16(火) MJ
オーディオフェスティバル
2/11(木)に秋葉原の損保会館で開かれた MJ(無線と実験)オーディオフェスティバルに参加した。
4 つのステージと自作コーナーで実演や相談の受付をしていた。メインステージでは自作アンプやスピーカーの試聴が行われ、音の良さを競っていた。感想としてはアンプを変えても殆どがメインスピーカーとして使っているアルテックの音(中音域の響きが良い)から大きく変わらないと言う印象だ。
イエローステージでは MJ の執筆者が選んだ各種アンプの比較試聴が行われていた。製品の試聴では恣意的に音圧を変えるという本音トークもあり面白かった。
アンプの比較ではパワー不足だと確実に歪む事を体験した。でも皆さんは歪みに慣れてしまっているのかあるいは嗜好が違うのか、小パワーでも良くドライブできているなどと言う信じられないコメントをされていた。これでは録音の歪みが減らない訳だ。パワーに余裕があるとピークでも歪まないのでやはりパワーは大事だ。と言うことで、家で使っているデジタルアンプを Lepy LP-2024A+(20 + 20 W)から SMSL SA-50(50+50 W)に変えてみたら確かに大きな音では SA-50 の方が良いことが分かった。これまであまり気にしていなかったがアンプのパワーは大きい方が良い。
20+20 Wのデジタルアンプ Lepy LP-2024A+(左)と 50+50 Wのデジタルアンプ SMSL SA-50(右)
MJ オーディオフェスティバル参加の主目的はルーム補正の実演だった。ところが、当日の実演は段取りが悪く巧く補正されなかった。結局当初の目的は果たせなかった。
![]() 2016-02-14(日) パソコンで CW(モールス)
2016-02-14(日) パソコンで CW(モールス)
JA3CLM さんが作ったモールス信号送受信ソフト Digital Sound CW を使って FT-991 の CW を試してみた。
Digital Sound CW 受信の様子 パソコンと FT-991 は USB ケーブルで接続、インターネットの記事を参考にリグのMENUとソフトの設定をした。
◆FT-991 側の MENU 設定:
060 PC KEYING は RTS
071 DATA PTT SELECT はDTR ないしは RTS受信は問題なく動作したが最初送信がうまく行かなかった。原因は利用する COM ポートの間違いだった。インターネットに書かれていた「仮想ドライバの若番」が違っていたようだ。仮想ドライバの COM ポートは 2つあるが、後番の COM4 が正解だった。これで無事送信ができるようになった。
FT-991 側で受信帯域を狭め、DNRでノイズを抑えれば普通に使えるようだ。さすがに QSB が深い時は耳で聞いて補完する必要がある。
![]() 2016-02-12(金) ATAS-120A
の SWR が 1.1 以下になった
2016-02-12(金) ATAS-120A
の SWR が 1.1 以下になった
ベランダに設置した ATAS-120A の設置方法やアースの取り方を種々試した結果、次の条件で SWR が全バンド 1.1 以下に収まった。
- 設 置:
コネクタ部がベランダ手摺の下部から 10 cm 上になるように設置。これより高くしても低くしても SWR が上がる。
- アース:
ベランダの手摺にあったネジを利用して両端に圧着端子をつけたケーブルで接続。これである程度は効果があった。
- カウンターポイズ:
3.6 m× 1本、5 m×4本、10 m×2本を接続。3.6 m と 10 m の 1本を除き線は巻いたままで手摺の下に設置。
常識とは逆で線をベランダに張り巡らしたら SWR が上がってしまった。ある OM さんは「電波はカウンターポイズからも出る。線の端はとぐろを巻いたようにしておくのが良い」と言われていたのが少なからず当たっているようだ。また、追加で 10 m ×5本を接続したら SWR が上がった。カウンターポイズは多ければ良いという物ではなさそうだ。なかなか難しい。各バンドのSWR
バンド Freq. (kHz) SWR 7 MHz 7,100 1.1 10 MHz 10,130 1.0 14 MHz 14,112 1.0 18 MHz 18,110 1.0 21 MHz 21,150 1.0 24 MHz 24,930 1.0 28 MHz 28,200 1.0 50 MHz 51,000 1.1
SWR は FT-991 のメータから読み取った値微妙なバランスで何とか全バンド SWR を1.1 以下にすることができた。ただこれでも 7 MHz で強い局を呼んでみても応答はない。ホイップの限界か?それとも 50 W ではパワー不足か?
<追記>
昼前に 14 MHz を聞いたら北海道(JA8)の局が聞こえていたので呼んでみたら応答があった。相手局(苫小牧)の RS は 59 でこちらは 57 だった。相手局の出力が 100 W でこちらが 50 W なので妥当なリポートだ。
ベランダの中に設置したホイップアンテナで北海道まで届くとは予想外だった。たまたまコンディションが良かったのだろう。7 MHz でも 7K1KJC 局に 49 で拾って頂いた。恐らくこちらの信号はノイズすれすれだっただろう。
![]() 2016-02-09(火) miniDSP
の最大の効果はストリーミングを高音質で聞けること
2016-02-09(火) miniDSP
の最大の効果はストリーミングを高音質で聞けること
miniDSP の導入で Amazon Prime Music が高音質で聞けるようになった。
これまでは WaveSpectra などで録音してから foobar2000 で再生していたがその必要がなくなった。ウェブブラウザで気軽に曲を聞けるのが良い。最近はダイアナ・クラールを BGM で流している。
Amazon Prime Music(MP3) でもボーカルの歪みだけはいただけない。どうも意図的に歪まさせている感じがする。 MIX の TIPS を見るとそのような記述がある。これではダメだ。歪んでしまった声は元に戻せない。
![]() 2016-02-08(月) ASIO
は音が良いは迷信
2016-02-08(月) ASIO
は音が良いは迷信
色々な曲を聴いてみると、ASIO よりも Windows のサウンドドライバーの方が聞きやすいことが分かる。
電気的性能は ASIO の方が上だが、実際に聞いてみると耳につく音がする。
恐らくデータを正確に送るためスピーカーがインパルス応答に追従できずにその結果音が歪んで聞こえてしまうのではないかと想像している。タイムドメインスピーカーなら事情が違うかもしれない。いずれにしても今のシステムでは ASIO よりも Windows のサウンドドライバーの方が合っているようだ(サンプルレートは 192 kHz)。
音が良いと評判の Music Bee が Windows のサウンドドライバーを推奨しているのもうなずける。
DSD や真空管の音が良いというのもこの辺りにポイントがありそうな気がする。
![]() 2016-02-07(日) miniDSP
によるルーム補正
2016-02-07(日) miniDSP
によるルーム補正
ポケットサイズの DSP(Digital Signal Processor)が手頃な値段で販売されていたので、買って試してみた。買ったのは、miniDSP 2×4 。アナログ入力が 2 ch 、アナログ出力が 4 ch 。プラグインソフトウェアを利用することで色々な音響信号の処理ができる。
今回は、プラグインとして 2Way Advanced をクーポンで購入した。4 ch ともパライコが使えるので、2 ch をスピーカーに、2 ch をヘッドホンに割り当てた。
ルーム補正の音響測定には REW(Room EQ Wizard)を使った。REW は左右同時の測定ができないようなので、Left と Right を別々に測定した。測定時の音圧レベルは約 49 dB だったので補正の Target レベルを 45 dB と軽めにして miniDSP で使える EQ データを作成した。
左チャンネルの補正 右チャンネルの補正 補正して音楽を聴いてみた結果、直ぐに MathAudio の Room EQ for foobar2000 よりも素直な音がする事が分かった。
これはまともに使えそうだ。
![]() 2016-02-03(水) HDD
が回りっぱなしになる原因
2016-02-03(水) HDD
が回りっぱなしになる原因
最近 SUMI2013 の HDD が回りっぱなしになっている事に気がついた。以前 HDD が飛んだのもこれが原因の可能性が高い。
インターネットで調べると同様の現象が確認されているようで、その対策が 10 種類ほど載っていた。全て試して見た結果、イーサーネットの IPv6 を停止することで解決することが分かった。
SUMI2013 側の IPv6 を停止することで、SUMI2009 の CPU 使用率も下がったので、2 台のパソコンが影響しあっていたようだ。
![]() 2016-02-01(月) 7,195
kHz の AM が面白い
2016-02-01(月) 7,195
kHz の AM が面白い
アマチュア無線の 7MHz 帯を覗いてみると、このバンドの上限である 7,200 kHz の少し下 7,195 kHz にAM(A3E)の局が良く出ている。 CW や SSB よりもパワーが必要だが、SSB と違って受信機の周波数を正確に合わせる必要がなく声が自然に聞こえる。
JA8EZL 開局当時は AM だった。 QSB の影響を受けた AM 独特の音が聞こえて面白い。
7,195 kHz に AM 局が出ている
![]() 2016-01-31(日) ATAS-120A
の SWR が下がった
2016-01-31(日) ATAS-120A
の SWR が下がった
ベランダに設置した ATAS-120A は仮にマグネット式基台(ダイヤモンド SPM35)を使っていたが、これをモービルアンテナ用ベランダ取付金具(ダイヤモンド BK10)に変えた。更にカウンターポイズの位置を高くしたら全バンドで SWR が 1.5 以下に下がった。
各バンドのSWR
バンド Freq. (kHz) SWR 7 MHz 7,100 1.1 10 MHz 10,130 1.0 14 MHz 14,112 1.1 18 MHz 18,110 1.1 21 MHz 21,150 1.1 24 MHz 24,930 1.0 28 MHz 28,200 1.0 50 MHz 51,000 1.3 金具が効いたのかアースが効いたのか分からないが、とりあえず良くなったので、これで運用してみよう。
![]() 2016-01-29(金) ホイップアンテナの特性
2016-01-29(金) ホイップアンテナの特性
アマチュア無線の V/UHF 用アンテナに DIAMOND のモービル用ホイップ SG7500 を使っている。アンテナをマグネット式の基台に載せて窓際に置き利用しているが、アンテナの位置を左右に動かすと受信時の信号レベルが変化するので交信時は最も良く聞こえる位置にセットしている。どの程度動かすと信号レベルが最低から最高になるのかを測ってみた。
433 MHz 付近のローカル 5 局で試してみたら、全ての局で移動距離が 22±1 cm だった。測定前は 1/4 波長の 17 cm で最低から最高になると思っていたので意外だった。今使っている SG7500 の 430 MHz 帯 は 5/8λ で設計されている。433 MHz の 5/8λは 43.3 cm でその半分が 21.7 cm となるので、実測された 22 cm と合っている。
DIAMOND のウェブサイトより430 MHz は 1/4λ のアンテナ(MR73S)もあるので次に試して見よう。
![]() 2016-01-26(火) 無線局の新免許状が届いた
2016-01-26(火) 無線局の新免許状が届いた
FT-991M 購入時に変更申請をした新しい免許状が届いた。
変わった部分は 144 MHz と 430 MHz の電波形式と空中線電力で、3VF → 3VA に、10 W → 50 W になった。これで正式にデジタル通信 C4FM が利用できる。
<ATAS-120A>
HF 用に八重洲無線のアクティブ・チューニングアンテナシステム ATAS-120A を購入してベランダに設置した。
CQ オームの簡易ラジアルケーブルセット(カウンターポイズ)を付けて何とか受信できるようになった。ただ、21 MHz と 24 MHz の SWR は 1.7 で、まだ 1.5 以下には達していない。 他のバンドは SWR が 1.5 以下で、10 MHz と14 MHz は 1.0 まで下がったので問題なく使える。でも、ベランダなので飛びは期待できそうにない。ベランダでの主ノイズ源はエアコン室外機のインバータ。エアコンを止めるとノイズが減る。
各バンドのSWR
バンド Freq. (kHz) SWR 7 MHz 7,100 1.4 10 MHz 10,130 1.0 14 MHz 14,112 1.0 18 MHz 18,110 1.2 21 MHz 21,150 1.7 24 MHz 24,930 1.7 28 MHz 28,200 1.3 50 MHz 51,000 1.3
これまでハム用の無線機はハンディタイプの 144/430 MHz FM 専用機(FT-60)だけで HF が聞けなかったので、オールバンド機(FT-991M)を買った。この無線機は 144 MHz と 430 MHz では C4FM 方式のデジタル通信ができるほか、1.9 〜 430 MHz までの全てのバンドで移動局として許可される最大出力の 50 W 送信ができる。早速、インターネットを使って免許状の変更申請をした。
FT-991M は、巷の評判では混信に強いそうだが、まだ HF のアンテナがないので確認はできない。ただ、今住んでいる所は長いアンテナを張るスペースがないのでアンテナをどうするか悩みどころだ。
FT-991M はモバイル用のため AC100 V が使えない。このために DC 13.8 V が出る直流安定化電源(ALINCO の DM-330MV)も買った。スイッチング方式なので小型・軽量で低発熱だがノイズが発生しないかが気がかり。簡易的に室内アンテナで試した所、パソコンを付けると HF 帯は確実にノイズが増える。
![]() 2016-01-09(土) GX-70HD2
は EMI に弱い
2016-01-09(土) GX-70HD2
は EMI に弱い
DALI のスピーカー ZENSOR1 を使い始めてから、オンキヨーのパワードスピーカー GX-70HD2 は使っていなかったが、折角あるので使ってみようと US-366 のモニター用として接続してみた。
ところが、近くにあるアマチュア無線機の FT-60 で電波を出すとこのスピーカーからハム音がでる事が分かった。たった 1 W でも 144 MHz と 430 MHz の両方にアンプアイが入る。
どこから電波が入るのか調べるために接続している線を全て外してみたが、一向に改善しなかった。EMI 対策用のフェライトコアを電源ケーブルに取り付けてみたが、何も変わらなかった。どうもアンプの基板に直接電波が乗っているようだ。これ以上の対策は困難なので使用をあきらめた。
GX-70HD2 は EMI に非常に弱い。恐らく最近の EMI 仕様を満足していないのだろう。オンキヨーも技術レベルが低い。中国製 Lepy のアンプはケースが金属製だと言うこともあり全く問題はない。
|
|
![]()
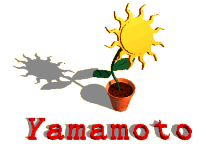
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る