| <<What's New>> ハムとパソコン、PCオーディオ奮闘記 2017年 |
|
|
![]() 2017-06-19(月) 【ブログ移行】2017-10-22
追記
2017-06-19(月) 【ブログ移行】2017-10-22
追記
今後のブログは YAHOO! に掲載します。
記録は全てe-masionのサーバーに移しました。2017-10-22
![]() 2017-06-18(日) LW
のエレメント長
2017-06-18(日) LW
のエレメント長
オートアンテナチューナー FC-40 の取扱説明書を見ると、使用可能周波数は、7 m 以上のワイヤーで 3.5 〜 54 MHz となっている。
以前、エレメント(ワイヤー)長を 11 m 〜 22 m まで変えて各バンドの同調可否を確認したときに、3.5 MHz は 17 m 以上ないと同調しなかった。取扱説明書の内容が正しいならもしかしたら 7 m に近くなると 3.5 MHz も同調するかもしれないと考えて 10 m 以下も実験してみた。結果は下表の通りで、残念ながら 7 〜 11 m の範囲では 3.5 MHz には同調しなかった。メーカーの測定とは条件が違うようだ。
下表と過去の実績からみてベランダ LW のエレメント長は 11 m 前後が良いようだ。
今回実験した LW のエレメント長と FC-40 の各バンド同調可否
及び FC-40 OFF 時の同調周波数
<参考>以前実験した LW のエレメント長と FC-40 の各バンド同調可否
![]() 2017-06-17(土) クランプフィルタ
2017-06-17(土) クランプフィルタ
FT-817ND に付属してきた外部電源ケーブル用フェライトコア(クランプフィルタ、通称パッチンコア)は 50 MHz のコモンモード除去性能が非常に良かった。ケースの記号を見ると JPN135 5.5 と書かれていたのでWebで調べてみるとトミタ電機の EMI Suppressors Core だった。トミタ電機(蒲田にある東京営業所)に電話して小売りしているかを聞いたら「デンカエレクトロン」を紹介された。ここでの型番は DC-1606N だった。このクランプフィルタは 3D-2V ケーブルが余裕で入るが 5D-2V は入らなかった。5D-2V 用は DC-1907N だったので、それぞれ10 個を注文してみた。
クランプフィルタによるコモンモード除去でノイズ低減に劇的な効果があったのは、ノンラジアルタイプのホイップアンテナ(HR50)で、同軸ケーブルに付けると確実にノイズが減る。現在ノイズの少ない時間帯では FT-991 の AMP1 で 50.175 MHz のノイズ(SSB)は S1 以下(AMP2 で S4)になっている(充電器と PC モニターの電源 OFF 時)。
手すりをグランドとしている FC-40 に接続した LW では効果が少なかった。現在のノイズは AMP1 で S4〜5(AMP2 で S8)。50.175 MHz のノイズ(SSB)
FT-991 の設定 ホイップアンテナHR50 FC-40+LWアンテナ IPO:AMP1 S1 以下 S4〜5 IPO:AMP2 S4 S8
FT-991 に関連するケーブルに取り付けているコモンモード除去フィルタ:
- 同軸/#43 トロイダルコア(3D2V W1JR巻き)+JPN135
- アースライン/#61 トロイダルコア(半周巻き)
- 電源DC ケーブル/5D 用クランプフィルタ(ESD-SR150)に一巻き
- 電源AC100V ケーブル/現在フィルタなし(付ける予定)
![]() 2017-06-15(木) FT-817ND
の周波数誤差は 0.5ppm
2017-06-15(木) FT-817ND
の周波数誤差は 0.5ppm
FT-991 を 10.000000 MHz で校正した後、FT-817ND の周波数誤差を測定してみた。
結果は下表の通りで周波数誤差は −0.5 ppm だった。オプションの TCXO ユニットの精度が 0.5 ppm なので実に微妙な数値だった。FT-817ND の周波数誤差
測定周波数
(MHz)周波数誤差
(kHz)相対誤差
(ppm)430.230 -0.18 -0.4 144.230 -0.07 -0.5 50.230 -0.02 -0.4 21.230 -0.01 -0.5 平均 − -0.5 2017-06-11(日) 電子機器はノイズ発生源
FT-817ND を使って室内のノイズ源を調査した。
これで発見したのがマキタのバッテリー充電器。ハンディクリーナー用のリチウムイオンバッテリーの充電に使っていたもので、これが HF の大きなノイズ発生源だった。以前から 50 MHz はノイズの多いバンドだと思っていたがこれを止めたらノイズが激減した。デスクから少し遠いところにあったので、これまでは気がつかなかった。FT-817ND の調査でこれが判明した。何とノイズ源は自分の部屋にあった訳だ。
これ以外にも各種バッテリーの充電器はノイズが発生する。
パソコンも当然、パソコン用モニターもノイズ発生源だった。以前から SSB で聞くとピューピューと周波数の変わる音がするキャリアの発生源はパソコン用モニターだった。いずれにせよベランダに設置したアンテナでは室内のノイズの影響をまともに受けるので、微弱信号を受信する時には室内にある電子機器の電源を OFF にする必要があるようだ。
<雑感>
これとは関係ないが最近は HF 帯に潜水艦探索用レーダーの電波が飛び交っている。何かきな臭い感じがする。
![]() 2017-06-09(金) 変更手続き失敗
2017-06-09(金) 変更手続き失敗
FT-817ND を買ったので「総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」を使って JA8EZL の局免許変更申請をした。
ところが、申請後に内容を確認した所、第 1 装置の技適番号が開局当時の FT-450DM になっていた。申請 2 日後に気がついたので、急遽「取下げ願」を出して変更申請をキャンセルした。受付処理前だったので何とか間に合った。その後、第 1 装置を FT-991M にした第 1 回目の変更データを探し出してそれに FT-817ND を増設する申請をした。このため 手続きが 2 日遅れてしまった。最初に使ったデータのファイル名は第 1 回目の変更時の日付だった。申請書作成時に V/UHF の空中線電力が 10 W になっていたので変だとは思いながらここを 50 W に書き換えていた。この時点で第 1 装置の技適番号を確認すべきだった。
無線設備の推移
申 請 第 1 装置 第 2 装置 第 3 装置 開局時 FT-450DM FT-60 なし 第 1 回目の変更 FT-991M に取替 FT-60 なし 第 2 回目の変更 FT-991M FT-60 FT-817ND 増設 空中線電力の推移
申 請 HF V/UHF 備 考 開局時 50 W 10 W − 第 1 回目の変更 50 W 50 W V/UHF は変更 第 2 回目の変更 50 W 50 W 変更なし 後から分かったことだが、以前に申請したデータ(申請書)は Lite の「照会・ユーザー情報変更」の「申請履歴照会」からダウンロードできるようになっていた。ここからデータをダウンロードすれば今回のような失敗は避けられたようだ。
![]() 2017-06-07(水) FT-817ND
を購入
2017-06-07(水) FT-817ND
を購入
ベランダのアンテナ調整と屋上での移動運用のために FT-817ND を買った。
出力は最大で 5 W しか出ないが、この大きさで HF から UHF(430 MHz)までオールモードに対応している。ただ、スイッチ類が少ないのでその分操作は複雑そうだ。
充電が終わった FT-817ND
![]() 2017-05-27(土) LW
微調整
2017-05-27(土) LW
微調整
ベランダの LW は HF のハイバンドで利用するのが適切なようなので同調周波数を 21 MHz に合わせた。調整前のエレメント長は 11.0 m で 7 MHz 帯にギリギリで合っていた。これを少し短くして 10.4 m にしたら 2 つ目の同調周波数が 21 MHz にあった。
これで 21 MHz は以前よりよく聞こえるようになった。ただ、18 MHz は感度が下がったのでもう少し長い方が良いようだ。
7 MHz はエレメント短縮前後で感度の変化は殆どなかった。エレメント長と同調周波数 MFJ-259Cで測定、( ) 内は SWR
No. エレメント長 11.0 m 10.4 m 1 7.19 MHz (1.3) 7.56 MHz (1.2) 2 19.70 MHz (1.4) 21.20 MHz (1.3) 3 32.39 MHz (1.3) 33.87 MHz (1.2) 4 46.02 MHz (1.0) 47.62 MHz (1.2) 5 55.19 MHz (1.3) 58.56 MHz (1.4) 調整後 21 MHz をワッチしていたら 27 日の午後はコンディションも良かったのか、JA7WQX 局(仙台)や JA3HU 局(西宮)が強く入っていたのでコールしたらどちらも RS 59 のリポートを貰った。
JA3HU 局の話では「21 MHz の DP アンテナではエレメントは壁から 70 〜 100 cm に置くのが最も良い。マンションの鉄筋がラジエータとなっているのだろう。壁から離すほど正面方向へ飛ぶようになり、近づけると横方向に更には建物の裏側にまで飛ぶようになる」そうだ。MLA だけでなく電界型のアンテナでも電磁励起現象が起こるらしい。
![]() 2017-05-26(金) 再び MLA
2017-05-26(金) 再び MLA
25A の塩ビパイプとエルボーを買ったので、MLA(Magnetic Loop Antenna/Field_ant のスモールループアンテナMK-2AM)をカメラの三脚上に水平にバランス良く取り付けられるようになった。
早速 21 MHz で北海道の局の信号強度を LW と比較してみた。LW のエレメントは南北に張ってあるので北海道方向は感度が悪い。これに対して 水平に設置した MLA は全指向性なので LW よりも有利な筈だ。
ところが結果は期待外れで MLA は LW に比べると S で 2 〜 3 感度が低かった。
LW はエレメントが壁から 20 cm(手すりから80 cm以上)前にあるのに対して MLA はベランダの手すりの中なのでこの違いも影響していると思われる。
以前、MLA を垂直にして LW と感度比較したときの結果に比べると多少差は縮まっている。MK-2AM はループの直径が 77 cm なので、エレメント長は約 2.4 m、LW の 11 m に比べると 1/5 程度。一般に言われているとおりエレメントは長い方が有利なようだ。
ただ、スモールループアンテナのサイトには"高く自由空間に近い場所に上げるよりベランダの手すりや、戸建てのアルミの物干し、モービルのルーフトップに取り付けた方が、放射効率が上がりFBです。"と書かれているので、単純にエレメント長だけで評価してはいけないようだ。
![]() 2017-05-23(火) LW
その後
2017-05-23(火) LW
その後
LW(ロングワイヤー)の先端に MFJ-931 を接続してグランドに戻す miniLoop アンテナは 7 MHz では 6 dB 程度改善の効果を確認出来たが、他のバンドではそれ程の効果はなかった。miniLoop アンテナは使用バンドを変更するたびに MFJ-931 の設定変えにベランダへ行く必要があり不便だった。このため最近は元の LW に戻している。
<目立たない方策>
LW は壁からの距離が電波の飛びに影響するので、エレメントはできる限り壁から遠ざけた方が良い。そのためには支柱を壁より前に出す必要があるがマンションなので目立たない工夫が必須だ。これまで色々試した結果、現在は支柱の先端部分をφ 2.5 mm のステンレス鋼棒にしている。これだと遠くからは殆ど見えない。この支柱は常時左右が壁から 20 cm 出ている。更に下のエレメントは中央部で釣り竿の先端部分を使って 50 cm 前に出している。これ位の張り出しなら隣からも見えないので常設でも安心。HF のハイバンド(18 MHz 以上)はこれでも問題なく利用できるようだ。この張り出しで実際にはエレメントから構造物までは給電点を除いて 1 m 以上離れている。
![]() 2017-05-16(火) 430
MHz のスイスクワッドを試してみる
2017-05-16(火) 430
MHz のスイスクワッドを試してみる
神奈川ハムセンターからスイスクワッド New MK-4WD を購入して試してみた。
アンテナに同梱されてきた Data Sheet では同調周波数が 432 MHz で SWR が 1.0 になっていた。ところが、ベランダに設置して実測したところ同調周波数は 434 MHz に上がり SWR の最低値も 1.1 と高かった。大分周囲の影響を受けているようだ。
それでも室内の GH-4 やベランダの SG7500 と受信感度を比較すると FM 局では多少 New MK-4WD が良い感じがする。AL-207 は 430 MHz では SG7500 と同レベルなので、これらの中では New MK-4WD が最も感度が高いと言える。ただ、極端な差はない。
![]() 2017-05-14(日) たまには J-POP もいい
2017-05-14(日) たまには J-POP もいい
2014 年 2 月に e-onkyo music から購入したハイレゾ音源、中森明菜 ベスト・コレクション 〜ラブ・ソングス&ポップ・ソングス〜 flac 96kHz/24bit 全 34 曲を聞き直してみた。音の良し悪しはコンテンツ次第だが、このアルバムは J-POP にしては録音もそれ程悪くはない。音造りは SR-009 に合っている。
![]() 2017-05-06(土) 50
MHz の E スポは LW の勝ち
2017-05-06(土) 50
MHz の E スポは LW の勝ち
50 MHz の E スポで沖縄の局が聞こえていたのでアンテナの受信感度を比較してみた。たまたまワイヤーアンテナは mini Loop ではなくエレメントの先端が解放状態の LW になっていので、これとモービルホイップアンテナ(HR50)で信号強度を比べたら何と LW の方が S で 2 程高かった。
アンテナは指向性パターンがあるので簡単には比較できないが、今回は LW の勝ちだった。LW と HR50 のどちらが良いかはもう少しデータ数を増やす必要がある。
7 MHz は LW よりも mini Loop の方が高性能だが、波長よりエレメントが長い 50 MHz は状況が違うのかも知れない。
パイルアップの中、LW で沖縄(JR6)の局をコールしたら一発で応答があった。意外と LW も悪くない。LW の問題点は、ローバンドでは壁からの距離が大きく影響すること。インターネットの書き込みを見るとエレメントは構造物から 1/8 λ以上離す事が推奨されているようだ。
7 MHz の 1/8 λは 5 m なので、なかなか微妙な距離だ。3.5 MHz では 10 m 離す事になるので実質は無理だろう。以前試した 6 m の釣り竿アンテナ(壁から 5 m 前に出てた)では 7 MHz の CW で米国まで届いたのがうなずける。
やはりアパマンハムの HF はハイバンドが適しているようだ。これまでの実績をみると、18 MHz と 21 MHz が合っているようだ。50 MHz は何故かノイズレベルが高い。因みに、3.5 MHz の性能は、
ベースローディングの LW > HR3.5 > miniLoop
7 MHz とは LW と miniLoop の順番が変わっている。
![]() 2017-05-01(月) HR3.5
を買ってみた
2017-05-01(月) HR3.5
を買ってみた
50 MHz 用のホイップアンテナ HR50 の性能が良かったので、今度は 3.5 MHz 用のホイップアンテナ HR3.5 を買ってみた。
こちらはアースが必要なタイプだが、これまでの経験からベランダの手すりがアースとして利用できる事が分かっているので、同軸コネクターの取り付け部に圧着端子を挟み込んでそれに接続した電線を手すりのネジ部に圧着端子を使って接続した。
設置は HR50 と同様に折り曲げ機構を利用してエレメントを水平にした。アンテナの全長が 2.23 m で壁からは 1 m 強突き出す形となった。
意外とエレメントは目立たないが短縮コイルの黒色が目立つので灰色のビニールテープを巻き付けてみた。多少は存在感が減った。でも利用時間は限られる。HR3.5 折り曲げ機構を利用してエレメントを水平に エレメントを壁に対して垂直にすると同調周波数が 3.550 MHz とバンドの中心にくるが、平行にすると同調周波数が 3.2 MHz 位まで下がり殆ど何も聞こえなくなる。 3.5 MHz は壁の影響が非常に大きい。3.5 MHz の場合はエレメントを壁に対して垂直にするアンテナが向いているようだ。これは HF 全体に言えることかも知れない。
因みに、45°傾けたときの同調周波数は 3.500 MHz だった。この程度の傾きは許容範囲あるいは逆に同調周波数の調整に利用できそうだ。
<性能比較>
HR3.5 の性能は mini Loop アンテナよりも良く、受信感度で S 2 〜 3 上だった。
QSO してみるとこれまでのアンテナでは無理だった岡山まで RS 59 で届いた。この差は大きい。
ただし、同調周波数範囲は狭い。SWR は MFJ-259C で測定
![]() 2017-04-24(月) HR50
を買ってみた
2017-04-24(月) HR50
を買ってみた
試しにコメットの 50 MHz 用ホイップアンテナ HR50 を買ってみた。
このアンテナは HF 用としては珍しくノンラジアルタイプで使いやすい。
それに加えて 2.15 dBi のゲインがある。
ただし、1/2 λ方式なので全長が 2.13 m もある。ベランダでは垂直に立てられないので折り曲げ機構を利用してエレメントを水平にしている。mini Loop アンテナと比較すると、感度は数 dB 高いようだ。HR50 の先端を壁から出すとノイズが減って遠くの局が良く聞こえるようになる。性能はエレメントが手すりより内側にあるか外側(壁面側)にあるかで大きく変わる。
壁に近い位置では mini Loop アンテナよりも性能が上なので 50 MHz はこちらを利用する事になりそうだ。ただ目立つので利用時間の制約を受ける。
コメット HR50(折り曲げ機構を使いエレメントを水平にして利用)
![]() 2017-04-18(火) ミニループアンテナの SWR
2017-04-18(火) ミニループアンテナの SWR
LW(ロングワイヤー)とミニループ(mini Loop)アンテナの SWR を比較してみた。
ミニループアンテナの MFJ-931 の設定は 7 MHz に同調する K 0 で、この時のコイルは 13 μH、バリコンは 320 pF となっている。MFJ-931 は電気的には LC の直列回路となっているので、計算上の同調周波数は 2.5 MHz(等価長:30 m)となり 7 MHz と直接の関係はなさそうだ。
ミニループアンテナは 7.1 MHz に SWR の極小値があるが、これ以外にも 1.6 MHz や 14 MHz に極小値がある。グラフを見ると LW の極小値が単純にシフトしている訳ではない。恐らく 12 m のワイヤーと MFJ-931 の等価長(30 m)の合成でこのようになるのだろう。確かに単純に長さを足した 42 m は 7.1 MHz の 1 波長に相当する。ループアンテナのエレメント長は通常1 波長なので、条件にあっているのだろう。ただ、電波を放出するエレメントは 12 m で、42 m の 29 % しかないので同調しているとはいえ効率は悪いだろう。
また、14 MHz は 2 波長に相当するので等価長で同調していると思われる。これに対して 1.6 MHz は 1 波長が 188 m なので 42 m の倍数ではなさそうだ。周波数が低くなるほど周囲の影響を受けやすいのでベランダアンテナでは計算とズレてくる可能性は十分にある。
アマチュア無線とは関係ないが、この 1.6 MHz はもう少し同調周波数が下がれば中波を聞くのにいいかも知れない。
試しに MFJ-931 の設定を K 0 からインダクタンスが最大の L 0 に変更してみたら 1,422 kHz の受信感度が 1〜2 dB 上がった。
因みに L 0 の同調周波数は 1.2 MHz, 4.9 MHz, (9.0 MHz)。
設定を L 3(バリコン容量を約半分)にしてみると同調周波数は 1.5 MHz, 5.0 MHz, (9.0 MHz) となり、1,422 kHz の受信感度が K 0 に比べて 2 dB 上がった。<4/20 追記>
エレメント右側の折り返し部分を少し長くして 65 cm にしたら 1.6 MHzの同調周波数が 1.5 MHz に下がった。7 MHz も若干下がったが影響は少なかった。やはり周波数が低いほど周囲の影響を大きく受けているようだ。
![]() 2017-04-16(日) 新コイルで 3.5 MHz も同調
2017-04-16(日) 新コイルで 3.5 MHz も同調
LW の先端に MFJ-931 を繋いでグランドに落としたら性能が良くなった。ただし、MFJ-931 では 7 MHz までしか同調しなかったので、新しいコイルを作ってみた。
直径 75 mm のポリ容器にφ1.6 mm のスズメッキ線を 40 ターン巻いた。 MFJ-259C でインダクタンスを測定したら 1 MHz で 33 μH だった。
これに 250 pF のタイトバリコン(耐圧 1 kV)をパラに接続して MFJ-931 の代わりに使ったら、3.5 MHz でも FC-40 でチューニングできるようになった。 MFJ-931 のメーター部分だけを使って電流が最大になる所を探すと、新コイルは部分ショートせずに全ターンを使ってバリコンは約 90 pF の所だった。33 μH と90 pF の共振周波数は計算では 2.9 MHz で 3.5 MHz より低い。この新コイルを使って 3.5 MHz で電波を出したところ、夜に辛うじて仙台までは届いた。でもレポートは良くなかった。昼間に 5 km ほど離れた局に受信してもらったら、方向も悪いのだが聞こえないと言われてしまった。やはり 12 m のワイヤーでは無理がありそうだ。
![]() 2017-04-08(土) ミニループアンテナの性能(その2)
2017-04-08(土) ミニループアンテナの性能(その2)
LW(ロングワイヤー)アンテナに比べてミニループアンテナの方が性能の良いことが分かった。では、どの程度の差があるのかを比較してみた。7 MHz で比較的信号強度の安定していたローカル局(距離は約 3 km)を受信して S メーターをみたところ、ミニループアンテナは LW よりも 6 dB 程(S メーターの一目盛り分に相当)高かった。この分が性能差と思われる。
また、ミニループアンテナでも LW と同様にエレメントを壁から離すと強度が上がった。最初は外壁から 10 cm の位置(ベランダが引っ込んでいるので手すりからは 70 cm 前に出ている)で強度を測定し、そこから前へ 80 cm 出すと強度は 6 dB 上がった。
受信強度の比較(7 MHz)
外壁からの距離 *1 10 cm(70 cm) 90 cm(150 cm) S メーター LW 59 + 2 dB 59 + 8 dB *2 S メーター ミニループ 59 + 8 dB 59 + 14 dB *1 最大距離で、( )内は手すりからの距離
*2 2017-04-17 追記。ベランダ内の LW からの差は 12 dB で、電力としては 15 倍に相当するので大きな差だ。
![]() 2017-03-28(火) ミニループアンテナの性能
2017-03-28(火) ミニループアンテナの性能
これまで使ってきた LW(ロングワイヤー)アンテナと LW の先端を MFJ-931 でグランドに戻したミニループアンテナの性能を比較してみた。
受信時の Water Fall 画面を見るとミニループアンテナの方が高感度である事が分かる。これだけ違えば飛びにも差が出る訳だ。
この性能の差は単なる指向性パターンだけではないような気がする。元々今の LW がスペースの制約からエレメントを折り返ししているところに問題があったのかもしれない。
MFJ-931 あり(ミニループ)
MFJ-931 なし(これまでの LW)確認のために CQ を出していた浜松の局を呼んでみた。その局のアンテナは逆 V でパワーは 180 W、59 で届いていた。貰ったレポートは 57 だった。こちらのパワーが 50 W だったので同じパワーならもう少し良いレポートになるだろう。まだ性能は DP(ダイポール)アンテナには届いていないがだいぶ上がってきたようだ。
![]() 2017-03-26(日) 人工 RF グランドを試してみる
2017-03-26(日) 人工 RF グランドを試してみる
アースが不十分な時に役立つのが人工 RF グランド。コイルとバリコンを使ってアースグランドを電気的に最良の状態に調整する機器。回路的にはコイルとコンデンサーを直列に接続しただけの簡単なものだが整合がとれれば電波の飛びが良くなるらしい。
現在使っている LW(ロングワイヤー)のアースであるベランダ手すり(材質はアルミニウム)の電気的な長さは 5.8 m のようなので 7 MHz には少し足りない。この部分を人工 RF グランドで補うと LW の性能が上がるのか試してみた。今回買ったのは MFJ 社の MFJ-931。
まず、これがどのようなものか簡単に特性を測ってみた。
最初にバリコンの容量を測定してみた。最大容量は目盛り 1 の少し下でキャパシタンスは 0.32 nF だった。最小容量は目盛り 6 の少し下にあり測定値は 0.02 nF だった。
インダクタンスはタップ位置 A が最小で約 1 μH、タップ位置 L が最大で約 17 μH だった。
この MFJ-931 をアンテナチューナー(FC-40)のグランド端子と手すりに容量結合したアース線との間に入れ各バンドのグランド電流が最大となる設定を調べてみた。結果は下表のように各バンドとも最適な設定が見つかった。
手すりの最良点
バンド
(MHz)コイルタップ位置 キャパシタ位置 3.5 *1 G 0 7 D 1.5 14 E 2 18 D 3 21 D 1.5 28 D 1〜5 *1 3.5 MHzは LW のエレメントにシリーズに短縮コイルを挿入している。
これで 各バンドを試してみたところ、7 MHz と 14 MHz はノイズが減ったが飛びはそれ程変わらなかった。確かに MFJ-931 のメーターを見ても同調時の読みが 40 % の時にバイパスに近い最も低いインダクタンス(コイルタップ A)に切り替えても読みは 35 % 程度だった。これは 1 dB 程度の差なのでSメーターでは一目盛りの 1/6 と殆ど誤差範囲だった。
それでは、と言うことで別の使い方を考えてみた。
<別の使い方> ミニループアンテナ
LW の先端は絶縁されているが、これを MFJ-931 のカウンターポイズ端子に接続して、ミニループアンテナとして使用してみた。この時のループ寸法は横 5 m ×縦 0.5 m 程度で給電点は左下。この接続でグランド電流が最大になる設定は下表の通り。ただし、18 MHz 以上は MFJ-931 なしでも FC-40 でチューニングできるので直接グランドに戻しても良いようだ。
バンド
(MHz)コイルタップ位置 キャパシタ位置 7 K 0 14 I 0 18 F 0 21 C 3 24 F 0 28 D 0 50 B 0 実際に使ってみると何となく LW よりも飛びが良い感じがした。土日のコンテストで海外の局を呼んでみたら、7, 14, 21, 28 MHz でフィリピンと QSO ができた。また、7 MHz の CW で CQ を出して Reverse Beacon Network を見てみたら米国ネバダ州で S/N 6 dB で受信できていた。単純な LW よりもループにした方が良い結果が出ていると思われる。アンテナに詳しいローカルの OM 局にお聞きしたところ、指向性パターンが変わったのだろうとアドバイスを頂いた。パターンが変わって建屋に吸い込まれる電波が減ったのかもしれない。
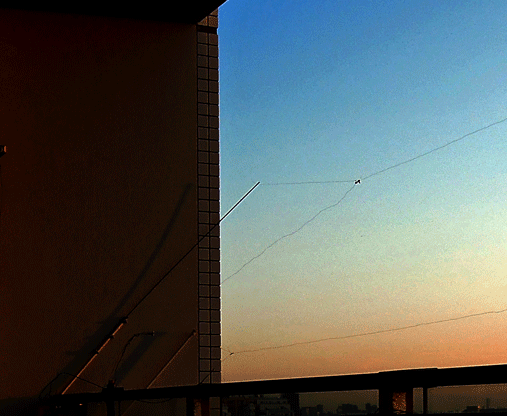
ミニループアンテナ Φ0.5 mm のワイヤーが写るのは夕暮れ時だけ
![]() 2017-03-04(土) アローライン AL-207F の SWR
2017-03-04(土) アローライン AL-207F の SWR
ベランダに設置している V/UHF 用アンテナ(アローライン AL-207F(H)-MR)の SWR を測定してみた。
SWR 計は簡易型の SX27P。
UHF(430 MHz)は中心周波数が 435 MHz でちょうどハムバンドの中心になっていたが、VHF(144 MHz)は中心周波数がバンド内になかった。どこに合っているのかを MFJ-259C で探してみると、中心周波数は 142 MHz 付近だった。バンド中心の 145 MHz から見ると 3 MHzほど低かった。 設置場所を変えると中心周波数が変わるので周囲の影響を受けているようだ。試しにラジエータを少し上げてみると中心周波数が下がった。短縮コイルやコンデンサー、位相反転コイルなどが付いているため調整の難しいアンテナだ。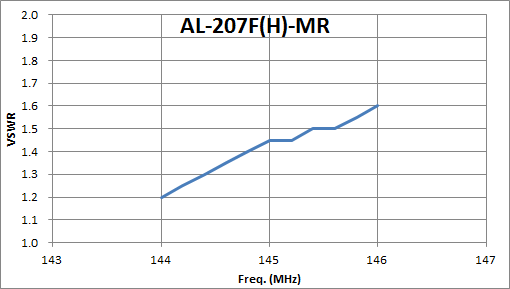
AL-207F(H)-MR の SWR試しに室内に仮置きしたモービルホイップアンテナ SG7500 の SWR を測定してみたら、144 MHz 帯の中心周波数はこちらも 142 MHz 付近だった。何故だろう。
![]() 2017-02-28(火) LW
インピーダンスの凸凹はアース側の特性
2017-02-28(火) LW
インピーダンスの凸凹はアース側の特性
ロングワイヤーアンテナ(LW)の測定でエレメントの長さや折り返し方法を変えてもインピーダンスについてはピークやディップの周波数が変化しなかった。従ってこの凸凹は FC-40 に接続されたアースの特性を反映していると思われる。
ピーク周波数を見ると最大ピークが 12.9 MHz でその 1/4 λは 5.8 m になる。手すり(アルミニウム製)の長さが 5.85 m なのでほぼ合っていた。
すなわち手すりがカウンターポイズの役目を果たしていることが確認できた。
インピーダンスのピーク周波数は HF バンドにはかかっていなかった。
ピーク周波数 f(MHz) f の波長 1/4λ(m) 比率 f/f0 倍 数 6.6 11.4 0.5 2/4 12.9 (f0) 5.8 1.0 4/4 20.1 3.7 1.5 6/4 25.5 2.9 2.0 8/4 38.8 1.9 3.0 12/4 また、ディップ周波数は下表のようにこちらは運悪く 10 MHz バンドがディップ周波数にあたっている。これが原因で FC-40 ではチューニングできないようだ。10 MHz 用のカウンターポイズ(7.4 m)を追加すればチューニングできるかもしれない。
ディップ周波数 f(MHz) f の波長 1/4λ(m) 比率 f/f0 倍 数 10.0 7.5 0.8 3/4 16.2 4.6 1.3 5/4 22.9 3.2 1.8 7/4 現在のロングワイヤーアンテナのインピーダンスは、12.9 MHz の 1/4 の周波数の偶数倍がピーク、奇数倍がディップとなっていた。
![]() 2017-02-25(土) ロングワイヤーの SWR その3
2017-02-25(土) ロングワイヤーの SWR その3
ロングワイヤーの折り返し部分が同調周波数に影響していることが分かったので、U 字部分を更に長くして 58 cm にしてみた。
前回の約 20 cm の時の同調周波数は 7.13 MHz だったものが更に下がって 6.96 MHz になり、計算上の 6.8 MHz に近づいた。一寸下がりすぎたのでエレメントを少し短くして以前使っていた 10.8 m に戻した方が良いかもしれない。
相変わらず 10 MHz は FC-40 ではチューニングできないがそれ以外のバンドでは使えるようだ。
折り返しの U 字部分の長さを 58 cm に伸ばしたロングワイヤーの SWR と インピーダンス Z
折り返し前後のエレメントの影響が減った分効率は上がっていると思われるがコンディションや壁からの距離の効果に比べれば微々たる差だろう。
![]() 2017-02-23(水) ロングワイヤーの SWR その2
2017-02-23(水) ロングワイヤーの SWR その2
現在使っているロングワイヤーのエレメント長は約 11 m。このエレメント 2 本でダイポールアンテナを作ると同調周波数は短縮率が 0 でも 6.8 MHz となる。先日測定した時の同調周波数が 7.35 MHz だったので 8 % 高い。エレメントの折り返しが実効長を短くしているのだろう。
そこで折り返し部分の形状を V 字型から U 字型(折り返し部分の上下エレメント間距離は約 20 cm)に変更してみた。 SWR や Z のパターンはそれ程大きくは変わっていないが、同調周波数は少し下がって 7.13 MHz になった。計算上の 6.8 MHz に比べるとまだ 5 % 高いが 7 MHz のバンド内に入ったので、7 MHz 帯はアンテナチューナー(FC-40)なしでも SWR 1.5 以下で利用できるようになった。 21 MHz 帯は FC-40 のチューニングが安定しないが何とか使えるようだ。
折り返し部分を U 字型にしたロングワイヤーの SWR と インピーダンス Z
![]() 2017-02-15(水) ロングワイヤーの SWR
2017-02-15(水) ロングワイヤーの SWR
アンテナアナライザー(MFJ-259C)を買ったので、ベランダに設置しているロングワイヤー(LW)の特性を測定してみた。
FC-40 のコントロールケーブルを FT-991 につないだまま FT-991 の電源を ON、TUNE OFF の状態で FC-40 からの同軸ケーブルを MFJ-259C に接続して測定した。
LW のエレメント長は現在 11 m になっているが、同調周波数は 7.35 MHz だった。その上の同調周波数は、19.0,32.1,44.7 MHzで、これらは 7.35 MHz の 2.5倍、4.5倍、6倍となっていた。残念ながらこれらの周波数はどれもハムバンドには合っていない。ただ、周波数が高くなるほど全体的に SWR が下がっていくようなので、エレメントは長いほどチューニングが楽になるようだ。
また、インピーダンスZ(Ω)は SWR よりも山谷が多く、中でも 10 MHz は 4 Ωで FC-40ではチューニングできない程低かった。
ロングワイヤー(LW)の SWR と インピーダンスZ(Ω)
試しに LW のエレメントを 40 cm 長くすると同調周波数は 7.15 MHz になったが、21 MHz が FC-40 ではチューニングできなくなったので元に戻した。
![]() 2017-02-12(日) MLA
を試してみる
2017-02-12(日) MLA
を試してみる
ベランダでもDX が出来ると噂のMLA(マグネチック・ループ・アンテナ)を試してみた。購入したのはフィールドアンテナのMK-2AM とカメラ用三脚(HK-836B)。目立たないようにループエレメントは黒色のビニールテープを巻いた。
ベランダに仮設置した MLA(マグネチック・ループ・アンテナ)まず、デフォルトの21 MHz でループを垂直にしてベランダの中に設置した。大田区の局と交信した結果、ロングワイヤー(LW)に比べて10 dB ほど送受信とも低かった。
ベランダの中に置くとノイズが大きくて使えない。前面に出すとやっと使えるレベルになる。ところが更に前へ出していくとロングワイヤーの近くになるためかSWR が下がらなくなった。MLA はかなり周りの影響を受けるようだ。設置場所でノイズや特性が大きく変わるので使いづらいアンテナだ。
次に水平偏波にしてQSOしてみた。
グランドウェーブでは多摩市や市川市の局と59で交信できた。
ところが沖縄の局が良く聞こえたので呼んでみたが全く応答がなかった。また垂直偏波に戻してマニラの局を受信すると確実にLW の方がS が強く了解度も上だった。垂直では指向性が出るそうだが向きを変えてみても差がよく分からなかった。
MLA を水平で使用するときはLW を下げる必要があり簡単には比較ができないが、今の所性能的にはまだLW に負けている。1 つの望みは無指向性を利用した北海道方向への飛びでこれから時間を掛けて試してみる。
![]() 2017-02-04(日) ATOK
2017 購入
2017-02-04(日) ATOK
2017 購入
昨日( 2 月 3 日(金))発売された ATOK 2017 の DL 版を購入した。
ATOK の購入は殆ど恒例行事になっている。今流行の AI 処理で誤変換が減っているらしい。今の所不具合は出ていない。
![]() 2017-01-16(月) FT-991
のファームウェアバージョンアップ
2017-01-16(月) FT-991
のファームウェアバージョンアップ
八重洲無線のウェブサイトを見たら FT-991 のファームウェアバージョンがだいぶ上がっていたので、更新してみた。
ファームウェアのバージョン
ファームウェア バージョンアップ前 バージョンアップ後 MAIN 2-13 2-17 DSP 1-05 1-09 TFT 2-02 2-04 C4FM DSP 4-10 4-15
バージョンアップ後の確認画面 バージョンアップ後に何か変わったところがあるか見てみたが、Sメーターの振れなど期待していたところは変わっていなかった。
![]() 2017-01-10(火) REVEAL
402 の EQ
2017-01-10(火) REVEAL
402 の EQ
ZENSOR1 に続いて REVEAL 402 についても DR-40 で音響特性を測定し REW で EQ を作成してみた。
結果は下図で、部屋の反響音よりもスピーカー特性の補正となっている。確かに音は EQ を掛けた方が自然に近い。意外だったのは 11 kHz 付近のピークで、無指向性(全指向性)マイクではこのピークは左側のスピーカーだけにしか出なかったのが、DR-40 で測定すると右のスピーカーにも出ることだ。このあたりも単一指向性マイクの方がより正しい結果となっているような気がする。
REVEAL 402 の補正曲線
(DR-40 で音響特性を測定し REW で EQ 作成)78 Hz と 135 Hz は部屋の反響、11 kHz 付近はスピーカーの特性補正となっている。
![]() 2017-01-08(日) DR-40
のマイクで補正
2017-01-08(日) DR-40
のマイクで補正
前々からルーム補正用の音響測定に無指向性マイクを使う事に疑問を持っていた。
無指向性マイクで録音した音を聞くと反響音が聞こえて、通常聞いている音とは違っている。これで補正すると恐らく本来の音は出ない、部屋の共振補正量を低く抑える方が良い結果が出るのもこれに起因するのではないかと思っていた。そこで本体に単一指向性マイクが付いているリニア PCM レコーダー DR-40 で音響測定して補正を試してみた。
結果は予想通りで、無指向性マイクで測定・補正した時よりも聞きやすい音になった。共振ピークも無理して低く抑える必要がない。と言うよりも共振ピークがそれ程顕著に表れないという方が正しい。こちらの方が本来の補正特性に近いと思われる。
これなら REW で作成した EQ でも十分使えそうだ。赤色線が左 SP 、緑色線が右 SP の補正曲線 音響特性測定時はマイクを正面向きにする。2 つのマイクで測定したデータを REW で平均化して EQ データを作成。
ただ、DR-40 の内蔵マイクは特性がそれ程良くないので、UMIK-1 でキャリブレーションした値で補正するのが正しいだろう。DR-40 内蔵マイクの感度曲線は下図の通りで、それでも 80 Hz 〜 12,000 Hz の範囲では±2 dB 以内に入っていた。
DR-40 内蔵マイクの感度曲線 これからのメインマイクは DR-40 になりそうだ。
今回は入力インタフェースに US-366 を使ったので操作が複雑だったが、直接 PC のライン入力を利用すれば簡単になるだろう。
![]() 2017-01-03(火) REW
でマイクの特性を比較してみた
2017-01-03(火) REW
でマイクの特性を比較してみた
最近音響測定で標準的に使っているマイク UMIK-1 と以前使っていた EMM-6 の特性を REW で比較してみた。REW は 2 つの測定値(dB)の四則演算ができるので、UMIK-1 と EMM-6 の測定値の比をとることで感度差が計算できる。
音響測定用マイク(今回比較したのは一番上の EMM-6 と中央の UMIK-1) スピーカーの特性を測定した時の両マイクの値の比をとってみると下図のようになった。2 つのスピーカー(REVEAL 402 と ZENSOR1)で試してみたが結果は良く一致している。
UMIK-1 の感度/EMM-6 の感度 これを見ると UMIK-1 と EMM-6 との感度差は 50 Hz 〜 20 kHz の範囲では±2 dB 以内だった。
このパターンは UMIK-1 のキャリブレーションカーブに似ているので miniDSP 社のキャリブレーションデータは信用できそうだ。逆に EMM-6(Dayton Audio)のキャリブレーションデータは使えない事が確認できた。今回の結果と UMIK-1 のキャリブレーションカーブから EMM-6 のキャリブレーションカーブを推測すると、EMM-6 の方が特性はフラットと思われる。
|
|
![]()
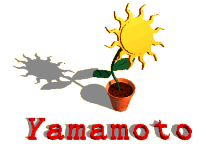
 ホームページへ戻る
ホームページへ戻る